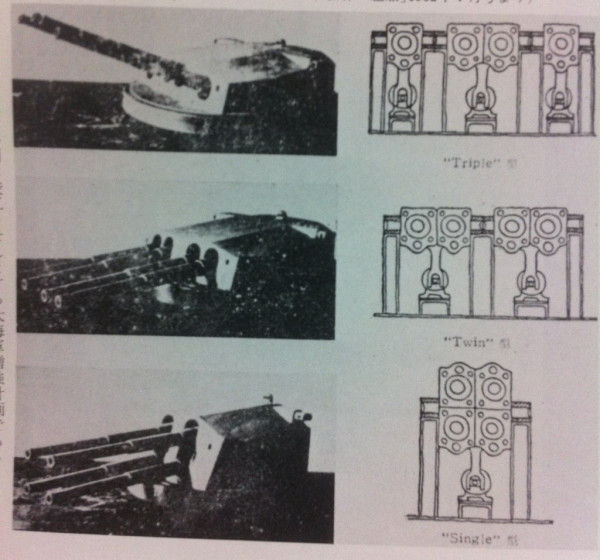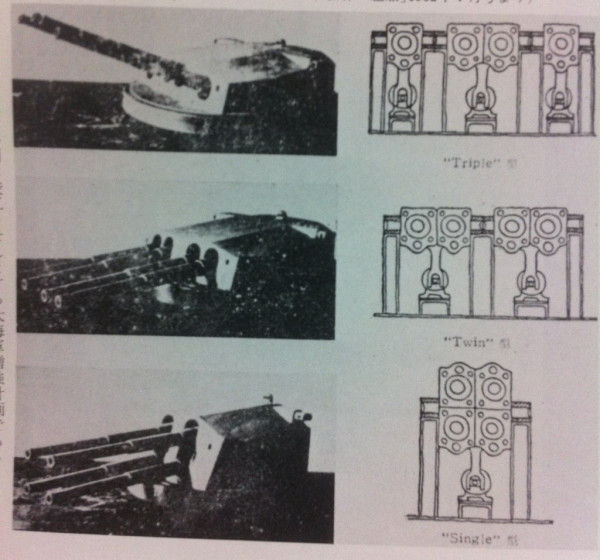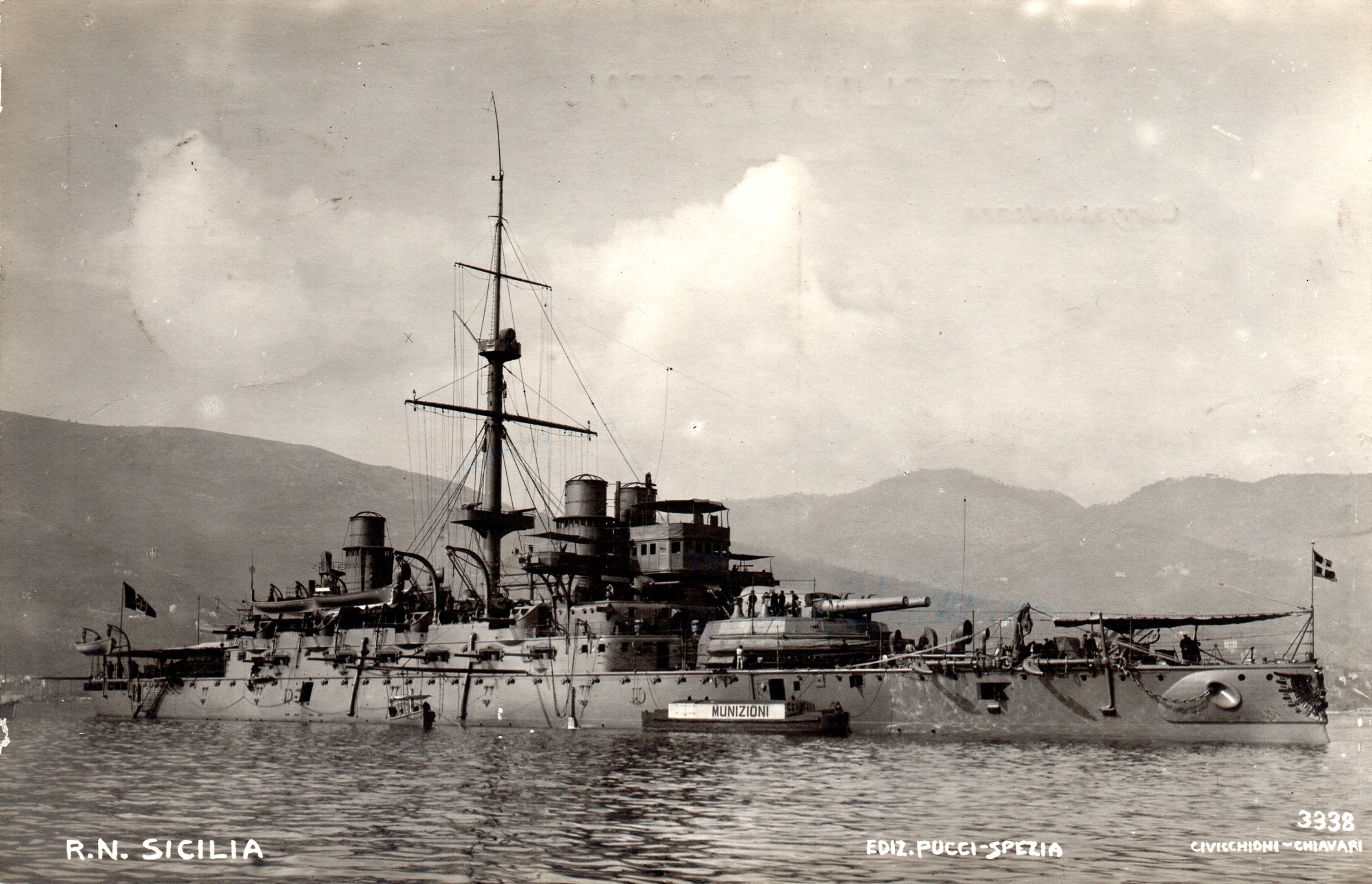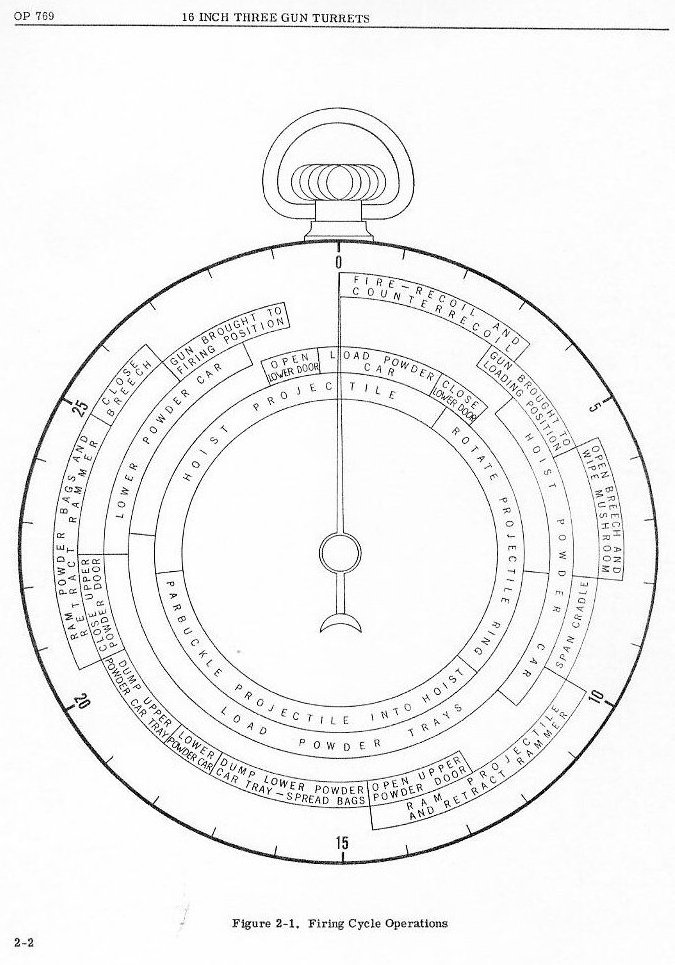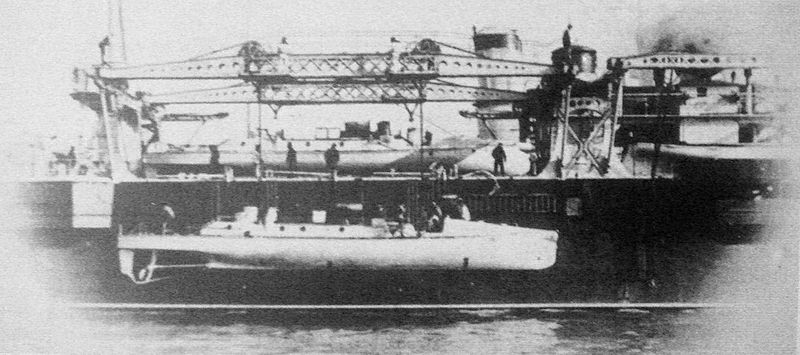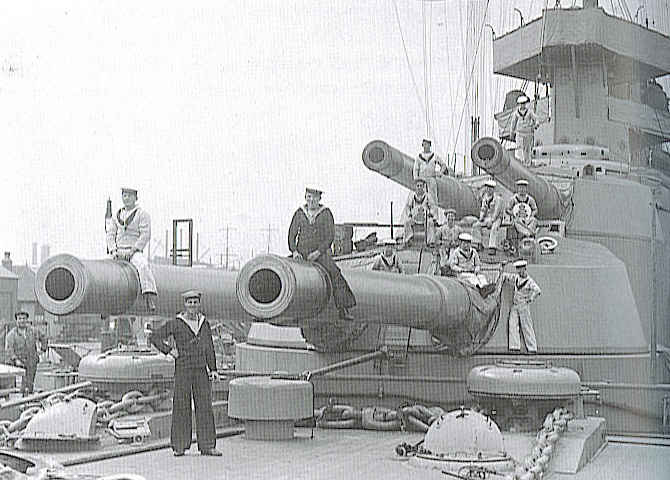�������ȗ��R�ɂ�鏑�����݂̍폜�ɂ��āF �����p�V �Ƃ݂������:�y�R���z - �V�E��̓X���b�h74�����C�� YouTube����>3�{ ->�摜>29��
����A�摜���o �b�b
���̌f����
�ގ��X��
�f���ꗗ �l�C�X�� ����l�C��
���̃X���ւ̌Œ胊���N�F http://5chb.net/r/army/1520287947/ �q���g�F http ://xxxx.5chb .net/xxxx �̂悤��b �����邾���ł����ŃX���ۑ��A�{���ł��܂��B
�͂̌��c���C�����E�T�u��������
�Ō�̐�̓��@���K�[�h�܂�
�{�����E�v��͂�
�F�X���܂���
�O�X��
�y�R���z - �V�E��̓X���b�h73�����C��
http://2chb.net/r/army/1516458670/ �O�X���@999 ���O�F�������O����
���{�C�R��3�����[�g���̖C���_���Ă�����
�\�O���^���m��͂ɂ��ĂȂ�
���̌�������41�W���A���C���ڂ�12�傩��14��͂̕����\�������݂��������ǂ�
>>5 �����Ȃ��ᓖ����Ȃ���B�d���Ȃ��B�R�l�̓G���W�j�A�ł��Ȃ���
>>9 ���[�_�[�������ꌩ���Ȃ��V�������z���X�g�́A���[�_�[������DOY�ɐ���̂Ȃ�������Ă��d���Ȃ���
�d���Ȃ��ƌ����Ȃ��璾��ōs���̂����̔��w����
>>9 �����̎ˌ���@���Ⴛ�����낤�ˁB
�����ƕ��ʂ������Ă��A����ŏƏ��ł���킯����Ȃ����B
>>10 ����ŃJ�b�R�������ƌ����Ă����Ȃ́H
�i���̂Ȃ��҂͌����ď��ĂȂ�
>>5 �܂��A�����炪�����Ȃ���A������������Ȃ��B���E�������ڋߐ�㓙�̐���������邩��A�S�C���͌��������̉������C�킾���l����Ηǂ��A�Ɩ��������ɕ��j���肵���낤���ˁB
�����đO��n��͊����̑��̓V���B
���{�C�R�͖{�������𗘂��Ĉ�C�ɋ������l�߂āA
>>6 >>7 ���ɂ���A�V��^�̉��nj^���x�ł�50���a16�C���`12��ŏd���b�̃T�E�X�_�R�^�^�ɂ͎��������Ȃ��A�Ƃ����F����13�����퍂���\���̏o���_�Ȃ̂ŁA�T�E�X�_�R�^������d�l��ڎw�����ƂɂȂ�͕̂K�R���Ǝv���B
�܂��A����������ƂČ����̍��͂ł͋I�Ɍ^���H�����������C�����邯�ǁB
���ɗ\�Z�����Ƃ��m�ۂ����Ƃ��Ă��֓���k�Ђ��������ȁE�E�E
������h���C�R�R�k��c�ɉ�����ė~����������
>>16 ���Ȃ~�߂Đ�͂�����Ă�Ηǂ�����
>>18 ��������1920�N��ɓ��{�̍����͕��Ă������ˁB
>>19 �����I�ɂ͎��͑債�����Ɩ��������肷��B
>>20 �z�ʂ̌�����ς肾�����ĕʂ����C�ɂȂ��Ă��Ȃ�
>>21 ��͑�a�̌�����1��6285��4750�~�B�N�Ԉێ����340��5373�~�B
�ێ���͌�����̖�2�p�[�Z���g�قǁB
5�疜�~��͂̈ێ���͖�100���~���x���낤�B�債�����Ɩ����B
>>22 ��͂�n��������
�ǂ����R�g���鎖�ɑ��鑼���̔����∳�͂Ȃz���o���Ȃ���������ȂȒP�ɑ��ł⍑�łƌ������낤
������͂������ׂĕ⏕�͑��₳�Ȃ���ɂ������Ȃ����A�C�R����剻����Η��R�������͊m�ۂׂ̈Ɏt�c������������
�ŌR���ɑ�ʂ̘J���l�����D����}���p���[�ˑ��̓����̓��{�o�ς͒v���I�ȑŌ����邵�A�R�g�ő����G�ɉĂ���Ό����߂ɋ@�B�����Ȃ�Ă̂������ɂȂ�
�܂荡�̖k���N�݂����ɂȂ邾������
���R�̓J�E���^�[�N�[�f�^�[�Ŗő���ɂ��ė\�Z��팸�A
�������^�݂����ȊȈՐ�͂ł��Ȃ��Ɩ���
������ȈՋ����Ă̂̓R���b�T�X���G18�^��炠�邯��
>>26 �������ƈ���ĊȈՌ^�ɏo����v�f���Ȃ�����A��͂́B
>>22 >>27 ������Ƒ��b���ȈՂɂ��ăn�b�V���n�b�V���Ȋ͍�낤���B
���V���g�����R������āA�R�k���[�h�R������Ă����Ċ֓���k�Ђǂ�����́H
�o�����Ă̂͊C�R�^�c����o�����ˁB
�ȈՐ�͂Ƃ����Ɨv�ǂ���ė��p��16�C���`�C��3��Ɠ����A���傩�牺�낵��14�T���`8��A�������牺�낵��12�Z���`���p�C12��
�ȈՐ�͂���R�������C�𗬗p���锤�������p�v���͂���������Ȃ��́H
>>33 �q�����ʎY�^��͂Ƃ�����������w
�O�X���̃A�C�A���f���[�N�Ƌ����ł���Ηǂ��Ƃ����A�O�����x���c�Z�p���Ȃ狃�������Ȃ��
>>23 �����펯�ōl���đ����̈��͂͗L�蓾�Ȃ��B�v�v�P�̒Ɏ��
����ǂ���ł͂Ȃ��̂ŁB
�܂��C�R����剻����Η��R���E�E�E���L�蓾�Ȃ��B�\�Z�������̂ŁB
�������R�k�����͂˂��Ă����Ƃ�����A���ɍ���ŗ\�Z���ʂ��Ă���ȏ�
�����͑��͍�邵��������B���Ȃ���ΊC�R���\�Z�𒅕��������ƂɂȂ邗
���ꂾ��������j�]�܂�������Ƃ����Ă��Ȃ���ł�����
>>35 ��ꎟ���̒Ɏ肪�����ɂȂ�Ȃ�����R�g�~�߂Ė��͋x�{���ĉ��ď�������v�c�����Ă����
����Ȓ����ő債����Q�����G���ň��̂ڂ�������������m�̎R�����R�g�ŋْ��Y�ݏo�����炻���L�`���`�̈��͂�������
���{�s��Ȃ̂ĂĂ����E���a�œ����闘�v�̕����傫����
>>30 �k�Ђ͎j���ʂ�ɑΏ������炢������B�؋��Ȃ�Ăǂ��̍��������Ă�킯�����C�ɂ��邱�Ɩ�����
WW1��̃C�M���X�Ȃ��GDP��200�p�[�Z���g���̔���Ȏ؋�������Ă����킯����
�����̋������{�͑A�܂������Ă���
�ŁA�\�Z���������痤�R�͑�l�������Ă���H
>>38 �j���ʂ�ɑΏ����邨��������܂��H
�j���ȏ�ɌR���ɋ��g���A�j���ƈقȂ葼���̉����������A�j���ȏ�ɎY�Ƃ͒�����łɑς����Ȃ����ĎO�d����ǂ����������ł����ˁH
>>34 �܂��D�c��q�Ȃ�R���̑��x�ł��[���₵
�S��QE���ɂ���1�ǂł�15�C���`�C��͂������������Ō��傫���̂ł�
�A�C�A���f���[�N�Ȃ����^�C�K�[��1�ǎc����������
34cm�C�e�̂Ă��Ȃ��Ȃ�킯��
>>36-37 �@
>>39-40 �R�͂̌�����Ȃ�Ď��ۂɂ͑債�����Ɩ�����B�푈�̔�p�Ɣ�ׂ���B
�푈�̗}�~�͂̏[���������厖�B
�����������ď����͕ʂɈ�v�c�����Ă��Ȃ��B�e���Ƃ��v�f�͂��ꂼ��B
�܂������͑��̌�����i�߂�ΐ��̃f�t���s���������Ƃ��ɘa����邾�낤�B
�j���ł͊֓���k�Ђɂ��k�Г������A���ʓI�Ƀf�t����ɐ����Ă�����
����Ɉ����x�v���X�����B
�����ăJ�l�]��̓��{����e�펑�ތ������ł��鉢�Čo�ϐw���劽�}�B
�R���d�������A��͈ɐ���4��5��n�́A�R�����h��2��8��n�́B�쒀�͐����5���n�́B
�쒀�͂̕����R�����o�J�H�����邵���������B��͎͂��͑債�����Ɩ���
���Ɨ\�Z��������Η��R�͂낭�ɓ����Ȃ��B���R�̘b�B
���m��͐ԏ錚���̎��_�ő��b�����\�͂̌��E����������āA
>>42 �ߋ��X���ŏ�����Ă�������WW�T��̓��{�͋��]�肶��Ȃ��B
�Ȃ�Ɣ敾�������̉p���ɂ��X�ɑ��z�̎؋�(���Ѝ�)�������Ă�����Ă���B
�������č��ɂ��B
�ȂC�R���Ɨ��̎Z���Ōo�c���Ă�ʂ̐��E���̐l�炵����
�����S���C�R�͓Ɨ��̎Z����������
����Ƃ��̎���͊ȒP�Ɏ؋��ł��Ȃ��B
>>4 ��ꎟ���̎��ɕĊ͑����p�C�R�̎w�����ɓ���������
�C����͑��s�����Z�ʂ��Ⴍ�ēƊC�R����ɐ킦�Ȃ��ƍ��]����Ă��̂�
���̊ԂɕĊC�R�͋@�ނ̎��������̋Z�ʂ��啝���サ�Ă�́H
>>6 ��������������Ȃ�A�����̌��E�Ƀ`�������W��������48�����C�ȊO�A41�����C���傫���C��
�吳���ɂ͎�����v�������Ȃ������B
���F�v���̑��u�}���`�v�ł͎���A�v��C���ӂ��߂Ċe�C�g�A�C���A�C�e�̃f�[�^���m�肤�����
�ԗ�����Ă邯�ǁA��a�p�̂��̈ȊO��46�����C�̃f�[�^���Ȃ��B
���Ƃ��Γ����Ȃ�C�e�̌`����3�N���ɂȂ邾�낤���ǁA�C�e�d�ʂ̎��Z�l����Ȃ��悤���B
�吳9�N9���ɋI�Ɍ^�̊͌^����A�����ɑ��D����46�����C�̉\�������J�n�A12����48�����C���ˁA
���ꂪ�吳10�N6���Ɉӌ���\����18�C���`�C�K�{�Ǝ咣���A����30�m�b�g(1�m�b�g�ቺ�܂őË���)
���S����40�����e�ɑ��P���Q��`�Q����(�P���T��`�P���W�炍�܂őË���)�ȂǂƋ�̓I�ɏ����B
�吳13�N�̕���̕��ŁA�����͑��v��̍Ō��4�ǂɂ��ẮA�S�R���܂��ĂȂ�������
�q�ׂĂ���̂�������B
�����A���D���ł͐�����z���ĐF�X�������Ă����悤�����A�p��������͌����ɂ�������ɂ�
46�����C���ڂ̗v���͏o�Ă��Ȃ������͗l�B
>>6 �Ȃ̂�46�����C�J���͌����X�P�W���[���ǂ���Ȃ�Ԃɍ���Ȃ��\����B�\�Z�Ƃ��h�b�N�̋�
���̎���ʼn��N���x���Ȃ�J���͊Ԃɍ������������A���̏ꍇ�A�悭�m���Ă镟��Õv�̑z���}
�ǂ���ɂ͂Ȃ�Ȃ��\�����B
��{���\�͏�L�̕���̈ӌ����ɏ����Ă���̂����ŁA���ɂ͕������͋I�ɂɏ����A�q������
14�m�b�g�łW��C���A���Ċʂ̊������I�ɂƓ���2���Ɏ��߂�A���ʂɐv����S���X��g��������
���Ƃ��S���V�T�O�O�g���ɂ܂Ƃ߂܂���A�\�Z�͂��ꂩ��4�Ǒ���ܐ�ܕS�g���^��S���A���l���l����
�[���^�ɂ���Ή��Ƃ��Ȃ邳�A���Ă����m���B
����Õv����������Ɂu���{�̌R�́v�őz���}�������āA���ꂪ���ɍL�܂�A��������������������B
�v�́A����̐��\�̐��l�́u�[���v���萄���v�f�����˂�����l�̈ӌ��ŁA�p�������͕���Õv��
>>5 ����͋t�B���E���ǂ��āA�Ȃ����I�ɗ��_������ƌ������ɂ������������猂���n�߂Ă����A
�Ƃ������B
>>48 �Љ��Ă�{��ǂ�ł݂�ƁA�������������ˁB���V���g���̋@�ւ̌����̗ǂ��ׂ邽�߂�
�C�M���X�̋Z�p�҂���荞��ł����Ƃ������Ă邵�B
>>49 ���̒ʂ�Ȃ��ǁA
�����41�����C�͊J���̎��ɁA�����A�}�K��14�C���`�C����Ȃ��āA
�C�M���X��45.7����/40���a�C�Ɠ����\���ɕύX����Ă���B
�J���\�Z���F����3�N�Ő����̗p�Ɛv���ɊJ���������Ă邩��A
�C�M���X����̏��A�r�b�J�[�X�̎x�����������ƍl�����Ă�B
�܂�18�C���`�C�̐������͎����Ă��i������Ƃ����ׂ����j��ŁA
���̐��@��48����������ĖC�g�\���̌��E���������ƍl������B
�Ȃ̂ŌR����18�C���`�����ɂ������Ɨv��������ΊJ���ɖ��͂Ȃ������Ƃ�����B
���R��a��46�����C�g�Ƃ͈Ⴄ�\���̕������ǂˁB
���ꂪ46cm�ς݂��������Ƃ��܂ł͂܂��ǂ�
���m�Ɍ����ƁA�I�Ɍ^��2�ǂőł��肶��Ȃ���
���̉ˋ��L��ƂɂƂ��ẮA46cm�C��8��Ă��L�܂����͍̂K�����������ȁB
�Ȃ��قڌ��܂��Ă����Ǝv����͎̂l�C���͂ŏ��Ȃ��Ƃ�41cm�C12��ȏ�A�Ȃ̂�
�T�E�X�_�R�^��50���a�Ȃ���A45���a�C12����x���ᓯ���̖C��͂Ƃ͌����Ȃ���Ȃ��B
>>57 ����̎l�A���C���������������A��傠����̎�C�e����Ë����Ēe�Ζ�ɗe�ς��l�߂�A4�A��4��16��܂ł��蓾������
�Ԃ������43�Z���`�C���J������悩�����̂�
�m�������͑�����͂̎l�A���C���̓��V�������[���Ɏ����A���C�����ׂ��`���ɂ����Ȃ������Đ����������悤�ȋC������
���̓����̎l�A���͋��e�\�͒ቺ�Ō��ǖ��Ӗ�
���e��n�̓m���}���f�B���̕ϑԂ���_���P���N���V�������[�̊�������A���C�R�̃A�N���o�e�B�b�N�ƌ���������ꓬ�ȓw�͂��l����Ɠ����̓��{�C�R�ɂ������܂Ŏv�������A�C�f�B�A���o�ė���Ƃ͂ƂĂ�����Ȃ����v���Ȃ�
�e��l�A���C���̖͌^����Ă��肷�邯��
�A��2���ׂ�Β��x�̍l�������肭�����Ȃ���
�܂���
���{�͍Ō�܂Ō��ݎˌ��d�������ǂ�
�C�̐��𑝂₷�ɂ́A���C�������A�������Ȃ�
>>50 >>54 �ڂ����b�������Ă���Ă��肪�Ƃ�
�\�O���^�͌����I�ɂ�41�W�C12��ȏ�ɂȂ��Ă����\����������
�㐢�ɂ܂��Ƃ��₩��46�W�C���ڗ\�肾�����ƌ����邩��ɂ́A�Ă����蓖������46�W�C���ڂ�O�Ă����̂��Ǝv���Ă�����
�P�ɕ��ꎁ�������̗[���̉��l�����߂��������̂ƁA���܂�ĂȂ�����46�W�C�𓋍ڂ��Ă݂��������Ƃ��͖̂ʔ�����
�����͑��͑��x���d�����Ă����͕������傷��l�A���C���͂��̓_�ł��s��
���̃X���̗��ꂩ��́A�ނ��둽�A���C���J����������f���ɉp���̋Z�p��18�C���`�C�J�����ăI�[�\�h�b�N�X�Ȕz�u�ɂ�������Z�p�I�n�[�h�����Ⴛ�������ǂȁB
�t���[���A�X��18�C���`���Ă��̂܂܂���Ί͗p�r�ɓ]�p�ł��Ȃ��̂��ȁE�E�E
����͓�S�O���n�̃A�C�h����\���W�֒e�C������������ĎO�}�̎�C�ɏo���Ȃ��̂��Ȃ��Ď���Ɠ��`��H
�C�M���X��15�C���`�̂܂܂̂��K���������C������B
����͖{��G3�ɓ��ڗ\�肾�����C���Ƃ͕ʕ��Ǝv������������
>>67 �Ԃ����Ⴏ�J�����Ԃɍ����ĂȂ�
�����͑��͌����X�P�W���[�����^�C�g�Ȃ̂ŁA�A�����m�Ō������邾���Ȃ��
�I�Ɍ^��2�ǂőł���ꂽ�̂����N�܂ő҂ĂȂ�����V��ɉ\�Ȍ���̏d���b����
�Ȃ�Ƃ��T�E�X�_�R�^�Ɛ킦���͂��l�����A�{�i�I�ȑR�n�͗��N�Ƃ�������
����܂�A46cm�C���Ԃɍ����ΗႦ��13���͂�3�Ԋ͈ȍ~��46cm�C�ɂȂ邱�Ƃ��\�����蓾����Ă���
�Ԃɍ���Ȃ���ΊԂɍ��������_�̎�͊͂�46cm�C�ɂȂ邾��
�Ȃ��17�C���`43�Z���`�C��N�����Ȃ������̂��s�v�c
>>75 �͂��͂��B
�N��43cm�C�Ȃ�A�l��44cm�C�ɂ��Ƃ��܂���B
>>75 �t�����X��431mm�C�͈ꉞ17�C���`�����A���̃��[�g���@�ō���Ă��̂ɓˑR�C���`�a�B
>>73 �C������Ȃ��ĖC���̘̂b
18�C���`�̎��������Ȃ��Ǒ���̍œK�������܂������ĂȂ������B
>>75 ������16�C���`�C��͂Ɛ키�̑z�肵���ꍇ17�C���`�ł͗D�z�o���邪���|�ɂ͎���Ȃ�
����Ȕ����ȃp���[�A�b�v�ׂ̈ɕ⋋���������P�����ʕ��ɂȂ�C�����͔̂��߂���
>>79 �����A�����B
>>75 ���ăl�^���X����Ȃ��́H
>>80 �����l�^�ɕt������������������}�W���X�Œׂ��Ă݂���
>>81 �l�^�Ƀ}�W���X����
���������}�W���X�ŕԂ��ƁA17�C���`�e��16�C���`�̏d��2����
15�C���`�ɑ�16�C���`��2����
15�C���`����16�C���`�Ƀp���[�A�b�v����������Ɠ������ʂ��A16�C���`����17�C���`�ւ̃T�C�Y�A�b�v�ɂ͂���
2�����͔����ȃp���[�A�b�v�ǂ���ł͂Ȃ�
�v�悾�ƃh�C�c��H42�^��42cm�������
>>82 16�C���`�C��15�C���`�C�ւ̃J�E���^�[�p�[�g����Ȃ�14�C���`�C�ւ̃J�E���^�[�p�[�g����Ȃ����ȁH
�C�M���X�̏ꍇ12�C���`�C��13.5�C���`�C��15�C���`�C�ƃX�P�[���A�b�v���Ă��āA�l���\����16�C���`�C�͂����܂ł������Ⴞ��
���Ă�12�C���`�C��14�C���`�C��16�C���`�C�Ɨ��Čv��܂߂�Ύ��͑o���Ƃ�18�C���`�C�ɂȂ��Ă��邵
>>85 �M���Ȃ�Ƃ��낶��Ȃ����炱��ȏ㏑���Ȃ����A16�C���`����17�C���`�ւ̃T�C�Y�A�b�v�́A�����ȃp���[�A�b�v�ł͂Ȃ��Ƃ����������������܂�
��C���a�̃X�e�b�v�A�b�v�����p�Ɠ��ĂňႤ�̂͂��̒ʂ肾��
>>82 �Ƃ��낪�v�Z�ʂ�ɂ����Ȃ��̂�1920�N���B
�C�M���X��15�C���`Mk1��16�C���`Mk1�̊ѓO�͂�2���Ȃ�č��͂Ȃ��B
1930�N��Ƃ͈Ⴄ�̂�B
�C���a�k�`�ɉ����������Ǝv�������ǂ��ꌩ�ău�b���
�X�E�F�[�f���l���ϑԂ��I
�悭����q�m�͈ĂȂ��ǂ���ȕϑԓI��C�������@�Ȃ�ď��߂Č���
�C�����i�[����ďo�ė����ł͂Ȃ����̂܂܂ŖC�g�ɋp���ĉ��Ď��Ȃ̂�
���`�����ΘA����S�^���N�n�ߕϑԐ�ԐF�X�����Ă�����ȁc�c�c
>>88 ����͌���̃X�e���X�͂ɂ����g����Ȃ�
���̑����C�͘�p�����ǂ��납���˂��ł��Ȃ��̂�����A����͂Ȃ�ߋ����C��Ȃ�đz��O�����B
>>88 �����܂ł��ċ��Ɏ�C�ςނ̂����m�͂ɔ�s�b�ڂ���̂�������ǂ���ɂ��Ă������Ȏ�����Ȃ�w
>>44 �֓���k�Ђɂ����Z�s�Ǎ���肪���������̂͏��a��\�N��㔼������
>>74 �����͑��͂Ȃ��������}���́H
�S�ʍb�Ǝ�C�����S���z�u�𗼗������Ă�ƌ���Ό��\�D�G�����
�����C���ɂ������A
>>88 �T���N�X�B
���ꂷ�����B�A�j���Ȃ�C�������肠�����Ă���낤�ȁB
�f�X���[�����X�Ƃ��ď�肻����
>>94 �ŏ�����͎�ɌŒ肷�������������
�쒀�̓N���X�̑D�̂ɂ�46�Z���`�C�ς߂���
�����Ȃ���A3�ǂ��炢����Ċ͑��ɓ���Ƃ�������
�悭�����120mm�A�����p�C�H����ɔ��~�^�̔̂����Ĕ�s�b�̃N���A�����X��낤�Ƃ��Ă�ˁA�����ނ�������܂ł�����̂�
>>98 ����G���W�������ɍڂ��Ă�c
�A�j������B�ł悭���鍇�̃��{�݂����Ȃ���ł���
>>99 ���ʐ}�̊͋��O�[����n�܂��Ă�傫�߂̎l�p�`�l�̋�悶��ˁB
����܂��n�͂̋@�ւ͓��肻���ɂȂ����������ǁB
>>100 �h���K���̕����ɂ̓R�}�̔��ˋ@�\����
�A���͂��������Ȃ�������Ƃ�����
�ŋ���ѓ���r�b�O�u���X�g�����e�X�y�[�X�̊W��1���R�b�L���Ƃ���������̓��A���n���ۂ���ł����ǂˁE�E�E
���}�g�̉��˃~�T�C���͂Ȃ��Ȃ��挩�̖����������Ǝv����(VLS�S�ے�̎Q�d���\������)�A�A�����˂���悤�Ȏ������U�@�\�Ɨ\���e���e�X�y�[�X���c
����͕����C�ւ̃I�}�[�W���ƌ�����
>>88 �X�E�F�[�f�����A���͒j�̃��}��
>>92 �������Ȃ��Ɓu�͗�8�N�ȓ��̎�͊�16�ǁv���ێ��ł��Ȃ�����
���N2�ǂ̋N�H���X�P�W���[���I�ɕK�{
���łɗ��R���Վ�ἁX�Ɨ\�Z����_���Ă邩��
�Ȃ��m��Ȃ����ƕ��C�ŏ����̂��Ȃ��H
���R�͖����̑����̂܂܂���������A
>>111 �������Ȃ��Ɣ����ɂȂ�Ȃ�����
����͍���ďI��肶��Ȃ��ď�Ɏ�͊͂̓����8�E����8�ő����悤�Ƃ�������
����ɂ͍Œ�ł��N��2�ǂÂ��N�N�H���čX�V���Ă����ɂ�Ȃ��
���R��͊͂����łȂ��⏕�͂�������v�悾�����̂łƂ�ł��Ȃ��������u�|���葱����v���ƂɂȂ�
���V���g���C�R�R�k��ɑ��_�ł͓��{���R�k�ɉ����悤�Ƃ����̂͑��̈�
��͈�ǂ̔�p�ƈێ�����Ō��āu�債�����ƂȂ��v�Ȃ�Č����͉̂����킩���ĂȂ�����
�k�Е�����p�������ŕ\�ʏ�ɏo�Ă���z���ڗ����ǎ��ۂ̎x�o��p�͂����Ƃ����Ƒ傫��
�������N���ɑ�ւ�肳������ăA�����J���т�����Ȍv�悾����Ȃ�
����y���V��ԏ�͓����N�ɋN�H
�������A���̔����͑��̎����̂����ŁA��̌�q�͑��̒萔���u��q��8�ǁA�w��8�@�v�ɂȂ��Ă��܂����̂����߂���
�������i���ɓ��{�o�ς��������Ă���A
>>117 �ߐ�����68
���傤��3�����邩��L����������Ȃ��H
>>117 ������͖�����{�����O���ɂ��������
�P���l���ŗL�������t���Ă����(�܂��A�������������邾�낤���ǁj
�������J�b�R�C�C�c���▼�O�̐l��1000�l���炢�������Ă��������Ȃ�
��̖͂��O�Ɏg��������h�Ȑl�Ԃ���S�l������Ȃ炻��������͂�S�N�߂̊Ԗ��N����l�Ȕn���Ȑ^�����Ȃ����
�������A���h�����_�Ƃ��J�V�I�y�A�Ƃ��}�b�R�E�N�W���Ƃ��Ȃ�ł�����ɂ��Ă��܂�����
�����炭�A60�N��܂ł͂���Ȃ�ɕێ�I�ȃl�[�~���O�ŁA
3�N��2�ǂ��N�H����16�ǁA24�N�ޖ��Ƃ��Ë������
>>122 >2010�z����ƁA�A�j�I�^�L������������������낤��w
����Ƃ������Ƃ������Ƃ�����
>>88 ����ʔ�����
���߂Č���
�X�E�F�[�f���̓S�g�����h�݂������\�͎w����������������A���������͗~�����̂���
�C�̂Ȃ����́A�������ɓG�͂����A�����Ȃ葊��̎˒����Ƃ����Ƃ��A�G����͂Ȃ瓦���邯�ǁA���m�͂Ȃ瓦������Ȃ�����C�킷�邵���Ȃ��ƍl����ꂽ���
1941�N�̃~�b�h�E�F�C�����Ăł�8�C���`3�A��3��9��̎�C�����Ă邭�炢������
���A�������[�Ńl�[�~���O��W������A
���̓V�c���c�A�{�Ƃɂ���ς���
����o�����M���̃n�C�T�C�N�������͑��v��Ȃ�Ă���Ă���A�O��ڃO���[�v�ɂȂ������C46�W��50�W��������O�݂����ȃ��o�C�͑��ɂȂ肻��
>>130 �܂��g�����͂����̃T�C�N���Ŕp�͂Ƃ����_�g������ȁB
�V�Ԃ���p�Ԃ܂ł̊��Ԃ����݂ł̓o�u������肸���ƐL�тĂ邻�������B
�����͂�����J�̑ϋv���̖�肶��Ȃ��B
�y�����đ�(21)�����z�u���͓�������Ȃ��Ƃ������Ƃ͕ł��Ȃ��v�ƑS�ʃJ�b�g�y�X�e�[�V�����z
http://2chb.net/r/liveplus/1520121841/l50 �܂��A���̍��̐�͂̐i���X�s�[�h���}������������ˁB
>>131 �܂��g��������Ă��A���̐�͎͂j����
���{��͂̂悤�ɖ��������ꂽ�㕨�ł͂Ȃ���łȂ�
�V��������낭�����ۉ�������ĂȂ�������
�A����24�N���1937�N�ɔp�͂ɂ���̂͑Ó��Ȃ�ł́H
�͗�̎Ⴂ�ޖ��͂͊C�O�֔���Ηǂ��������B
����A�W�A�̗Y�A�^�C�ɋ����荞��
�e�^�̂ǂ������͔p�͖��ɖC���̓I�ɂȂ�낤��
�܂��͂�A�o�Y�ƂɈ�Ă�ΏT�Ԑ�͂����ł͂Ȃ�������
>>115 ��q�͑��́u���v�͉��K���J��Ԃ��Ĉ�Ԍ����̗ǂ��Ґ�����I�Ƃ������ƂŁA�������ł��̐��Ɍ��܂����킯�ł͂Ȃ��悤�����B
�j���Ƃ��Ɠ����ŁA���ϓI�Ȑl�Ԃ̔F�m�͂ŊǗ����₷������̐����u���v�Ƃ������ƂȂ낤�B
�ꉺ�͂V�Ɋ��͎��g�̂P�������āu���v�Ƃ������ƂȂ낤�ȁB
�R�k��Ȃ��Ă��p�C�R�̑啝�팸�͔������Ȃ�����
>>131 �C�h�͂ɂ�����ߌ~�D�ɂ�����Ń��T�C�N���B
>>134 �������ɁB���������͑������Ă���ɍX�V��������ɐ��ȉ��̐�͉��l�����Ȃ�ቺ����B
�����^�ł���������Ȃ��ᒷ��Ƒ卷�Ȃ����x���\�����珄�m�͂̕⏕�ɂ��Ȃ�Ȃ��B
��͕�����46�Z���`��C���˂̗l�q�����܂����@�b�ɂ���l�Y�~�͔��˂̏Ռ��œ����Ԃ��܂��Ď��� [809488867]
http://2chb.net/r/poverty/1520511140/ >>146 ����˂�y���ˁA�F���ˁA��Ô˂͎�̖͊͂��ł������ǁA�c�ؔ˂��{���˂͎�͖͊��Ƃ��Ă͂ǂ�����
>>145 �����̃l�C�r�[���[�h���̓��W�L���́A��a�Ɋւ���ŐV�l�����A�����ꐬ���̃����O�C���^�r���[
�������āA���̎ʐ^�Ɏʂ��Ă�̂��������Ɣ��肵���o�܂�A�e�Ԗ�͒��a1�����̑�����@�ƍl�@�A
�������ꂽ25�����A���@�e���j������3�A���łȂ��Ɣ��f�������R�ƁA�����ʒu�̐���܂ŏ�����Ă��B
>>109 ���R�͔����͑��܂ł͋��͂���A�đ呠�������O�҉�k�ō��ӂ��Ă邪
���Ԃ��Δ������ڍ������狦�͂���`���͂Ȃ���
������C�R�Ƃ��Ă̓X�P�W���[���ʂ�ɔ�����i�߂Ȃ���Η��R�i�Ƒ呠�j�Ɍ�����^���Ă��܂��킯��
�܂��A���͂���͔̂����܂ł�����A�������͑��͊W�Ȃ�
�������낤�Ƃ�����A���x�͗��R���瑊���Ȓ�R���\�z�����
�R�k��������̗\�Z�ǂ��Ȃ��������炢���ׂ���H
��x�����\�Z�������Ȃ�ďo����킯�Ȃ������w
���łɌ����A�R�k��̏d�����͑������\�Z�́A
���ꂩ��͑�������Ȃ̗\�Z�͑S���Z�߂ďo���킯���ᖳ���B
�ŁH
���ɑ��Ă̔䗦�Ȃ낤�˂��H
�ނ����͍��̈ō����{�����ƈ���č����ɓs���̈����\�Z�̂��Ƃ������Ɣ��\���ĂĂ��炢�Ȃ���
���̑���u�����ׂ̈ɋ��͂���v��������O�ɂȂ��ĂĐ����Ɏ��R�͖������푈�Ƃ��Ȃ�Γ犘�⎔�������狟�o����H�ڂɂȂ�A������|����A���p���n�������Đ�ԕ����ɓˌ��Ƃ��Ȃ���H
�\�Z���t������S�z�茳�ɂ���Ƃ��v���Ă�l���Ă���ȁB
>>113 �T���X�Ő\����Ȃ����ǁA�u�P�ɖ��L����̔������牏�N���ǂ��E�E�E�v�Ȃ��
����I�Ȕᔻ�́A�����̌R��]�ɂ�����ƋC�̓ŁB
���������W�ǒP�ʂɂ͐�p�I�ȈӖ����������킯�����B
�����m��2��
�����̐l�����̊ϓ_���猩���ꍇ
�����͑��́A�ǂ̂悤�ȉ^�p��z�肵�č\�z�����̂����悭������Ȃ�
���{�C�R�̓��^�͓͂�̔{���A���C�����E�l�C�r�[�͌ܐǁA�ĊC�R�͂Ȃ����O�̔{�����D���B
���{�C�R�̓��^�͓͂�̔{���A���C�����E�l�C�r�[�͌ܐǁA�ĊC�R�͂Ȃ����O�̔{�����D���B
���������A���O�����ƂȂ����m�͂̂悤��
�Ђ��[��Ƃ��Ă��
>>164 2�Ȃ͎���z���A1�Ȃ͌���Ő�����P���ƍl������
�A�����J�݂�����3�Ȃ��Œ���̒P�ʂȂ낤��
�v����̂���������̂���ςȂ��������}�K�i�\��)�݂�����
4�ǒP�ʂō���Ă��܂��̂�1�Ԃ�Ƃ肠���ė��p�������Ă悳����
>>163 �P���ɓ��I�펞�̘Z�Z���Ɋg�債����Ȃ��́H
�Z�����ɂ����̂́A���̕�����͂h���鎞�ɕ֗����ƁA
�ɓ������̖{�ł����Ԑ̂Ɍ����o��������B
�����Ζ�̃y�A�̈ɏW�@�M�ǂŗL���ȈɏW�@�ܘY�����I�푈���ɂȂ������A1�l�̎w���������R�Ɏw���\�ȍő�ǐ���8�ǂ��Ɖ��K�̌��ʊm�F��������Ƃ���������
���͊͋����王�F�o���鐔���Đ����������������H
�ǂ̃��X���j���I�ȍ����Ɋ�Â��b�ŁA�ǂꂪ�l�I�ȗ\�z���u�Ƃ�����v�����Ă���̂��ق�ƕ�������
>>172 ���҂ւ̔l�肪�Z�b�g�ɂȂ������X����Ȃ���Εʂɂ�����Ȃ��H
�܂��������]���ōD������ɍl�����������āu�Ƃ�����v�ł�����
�܂��A���I�푈�̐����̌�������{�C�C�퓖���Ǝ����悤�ȉ^�p���l���Ă����̂͊ԈႢ�Ȃ����낤���ǁB
�㗤���ɂ������̖͂���������������������Ɏ�荞�߂˂�
�������`�{�[���Ȃ��A�����I�ȗ������o�Ă����܂����ȁB
>>176 �㗤���ɕK�{�Ȃ͍̂q��@�ł����Đ�͂���Ȃ�
�q��@�̖�������Ȃ�A
�ڕW�ϑ���i�̖�����͂͏㗤�C�݂݂̂������Ă��A
28�T���`�̂悤�Ȟ֒e�C�Ɍ�����邾���ɂȂ�B
�q��@�̖�������ɗ��ƌ��������͕̂s���ł����Ȃ��B
���Ⴀ�Ȃ�Ŗ��{�͂��������D1�ǂɃr�r�b�č~�������������ł����H
>179
>>179 176�������Ȃ�o�Ă����̂ŁA�q���ɂ͗������ɂ����̂�������Ȃ����ǁA
176��178��1930�N�㖖�ȍ~�̘b�����Ă�B
�����̘b����Ȃ���B
>>176 ���̑O�ɗ����v�ǂ̑�C�ɐ����ɂߕt�����Ă��邵�A�@���ł������ڂɑ����Ă��邩�痤�n�ɐ�͋ߕt����Ȃ�ċ֊��ɓ�������
��ꎟ���̐�P�ł���͂��s���Ȋ�������
�㗤��펞�̉Η͎x���ƁA��͑Ηv�ǂ͋�ʂ��Ęb���Ȃ���
>>179 �܂���ʘ_�Ƃ��āA��͈ȏ�̋��C�𑽐��z��������v�ǂȂ�A��͂ɏ��Ă�B
���������������̓��{�ɂ���ȑ�v�ǂ͖��������̂ŕs���������B
���풆�̓��{�������m�ɐ�͂�����悤�ȑ�v�ǂ��\�z�ł��Ȃ���������
�A�����J��͂Ɉ���I�ɒ@����܂������킯�B���ʁA�ʍӂ̘A����
>>183 ����̓I�����s�b�N���̗\�s���K�Ƃ��Ă̗���C���ƌ���ׂ�����
�Ă��Ȃ�Ŗ����̑���ɓ͂��Ȃ��˒��̋����C�Ƃ̐킢���o�Ă���̂��H
>>183 >>186 ���⎺���ɂ̓}���A�i��B-29���͂��Ȃ��B
����͐�̂�������ŁA�헪����������{�i�I�ɐi�o��������قǐ�������ĂȂ��B
�����łƂ肠�����A��͂̐헪�����I�^�p�̃e�X�g������Ă݂��낤�B
�����̒P�����V�v���͍ڋ@�̓��ڗ͂ł͂�������1000�|���h���e�ꔭ���炢�����ς߂Ȃ��̂ŁA���ԓ����蓊�˒e�ʂ��炷����͍ڋ@��헪�����ɓ���������͌����I�ƍl����̂��I�O��ł͖����B
�v���Γ����̊��⎺���͓��{�w�܂�̎����s�s�ň�勒�_����������A���ꂪ���܂〈��e������
���a�̂܂����~�܂��Ă邩��ȁB���a�p�ЂƂ��Ĕ���o���������
�����͖����Ƃ��Ă��A
>>188 �l��������͖ʔ�����������
�퓬�@���Q�[�����o�ŗ��q��Ԃ��@�e�|�˂��Ă����ƌ�����
>>188 ��͈͂ێ����邾���ŋ��H�����Ȃ���A�L�����p���Ȃ��Ƃ�
���E�q��@�̑g�ݍ��킹�ƈ���Đ�͂͗Z�ʌ����Ȃ�����A���{�̐�͕������=�č��̐�͎��Ɗ�@��
��͈�ǂň�A�������̐l�����K�v�Ȃ���
>>188 �I�O��
���@�������̋�P�̌�Ɋ͖C�ˌ��A��̋Ă镔���̂��V�т݂����ȕ�
���͍ڋ@�͂��̕K�v������Ȃ甽���U������B
�g���b�N��P�݂�����2���ԂƂ����B
�Ȃ�Ń~�b�h�E�F�[�ŗy������Ő�͑啔���ɔR����Q����Ă��납
�����̃R�s�y
����a�C�ɂ��ˌ����헪�����̑���ɂȂ�Ƃ��A�㗤���ɂǂ����Ă��K�v�Ȃ�A
>>198 �l���w�͊C�݂���5�L�������ɂ���
�͑������L����������ˌ������̂��m��Ȃ����A�w�ڏƏ�����͖̂���
�e���������オ��Ȃ��̂Ŏ��͂̒e���C�����s�\
�ԐڏƏ��Ō����Ȃ���A��s�@����̊ϑ����ʂŏC�����邵���Ȃ��A���ݖC��ڏƏ�������Ƃ͈���ē�x�͍���
���̂��߂ɕČR�͐��ɂȂ��ė���C���p�̊Ԑڎˌ��v�Z�@Mk48���J�������Ƃ����̂��O�X�X�����炢�̗���
MK48���g���ɂ͊C�ォ�猩���郉���h�}�[�N�ƂȂ�ڕW�ƁA��������ˌ��ڕW�܂ł̐��m�ȕ��ʁA�����A�W�����K�v�B
>>201 �������AMk48�����@�̋@�B�Ƃ�������͖���
�ԐڏƏ��ɂ��͖C�ˌ��͏Ə���e���C���̓�x�������A�o���������Ă��鐅��C����ȒP�Ƃ������Ƃ͖����̂ŁA���{�{�y�ւ͖̊C�ˌ��̖������������̂́A���ڏƏ���O��Ƃ�����͂ɂƂ��Ă͓�����O�������Ƃ������Ƃ�������������
��͂���̖C������U������������I�Ƃ͌����邪�A���݂ɐڋ߂���̂͋@����n�Ί̓~�T�C���U���̃��X�N�����邵�A�헪�ڕW�͉��݂ɂ���Ƃ͌���Ȃ�����A�U����i�Ƃ��Ă̔ėp���͔��ɗ��
������������炷��ƊC�ォ�狐�e�����A���^�C���Ŕ��ŗ���S�����ʂ͐�傾���ǂ�
>>199 ���j�^�[�Ȃ�Đ��͂͗Ⴆ�ێ�������Ă��g����ǖʂ����Ȃ��Ă��ꂱ���s�o�ς���
���ǁA��͂��G�v�n�̊C�ݐ��߂��ɓ\��t���ė���C���o�����Ԃ��āA���S�ɐ���E���C����
������������Ă邩�炱���o����킯�ŁA�����B���o�����Ȃ�A���Ƃ̍U����i�͂������g����
�����������ŁA���E���I����Ė������ɌR����g����g���鎞��ł͖����Ȃ�����
�L���ƕ������Ă��Ă��ێ���̂��������a�͖C�ς�͂�V�����Ȃ��Ă��A����ȊO�̂�����
�����Ĕėp���������Ă��������g���Ă��܂���E�E�E�ɂȂ�������
�C��͂��痤��ւ̓��˗͂̑��厩�̂͂��܂��ɂ���Ă�厖�e�[�}�̈�ł���
��16�C���`SHS�Ɠ�92��46�����O�b�e
���݂ɂ͂���Ă������C��������Ƃ��Ă��ǂ��ɂ�����̂�
�x�g�i���ł��A8�C���`�C�ł͚��������Ȃ��̂��A�j���[�W���[�W�[��16�C���`�C����
>>203 ���̐S���I���ʂő����ɉ�������������~�������́H
�헪�����Ȃ����̏ĈΒe�ŐS���I���ʔ��Q�A���܂��Ɍ��p����邭�炢��w
>>208 �G�����Ԃƒ��ڂ�肠���Ď��ʊo��͏o���Ă��Ă������ł����ɐw�n�̒��ŖC�e�┚�e�ɎE�����̂͌��������ɂ����Ď�L�͌��\���������Ō����邻����
��퓬���ɂ��s�s�����̋L���Ƃ͂܂��ʕ����Ǝv����
�^�����Ȃł��͖C�ł����ƃX�C�[�v���Ă킯�ɂ͂����Ȃ�������
>>209 �����牽�H
��̖͂C�e������Ȃ�ĊW�Ȃ��ł���B
�r���}��~�C�g�L�[�i���Ⴛ��ȖC�e�~���Ă��Ȃ����ǁH
>>209 ���������A��`��������n�܂��Ė�C�A�����C�e�A�������܂�āA
�^�R��̂Ȃ��Ɍ��@���ĕ����āA�Ȃ��킩���ѐH���āA���ɂ͒��e�ϑ��@���̂�т���Ă�B
�����ċC���G�ꂽ��������オ���ċ��ԂƋ@�e�|�˂���Ď���ł����B
�����Ă�z�͎���F�̏��w����Ĉ⍜�������ċA��B
�ǂ��ɂ��͖C�ˌ����o�Ă��Ȃ��푈���������O�ɂȂ�����������i
�T�C�p���ŏ㗤�O�͖̊C�ˌ��œ��{�R�̔�Q���ǂꂾ�������������R�m���Ă��ˁH
>>211 ��̖͂C���̐S���I���ʂ�ے肷��̂ɉ��̃r���}����̘b���o�Ă���̂��Ӗ���������Ȃ�
��̓��{�R���Ƃǂ�ȂɊ͖C�ˌ��┚���ɋ��|�����Ă����Ƃ��Ă��~�����鎖���̂��i���Ȃ��Ƃ��g�D�I�ɂ́j�s�\����
���Ȃ��炸�P�����������������͖C�ˌ��̋��|�ƈ�ʎs�����s�s�����Ŏ����|���Ꮏ���ʂ���҂��������㐢�Ɏc��̂�������O����
>>213 �����痤��̗�����������H
�C������|����̂͂ǂ�������B
�͖C�����ʂȂ�Ă��Ƃ͖����B
����Ƃ��͖C���ɋC���G�ꂽ���R�̕��m�͎㒎�������Ȃ�Č����̂��ˁH
��킪���U����̂����Đ��_�Ɉُ�����������ĕ��������Ȃ̂��ˁH
>>212 �͖C�ˌ��ɂ�鎀���҂͑S�̂�1%���x�ɉ߂��Ȃ����ē��v������̂͒m���Ă����
����������͖C�ˌ��̍Œ���������w�n�̉��ɐg����߂Ă��邩��ŁA���������w�n��j��͂���ԑ傫�������̂��͖C�ˌ����Đ�P���m���Ă���
�ŏ㗤���J�n����G���������藐���l�ɂȂ�Ζ������������Ċ͖C�ˌ��T���������䗦�I�Ɋ͖C�ˌ��̎����҂�����͓̂�����O
����ł͊���C���Ԃ��\��Ă��������w�n��̂��Ȃ���ʖڂ͌����A����ő�C���Ԃ̉��l�ے肷��z�͂��Ȃ�����H
�㗤�퓬�ł͂��̖�ڐ�͂⏄�m�͂��S���Ă������̘b
>>215 ���ׂ������ɉR�����Ȃ��łˁB
�`�������J�m�A�ɐw�n�Ȃ�ĂȂ��A����������ӂɕ��U���Ă������B
�����������ېw�n�Ȃ������Ă��Ȃ��A�g�[�`�J�����������邾���B
���j�^�[�͂̑�ʌ����Ȃ�Ă��������Ɍ��_�o�Ă��܂��悤�Șb��ɐV���Ȉ�𓊂��āA
�X����グ�闬���������̑�Ȓނ�t
>>203 ���Ɋ��t�B
�͖C�ˌ��̈З͂̂����Ő��ۖh��w�n����߂Ĕ��Ζʐw�n�Ƃ������h��ɐ�ւ����链�Ȃ��Ȃ�������
���˂ł���ڕW������ł���B
>>205 �y��ʂ�16�C���`�l�j-�W�O�b�e��18�E55����
��a��91�������1����33.85����
���Ȃ݂ɞ֒e�͕Ă̂��n�C�L���p�V�e�B�Ƃ�������������
��a�̗뎮��61.7�����ɑ���69.67�����ƌ��a�̂�葽��
�����O�}�K�W���ɘA�ڂ̒���a���n���C�`�p�U���ɓ��������b�͖G�����
���x�͖͊C�ˌ��ے�_���B
250kg�ʏ픚�e�ł����y��100kg,�O�b���e�ł���60kg���邩��ȁB
>>198 ����Ȃɓ����郂�m�ł������B�������ł́B
Mark 7 16-inch/50-caliber gun
http://www.globalsecurity.org/military/systems/ship/systems/mk-7-gallery.htm �A�C�I���̗���ˌ��̒e���}�BTARGET AREA�ɃA�����J���h���ȃy���^�S�����d�ˍ��킹�Ă�B
�ˋ���36000���[�h�ŖڕW�y���^�S���Ȃ甭��16�e�̂���8�������B����Ė�����50�p�[�Z���g�B
�ڕW����͂Ȃ疽�����͐��p�[�Z���g���x
�������j��͂͑傫��
�u�Đ�̖͂C�͕͂ČR5�t�c�ɕC�G����B���{���R�Ȃ�15�t�c�����v
���Q�d�@�x�h�O�@�u��{�c�Q�d�̏���L�v
>>10 �@
>>12 >�@���[�_�[������DOY�ɐ���̂Ȃ�������Ă��d���Ȃ���
>�@�i���̂Ȃ��҂͌����ď��ĂȂ�
�T���X�������Ȃ���̂͗ǂ��B�����A�ǂ���������Ŕ��Ȃ��邩�����B
�싅��T�b�J�[�ŕ������Ƃ��āA��I��Ȃ玩���̃v���C���������A�ēȂ�єz���l�������B
�I�[�i�[�Ȃ�����ƃJ�l���g���ėL�͑I�������ׂ��������A�ȂǁB
���{�C�R���V���̑������ł��Ȃ������B����͍őO���̕��m���I��̔��Ȃ��邱�Ƃł͖����B
�V������������ɂ̓J�l�����Ԃ��|����B�\�Z�̖��B
�J��O�͗\�Z�̑啔���i��7���j�𗤌R���m�ۂ��Ă����B�C�R�̗\�Z�i��3���j�͖R�����B
����āA������t�]�����ČR�����7�����C�R�Ƃ��ׂ��������B�����͑������̂悤�ɁB���ꂪ�u���ȁv
���{�{�y�͖C�ˌ��̈ꎟ�����Ƃ��Ă͂�����ɏڂ�����
http://mt1985.cocolog-nifty.com/naval_strike/2013/08/post-52d3.html �㗤��펞�͖̊C�ˌ��Ɩ{�y�͖C�ˌ��ňقȂ�̂́A�O�҂͓��d�܂ł�
���Ȃ����̖̂w�Ǎs�������~�߂Č����Ă���̂ɑ��āA��҂͂��Ȃ荂���ɑ�
��Ȃ���A���A�ˋ����������_�Ŏˌ����x�ɉe���^���Ă����Ɏv��
����㗤��Ŏˌ��ʒu�ɕt���E�F�X�g�E���@�[�W�j�A
���ΖC�����̃T�E�X�_�R�^
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSOBmsByXzs81fZ1SYILHztneZC0UeefoeGc4PVweKUcp5REJeE �㗤�x���ł͖̊C�ˌ��Ɠ��{�{�y�C�����̎ˌ����ʂ͓���ɂ͈����Ȃ��Ǝv��
�ʂɕd���낵�Č����Ă������̂�B
�K�͂͏��������ǐV�h���Ƃ��y�Ƃ��݂Ă�ƊC��̃{�[�g�̏ォ��]���r�_�������
�y11�z�@�i�E�V�J ���{���v ���E�N���@�@����C�X���G���鍑���@�@��_�@�v�s�b�@�����{�@�`���@�y46�z http://2chb.net/r/liveplus/1520731368/l50 �T�C�p���㗤�O���͖C�ˌ��̑��Q�́A
>>230 �E�E�E���̍s���s���҂��ĒP�ɐ������߂ɂȂ�����
����Ƃ��������Ė��[���o�ɂȂ����̂�
�㗤�x���͖C�ˌ��̑��̖ړI�́A�㗤��Ƃ̖W�Q��r�����邱�ƂȂ���A�G�R���T�̂悤�Ɉ���������Ȃ�A�K�v�ŏ����̖ړI�͒B�������̂ł́H
>>198 ���A�헪�����͍H����ӂ̃C���t���A���ƒn�сA�l�Ƃ܂Ŋ܂߂āu�H�Ǝ{�݁v�ƌ��Ȃ��ēs�s���ۂ��ƏĂ������v�z�Ȃ̂ŁA������H���w���s���|�C���g�ōU��������̂ł͂Ȃ��B
���ӂ̐l�Ƃɓ����������̂��S�āu�����v���B
>>233 ���w���̒�`�Ō���Ă��Ȃ���
�ʏ�ڕW�������Ă���̔j�o�������ō�퐬�����s�ƂȂ�B
������s�@������H��ւ̍ŏ��a29�̔����͖�����7���Ŏ��s�Ɣ��肳�ꂽ�B
���܂��̔���Ȃ�听���Ȃ낤�悗
���l���͖C�ˌ�
�j�~�b�c�͏㗤�n�_�Ɍ�����ꂽ�s�\���ȖC�����ł͂��܂�ɂ��s�O��ł���
���{�ւ̐헪�����́A�m���f���Ə�����g�������ԍ����x������������A��Ԓ���ʔ����ւ̃V�t�g������
�h�䂪�傪����ȌŒ�w�n�قǎ��O�̍q���@�ňʒu���\�I�����̂ŁA���ǂ͏㗤�O�Ɋ͖C�������Œׂ��ꂽ�ł��傤
>>238 �ق��A�J���[�̃h�C�c�C��Q�͑��݉B���ǂ��납��`�܂ł��Ă����A
��������j��ł��܂���ł����ȁB
�����Ĕ����̖C������Ċ͒���ڋ߂����Ȃ��������Ƃ��m��Ȃ��炵���ȁB
>>239 �����炠�̎肱�̎�ōŌ�ɂׂ͒��ꂽ�ł���
�ʒu�\�I���ꂽ�Œ�w�n�͐��E���C�����ꂽ�ł͐����c��܂����
�͖C����v�ǖC�𐧈��o���Ȃ����Č����Ȃ���������
>>234 ���������Ȃ�A���R�̎��͂������̒I�ɕ��蓊���Đl��l�邵���\�̂Ȃ��z����
���͂��킫�܂������w�����i�ߊ���Q�d�̕����܂����ȁB
>>240 ��������������˓����Đ������Ă���ǁH
�C�ݐw�n���Ă̂͂ˁA���̕��ʂ���̐N�U�h����ΐ����Ȃ�B
>>243 >�C�ݐw�n���Ă̂͂ˁA���̕��ʂ���̐N�U�h����ΐ����Ȃ�B
�㗤�����̋ǖʂɂ����Ă��̐w�n���ΐ��o����͈͓��ɂċǒn�I�ɂ�
���̖�ڂ��ʂ������ƌ�����ł��傤���A���ǂ͏㗤���ɐ��������
�����Ƃ�z����Ă��܂����Ȃ�A�㗤�j�~�̖{���̖ړI���ʂ����Ė�����
�ł����琅�ېw�n�Ƃ��Đ��������Ƃ͌����Ȃ��̂ł́H
���̂܂㗤�R�����ނ��ēP�ނ�������Ȃ琬���Ǝv���܂����B
>>244 ���O���Ɍ������̎肱�̎�Ō��ނ���B
��k�͒u���Ƃ��āA
�T�C�p���ɋ��łȊC�ݐw�n����{�R�̌v��ʂ���� �I��ł��Ȃ��B
�㗤�K�n�̓I���A�C����`�������J�m�A�ӂ�̊C�݂����Ȃ��B
���͂قƂ�ǒf�R��ǁA�����̓��ꕔ���ł��g���邩�ˁH
��͂̎�C�N���X�̖C�͎͂��ۂɍ���Ă�킯����
>>236 ���̕ČR�]���A���{���̕]���Ɣ�r����Ɩʔ����ł��ˁB
�u����ŁA���{�R����茩���͖C�ˌ��̌��ʂ́A�A�����J�R�̕ߗ��ƂȂ������m�̐q��ɂ��u�͖C�ˌ��ɂ��펀�҂̂��܂�̑����ɂ����Ƃ����v
�@�u�͖C�ˌ����ł����낵�������v�u�A�����J�̍ő�̏����͖͊C�ˌ��v�Ƃ̏،�����A���Ȃ�̋��ЂƂȂ��Ă��������M������v(wiki)
�đ��̕]�����Ⴂ�v���͉��L�Ƃ���܂����A
�E�����C�����Ԃ��Z���A�ڕW����������
�E�ϑ��̌P�����s�\��
�E�O�A��������z���Ēe���ߖĂ���
�E���{�R�Ί�̋U���Ɛw�n�ϊ����I�݂ł�����
����甽�ȓ_�����̏㗤��i�O�A���j�ł͂���������P���Ă��邠���肪�ČR�̕|���Ƃ���ł��B
����ł��ȉ��̗��R�ŕs�\���Ƃ���āA
�E50cm�̌��������i�v�g�[�`�J�͖͊C�̒����Ŕ���ł��邪�A���ߒe�ł͔j��ł��Ȃ��B
�E1m�̌��������i�v�g�[�`�J�͖͊C�ł͔j��ł��Ȃ��B
�E�J��W�����O�����̖ڕW�⋗����5,000���[�h����Ɗ͖C�̌��ʂ��ቺ����
�����ł͖͊C�ˌ��̎��ԉ����A�n�`�������B���ڕW�͋ϑ��ŋ͂��ł�
�C�z��������P�b�g�e��i�p�[���e�ň�т��k���Ă܂�����A�܂��ɂ��̎肱�̎�ł��B
�͖C�ˌ��̖��_�͊Ԑڎˌ��B
�C�������ŕЂ��t���Ȃ��ꎟ���͂����I����Ă�B
��͂ɑ���C���̏ꍇ�A200���[�g���~30���[�g�����炢�̓I�̋}���̂ǂ����ɓ�����A����ɐZ������Ȃ蔚������Ȃ肵�ĖڕW�S�̂����ނ��A�������͓����čs���Ă����
���������čl�����
>>249 ���א킪����n�ƒn�����ȓ����w�n��ƈ�ԈႤ�̂́A���͍����Ă��A�C�̏�œG�Ɉ͂܂�ČǗ�������
�킯������⋋������]�߂������̃X�g�b�N�ɗ�������ɂȂ�
�C���͒e���R������w�n��C�����݂ł������͂��������A������͂��͊����ė\����͂���������}����
��R�͂�����
�O����㗤�R�����ނ��ĉ��͂��Ă���Ȃ��ƁA�ǂ����łȗv�ǐw�n�𓇓��ɒz���Ă�������̓W���n�ɂȂ���
�������
�͖C�ˌ��̘b�Ɠ��א�̕�͉��̕⋋����̘b�͕ʂȂ��ǁH
>>254 �����I������b�����Ԃ��Ȃ�A��̘͂b�����r��
�����b�����N������Ă�̂����̃X���Ȃ̂ɁE�E�E
>>251 �@����͂�C��݂����Ȏg��������̂̓A�z������B
���{�S���ɖC����͖̂����A�C�R���ƌ������]�ˎ��ォ���蒼���B
�K�b�`���n���C�U���X���A�ŋߌ��Ȃ��Ȃ��B
>>198 >�@�l���w�ɂ���S���\�������������A�����͎O�\�Z���@>�@�l���w�͑��ԏ���܂L�͈�
�����ɕl���w�͈̔͂�400m�~100m�Ƃ��āA�A�C�I���^��3��m�ł̒��e�p�^�[���E����800m�~���E310m����
���������v�Z���Ă݂悤
�@400�~100�^�i800�~310�j��������16��
�w�Ɍ�����270�����Ă�42����������v�Z�B���ۂ̖����e��36���Ƃ���Α����̌덷���L�邪�����ނˌv�Z�ʂ�
�l���w�̑z�肪������
�l��
>>256 �������f�J���n���������̎咣�i�j�J��Ԃ��đ��l�S�ے肷�邾���������
�m���}���f�B�ɑ���a�v�ǖC����������H
�����㗤���g�͑呹�Q�A���肵����x���͑��̐�͈�A��Ljʋ]���ɂȂ邩���m���
�������̌�̓A�z�݂����Ȑ��̐�͏��m�͕��ׂĔ����ƍ��킹�Ē@���ׂ��Ȃ�I�ĕʃ��[�g����U������Ȃ��K�͂ȋ���������Ĕw�ォ��j������Ȃ�R�}���h�����Ŕj��H�삷��Ȃ肷�邳
�n�������ɗv�ǖC�̑O�Ɏr�R���͍��K�v�ȂȂ�
�v�ǂ̍ő�̈Ӌ`�͒ʂ肽�����[�g���������͂ŕ������邱�Ƃɂ��邩��
�v���Ίe�n��1�l��\�Ƃ����L�����}��2���͗��ɂ��Ȃ��Ă͂������
�͖C�ō����\�֒e�̏ꍇ�A�ǂꂭ�炢�܂��y��ʂ��܂���́H
���������G���U�߂ė������ȓ��ׂ�㗤�K�n�̑S�ĂɂɌ��Ԗ���16�C���`�C�h��̌��łȗv�ǐw�n�т�z���鍑�Ȃ��͂�
�����Ő����͂�쒀�͂ł�������l�Y�~�A���ł���݂�����
����A�ŁA�C�݂Ɠ��ׂ͂���ς莗�Ĕ�Ȃ�����Ȃ�
�T�C�p���A�e�j�A���A�O�A����2�`3��Â�8�C���`�C�A14�T���`�C�̖C�f��ݒu���Č���3���[�g�����炢�̓S�R���N���[�g������݂�����
>>270 �A���I�Ȕ�Q�ɂǂ��܂őς����邩�ł��傤�ˁB
�O�A����̓��{����P�ł́A���O�̏����C�����c�ꂽ�Γ_���ˌ����J�n����Ƃ���Ɉʒu��\�I���W���U������
�h�䌘�łȉB���C��ł����Ă��J��������̒e�Ђɂ�������Q�̗ݐς�A�C�����ɑ͐ς��銢�I�Ȃǂɂ��ˊE�����Ȃǂ�
�ˌ�����Ɋׂ��������ł��B���l����͓Ƃ̏d�h��ȉ��ݖC��ł��N���Ă��܂��B
�����ԏ邩�瑕�b���݂ŊO���Ĉڐ݂����P��8�C���`�Ȃ炠����x�̒��˂ɂ��ς���������
�ǂ��ς��Ă��O����̉��͂�����]�߂Ȃ���A�����W���n�ɂȂ��ċʍӂ��邾���̉^�����Ă͈̂���������ł���
�y�������s��̕��Q���z�@��ꎟ�̓u�b�V���A��̓g�����v�{�点���r�A���{�͕č����p�e���ŕԂ�
http://2chb.net/r/liveplus/1520908871/l50 >>273 >�����ւ̏W���ˌ��łق��͍̚���w�n�ւ̔�Q���y���ł����
���̌��ʂ͒e�����ȓ��{�R�ɂ͒ʗp���Ă��ČR�ɂ͒ʗp���Ȃ��ł��傤
���ہA�����h��{�������ېw�n�ȊO�͊����Ȃ��܂łɏ㗤�O�����C���Ő��������Ă܂�
>>270 ���V���g�������R���đ����m��̓��X��v�lj��ł��Ă�����\���������ǁB����Ȃ瑾���m�푈���}�~�ł��Ă������ȁH
>>276 ���̏ꍇ�ł��T�C�p���E�e�j�A���͕ė̃O�@���ɋ߂�����̂ł���ł��傤
���Ƃ�����܂���p
�����̓A�����J���t�B���s���ł�����x�̗v�lj���i�߂���Ԃŏ��ɂ�蓀������Ă��Ńo�����X�I�ɂ͓��{�s��
�Ȃ̂œ��������˂Ĉ����x�̗v�lj����s����ł��傤
���߂������������ǁA�v�lj��ɂ͌R�`���Ȃ��܂܂��̂�
��p�ɊC�R�H�������݂����\���͂��Ȃ荂���ł��傤
���}����������x�h�십������ł��傤���A�}�[�V�����ɑ�K�͂ȓ������s���قǂ̗]�T�͂Ȃ��ł��傤����
�܂�����@��n�����݂��ď����\�͂𑝂₷�����肪���E����
�g���b�N�͐�O����ڂ����Ă����ŁA�������̂��Ƃ����ł��傤��
���Ǒ�p���g���b�N����K�͋�P�Ŋ�n�͉���������u���ꂽ���A������ӂɗv�ǖC�����Ă����ʂł���H
��p�̏ꍇ�͌R�`�����ԈႢ�Ȃ��s����̂ł�������V���K�|�[�����C�N�ȗv�ǂɂȂ�܂�
>>279 ��ѐ���Č���ɕ��u���ꂽ��ǂ��h��ւ��Ă����ʂɂȂ���Ď��ł���
��p�̗Ⴞ�Ɣ�ѐ���ѐɂȂ��Ă܂���
��p���̂͑傫�ȓ��Ȃ̂ŁA���ꂱ���v�lj����ꂽ�n��͏㗤�n�_�Ƃ��Ă͔�����͖̂����ł��傤��
>>282 �ł��傤��
�ł����̏ꍇ�͑�p�S�y�̗v�lj��ł͂Ȃ��A���I�푈�̗����I�Ȉ����ɂȂ�ł��傤
��p�𐧈�����C�Ȃ牽�炩�̂������ŕK���U��������Ȃ����_�Ƃ���
�����m�푈�Ō����V���K�|�[���̂悤��
�v�ǂ̋��x���ǂ̒��x�ɂȂ蓾��̂��͂܂��ʂ̋c�_�Ȃ̂ŕۗ�
���ꂩ��n�}��ł̓l�b�g���[�N�����ꂽ�������_�Ɍ����Ă��A���_���m���݂��Ɏ���q����̂͏d�C���͂��͈͓������ł��B
���NJ͖C�ˌ��̘b�𓇛א�̘b�ɂ��肩����������ˁB
���̒ʂ�ł�
���א�ƌ����Ă��t�B���s���̗l�ȍL��ȌQ���Ɠ�C�̌Ǔ�������ł͌��܂���
>>287 �Е��̐�͂�����I�ɏグ���艺�����肵�Ă����ċc�_�����藧�����B
�^�ʖڂɋc�_�������Ȃ�A��͓����ɂ��Ęb���Ă���B
�o���Ȃ��Ȃ���߂�B
���ǒ����ł̎������������������������B
>>287 ���ł���o���̂悤�ɉI��ѐ��ƌ��������Ǝv���Ă�z�������č����Ă����B
���\�ȓ��e���ᖳ�����ȁB
�}���A�i�ł����C�e�ł��A�h�q���̐�͂̏o�Ԃ́A�����U�����̏㗤�̌�
����C�����������A����C��œG�D�c�𑒂�̂���̖͂{���I�ȗp�@����
��O���\�������C��͖h�q���������㗤�O�ɍU�����̐�͒��߂Ă����
>>265 �d�ʔ�Ȃ�5%�O��B�Ƃ������e�k���������C�e�ł���30%���Ȃ���
>>284 �R���q�h�[���A�V���K�|�[�����ȒP�ɗ������˂��B
�h�䐳�ʔ������킯�ł��Ȃ��̂ɉ������Ă�낤�B
���������Q���͐��ʂ���͖C�ˌ��Ő������Ă��猾���Ă���B
����Ƃ����ʂ����炻��Ȃ��̍��ȂƂł������̂��낤���H
�ăA�W�A�͑��̌R�`��p���m�͑��̌R�`���ȒP�ɐ�̂�����̂������Ƃł������̂��낤����
�h�[�o�[�C���̈�ԋ��������̃J���[����ȒP�ɏ㗤������̂��������Ƃł������̂��낤����
263�������Ă���ʂ�ŁA
>>292 �{���ƌ����Ȃ��̖͂{���̗p�@�͓G��͂��͖C�ˌ��ő��鎖����
�C���Ƃ��ẮA����ڕW�ɑ���͖C�ˌ���A���D�ɑ���͖C�ˌ������邯�Ǖ����I
���ǂ��ɓG���㗤���邩����Ȃ���炩���ߋߊC�ɔz���������ł��傤��
�ł����ꂪ����Ȃ�����A�㗤�ゾ������㗤���O�ɏo���ƂȂ邾����
���q�l�͉����G�`����Ȃ��ƋC�ɓ���Ȃ��݂���������A
>>297 �A��������ӂ܂Ōf���ɓ\��t���Ėi���Ă�傫�Ȃ��F�B�������������̂��w
>>298 ���邵���ł��Ȃ��Ȃ�ق��Ă�H
����Ƃ������͓������x���̎ғ��m�ł����������Ȃ���AA���~�����́H
>>284 �������ł������H
�u�C�E�q��E�����l�@�X�� �R���헪�E���E��p 28�v
http://2chb.net/r/army/1515417952/ >>300 ���������X���͗��C��S�Ă̑����I�Ȏv�l�͂ƒm�����v��Ǝv�����B
���̃X���ł��A�ł��Đl��l�郌�x���̐l�Ԃɂᖳ�����낤�B
>>296 ��͑ΐ�͂̐킢���A�����m�ƈ���ĉ��x�������������B�Ƃ͈Ⴄ���z��
�p�Ƃł́A��͂�D�c�U����D�c��q���S�O�Ȃ��������A���̌��ʂƂ��Đ�͓��m�̖C�킪�N�����Ă���
���������l�������NJD�F�̎��Ƃ��z���l�p������
>>302 ����̓h�C�c��͂��D�c�U�����Ă���ׂ̑Ώ�
�G��͑R�����牢�B�ł����z�͓��R�����Ǔ��l
�܂��h�C�c��͊J���ł����p�̐�͂�O���ɂ����Ă����悤�ɓG�̐�͑R�����{
�h�C�c�̎��������Ɠ���ł����āA�p���ɂȂlj��B�͂��̕ӓ���
�h�C�c�͓��ꂾ����Ȃ��B
�h�C�c��Z�v����t���X�y�b�N�ł��n�߂���
>>305 10�N�扄������H44���Ăǂ��̉�����L�̘b�ȂH
�h�C�c�̌v�悪��ՓI�ɃX�P�W���[���ʂ�ɂ����Ƃ��Ă��A
10�N��L����H�����6�ǂ���������
H���~6
>>291 �T�C�p���̏㗤�\��C�݂ɐ��10�ǖ��߂ĊC�ݖC��ɂł����邩
�T�C�p������Ȃ��ăp�C�p���Ȃ�悩�����̂ɂȒp�u
>>308 ����������Ƒ҂��ė~����
�h�C�c�̂͑S��26�m�b�g�ȏゾ���A20�`23�m�b�g�̃C�M���X�̋�����͌Q�͒u���Ă��ڂ��
�����Đ�͂ɂȂ�Ȃ��̂ł́H
>>311 ���Ƃ��Ă��h�C�c13�ǂŃC�M���X21�ǂɑR�����H
�t�b�h��i�E�������������ĒE�������Ƃ��Ă��A���������h�C�c�̓|�P��܂߂Ă���
�t���[�h���q�E�f�A�E�O���b�Z���o��������\���c
>>312 �|�P��͊͑���ɂ͎g���ɂ�������j���Ɠ��C���ŁA�V������28cm�C�̂܂܂Ȃ�
�Ώ��m�͕����p�̌����Ɏg���������ǂ��ł���B
���C�I�������\��ʂ茚���Ȃ�A���@���K�[�h�͎j����肨��y�Ȋ����ɂȂ��āA
���C��͑����D�c��q�B�l���\����t�b�h�ȑO�̊͂����l�B
�ŁA�C�M���X�{���͑���13�Ǒh�C�c�V��C�͑���͂�8�ǂ̒@�������łǂ����B
10�N�扄������1949�N�̃h�C�c����
http://www.platz-hobby.com/index.php?main_page=popup_image_additional& ;pID=6002&pic=1&products_image_large_additional=images/sqm0001_02.jpg
����Ȑ��E�Ȃ̂ł��͂��͂̐��͖��ł͂Ȃ��̂ł́E�E�E
https://ja.wikipedia.org/wiki/ �V�W���͑�
>�C�M���X�C�R�͗����̔z����͂ɑ��A�{���͑��Ƌɓ��͑��ɐ�͂�2�����đ�����\�z���������A1944�N���̑z��Ƃ��Ĕމ��͂��ȉ��̂悤�ɕ��͂��Ă���B
>���B����
>�{���͑� - ��͊�10�ǁA��
>���C�I�����~2�A�L���O�E�W���[�W5�����~5�A�t�b�h�A���i�E�����~2
>�h�C�c���C�͑� - ��͊�10�ǁA��
>H���~3�A�r�X�}���N���~2�A�V�������z���X�g���~2�A�h�C�b�`�������g���~3
>�ɓ�����
>���m�͑� - ��͊�12�ǁA��
>���C�I�����~2�A�l���\�����~2�A�N�C�[���E�G���U�x�X���~5�A���C�����E�\���F�������~3
>���{�A���͑� - ��͊�16�ǁA��
>�V��́~4�A�V���m��́~2�A���勉�~2�A�}�K���~4�A�������~4
>>316 ���ۂɂ̓h�C�c��H���O��D�悵�Ă���A44�N���܂ł�3�Ǒ�������肾�������
H�̃X�P�W���[���͒x���Ǝv���
39�N�x�v���2�ǂ��Ȃ�Ƃ��������Ă��邭�炢���H
O���\��ʂ�ɂ͂����Ȃ����낤����AH�~3��H�~2�{O�~2���炢����
�C�M���X�̓C�M���X�ŁA40�N�x�v��Ƀ��@���K�[�h���̌��Ă������Ă��Ă��Łi�������3�N�ő��}�ɐ�͉��j
���̑z��Ƀ��@���K�[�h����1�`2�ǒ��x�lj�����Ă���Ǝv���
>>311 �_���P���N��2�ǁE���V�������[��6�ǁE�A���U�X��4�ǂ�i����t�����X�C�R��
�\���[�Y��6�ǁE�N�����V���b�^�b�g��4�ǂ�1947�N�܂łɑ�����\�r�G�g�C�R��
���u���ăC�M���X�C�R�Ɖ��荇���z�肪�����������I
������͑�R�g���s������A�t���J�̖��c���@�Ŗ������^���ȃC�^���A�C�R�ɉ������Ă�����ĒI
>>318 �A���U�X�͎��ۂɂ̓��V�������[��5�E6�Ԋ́i�K�X�R�[�j����2�E3�Ԋ́j�Ƃ����������邵
���̎����\�z����Ă����ɂ��Ă�4�Ǒ����̂�50�N��ɓ����Ă��炶��Ȃ��H
�\�A�͂����ƍ����ă\���[�Y�̐i�����x��܂����Ă��ǂ��납
�X�^�[�����̂��@�����Ō������i��ł��邱�ƂɂȂ��Ă������Ŏ����I�Ȍ����J�n��2�N�ȏ�Y���Ă�
�܂��C�^���A�̓C�^���A�ŁA���b�g���I���̎��������1�ǁA40cm�C4���g�������\�z����Ă���
�J��P�O�N�扄�����ƁA
�܂�10�N�͖������낤��
�i�`�Ƃ͒�s�x�������̑�����Ƃ������肾������ȁB
�o�ώ����Ȃ��Ƃ����̂ɁA
>>325 ���m�̓����̈����͂����܂ł��Ă��炨�`��
>>325 �o�ς������Ȃ�����푈������ŁB
�؋��ŃN�r�����Ȃ��Ȃ��ċ��n�ɗL����˂����ޓz���݂����Ƃ��邾�낤
�^���R�f�������ł͑I�����߂��Ȃ�ƁA�v�ǍU�����J�n���܂�
>>325 �����̕s�����O�ւ��炷���ĖړI������A����͌���ł����Ă������̏퓅��i��
>>314 >>317
�܁A�����������E�Ȃ�V�����[�i�̎�C�����͑��i���ꂻ�������ǁA�P�Ɏ�C�ڂ�������������Ȃ��͎��Ƃ�������O����Ljʂ͌����x��������
>>328 �^��͒鍑�ł͍c�鑦�ʉ����N�L�O�o�����s�����ł��ˁH
>>330 �O�̂���
���z���E����Ȃ��Ď��ۂɃC�M���X�C�R���z�肵���Ґ�������
�Ȃ̂ł��̎��_�ł͍\�z����Ȃ��������{�̐V���m��́i���b���j�Ȃǂ̌�����܂܂�Ă�
�}�K��4�ǂ��Ă̂́A�C�M���X�I�ɂ͕}�K�ƈɐ��͉��^���x�̔F���œ��N���X�Ƃ݂Ȃ���Ă����Ă���
���������{�̐V��͂��Ă̂̓��C�I���Ɠ����x�����x��40cm�C��͂Ƃ����v���ĂȂ���
H����5���g��������͂Ƃ��l���ĂȂ�
�ɓ��ɖ{���Ɠ������̐�͂�z�����������ē��{�C�R������Ȃɋ��Ў����Ă�̂��B
>���{�C�R���������\�ꂵ�Ă��C���h�m����������t�Ŗ{�����U�������킯�ł͂Ȃ��̂ɁB
��ꎟ����C�M���X�C�R�̉��z�G�͓��{�C�R
�C�M���X���Γ��{�̌���C�ʂƂ����̂�
>>335 �p�C�R���������C�����ɍl���ē��{�C�R�ɗl�ɋp����ɂ������Ȃ������̂́A�吼�m�̋C�ۏ����ł͖����āH
�C�M���X�̑z��ł͖������Ȃǂ�
>>330 �唴�M���̔��t���ŁA�ƌ������Ƃ�
�u�c��É��̈Ђ��������߁v�������ȏo�����R�ɂȂ邵�]�T�]�T
>>337 ���̗��j�Q���������H
>>337 ���������C�M���X��͂��A���ۂ̖C��Ŗ����e����ԏo���Ă���Ƃ��������͋����[��
�ړ��ڕW�ɑ���Œ������L�^���܂߂�
�p��͂������e���o�����̂�
�i�����B�N�A�����Z���P�r�[���A�J���u���A�A�f���}�[�N�C���A�r�X�}���N�nj��A�}�^�p���A�k��
2017�N10�����̋L�����ȁu���̃V���K�|�[��������v
���͂��̍��̔��Ύ��̃T�}�[���̋L�������܂�ɂ��ȏo���Łd
�C�M���X�͕��ʔՂƎˌ��v�Z�@���g�����Ə���z�肵�ăh�C�c����{�͚ˌ����ϑ����Ȃ��疽�����������邱�Ƃ�z�肵���Ⴂ�ł͂Ȃ����B
���ʔՂƎˌ��Ղ��g��Ȃ�������̉����ɂ���Bage��z�͊�{�_�����ȁB
���{��͂̎ˌ��Ղ͂X�S���ǂ܂�łX�W���𓋍ڂ��Ă�͔̂�b�A��a�A�������������B
��͎�C�p�͂X�Q�����������̂Œ�������B���{�ł̗̍p�J�n�͏��a�W�N����ʼn���10�N�Ȃ̂Ńx�e�����ɂƂ��Ă͚ˌ��ŌP���������Ԃ̕����������ƂɂȂ�B
�������ƁA�ˌ��˂��H
>>342 �p���m�͑���������2�ǂ���Ȃ��l�����h��R4�ǂ̕Ґ���
�^��p���s�ɔ����Ė{�y�ɂ�������ȉ�6�ǂ��}���[�ɂ܂킵����
���p���12�ǂł̃}���[���C�킪���������̂ɂȂ��B
>>347 �ˌ��Ղ̌`���ʼn����Ⴄ�̂��Ȃ�ĕ����Ă��A
������̓��������������ȏt�x�݁E�E�E
>>349 ���h�l���͖C�͂Ńe�B���s�b�c�z����B��̉p��͂�����
�{�����炨������Ɨ�����ł���E�E�E
���ʔՂ�ˌ��Ղ������ł��ĂȂ��l������悤�Ȃ̂ł܂Ƃ߂�
���邭���邩��ƕ��ʔՂ̏�ɑ�x�����[�_�[�ڂ����炾�߂���
�e�X�����W�����@�A�B�C�̏������ćD�̎w�����o���܂ł̃v���Z�X�������Ă邪
�ˌ��Ղ̌v�Z�l�ɂ��āA���̌v�Z�l���K���A���̓~�X���Ȃ����A
�S���m���͎����Ōv�Z���ďƂ炵���킹���Ƃ����Ă���B
������͑��I�ՒS���҂̘b�B
http://www.naniwa-navy.com/senki-1-kaiten-itijisyutugekisyasenbatu1.html >>341 ���ˋ@������������Ă̂���ȗ��R������B
352�͎菇�𗅗������Ŋϑ��l��v�Z�̐��x�͎ˌ��ǐ����u�̂��قȂ�B
>>355 �v�Z���x�����ϑ����x����
�v�Z���̂́A���ʏ�̎��͓G�͂̑��Ή^���̌v�Z�ŁA���ǂ̂Ƃ���A���͂ɑ��ēG�͂����m�b�g�łǂ̕��ʂɉ�������̂��߂Â��̂��Ƃ����_�ɊҌ������
����ɒe�۔��Ď��Ԃ��|���Ė����ʒu���Z�o����
���x�����ɂȂ�̂͊ϑ��l�̂ق�
���ʊϑ��͕��ʔՂŏƏ����ɍ��킹�邾���Ō덷�Ȃ��łł��邪�A���͋����ϑ�
���̌덷�����݈ʒu�ϑ��⑪�I�̐��x�Ƀ����ɋ���
�ˌ����[�_�[�̓o��ŁA�����̊ϑ����x�����܂�A���܂ł���グ��������ԑ������\�ɂȂ������Ƃ͔��Ɋv�V�I
����ł�>356���̃����N��ɂ���ʂ�A���I�ł͎͊��͔��̔g��ڎ����邱�Ƃ��s���ł��������ƂȂǁA�ϑ��̋@�B���͍Ō�܂Ŏ����ł��Ȃ�����
�ƂȂ��92������98���̈Ⴂ�͂ǂ̒��x�������낤���Ǝv���ȁB
�G���ʋ������I����G�����ʒu�̌v�Z���@�͂�������������
�y��K�z�z�@�@���E�e�w�E�g���[�_�[�@�@���L���X�g�W�ėՁ����@�@�j�㏉�e���p�V�[�����@�@�y�~����z http://2chb.net/r/liveplus/1521080734/l50 >>354 ��a�Ȃ�āA�����V�̏�ɍڂ�������āA��������ɘc�݂��������Ȃ��̂��Ǝv����
�����V�ɂ̓e���V����������Ȃ��l�ɂ͕⋭���Ă�낤��
>>359 �Ƃ������ϑ��̋@�B���͕��ʂɎ��{����Ă��邪�A���E�s�ǂȂǂ̏ł͓���ł̔�����d�v�Ƃ̂��ƁB
364
���Ă��Ȃ��A�N���C�X�g������Ȃ��x����Ղ�ł͂ǂ����悤���Ȃ�
��͂̎ˌ��ǐ���92������22���d�T�ŏ[�����Ǝv���Ă�����
WW2���O�̉��B���ĂĎv����
��a�̑����V�̕�����21���d�T�̑����̍ۂɗ��ʂɑ���X���K�[�^�[��lj����ĕ⋭���Ă���
>>368 22���͔z�u�ɕt���̖��߂����Ă��瓮�������A�Ȃ��1�����������ĂȂ��̂��Ƃ����ƁE�E
��^�^��ǂ͉��x���������Ȃ��Ɩ{���̐��\���o�Ȃ��̂œd�M���q�[�^�[�ʼn��M���Ă�B
�������ϋv���Ⴂ����A���ғ�������Ɛꂿ�Ⴄ�Ƃ������z��
�Ȃ̂�3�`4���Ԃ��Ƃɓd����Ȃ��ƃ_���B
��G�������Ɏg���Ȃ�����܂����̂ŁA���߂���܂Ŋ�{�~�߂��܂܁B
�̂̃u���E���ǃe���r�Ɠ����ŗ\�M���ĂȂ��Ⴗ�������オ��Ȃ����A���肵�Ȃ��B
���̓d�C�@��̊��o�͒ʗp���Ȃ��B
>>369 �_���P���N���R�v�ŁA��������ł�QE����R���ɂ��R�o���閂������͂�����Ƃ͌����A����ł��܂ł��d����Ƃ܂ł͎v���ĂȂ��������낤�����
�w�ɕ��͑ウ���Ȃ���
�C�^���[�C�R�̓C�M���X����n���C�̐��C����D�҂��ČÑネ�[�}�݂����ɒn���C���E�̔e�҂ɂȂ�̂����Ȃ�B���̂��߂ɗ��R�͐����u���Ƃ����͓̂��{�Ɠ�������
�y�w�f�[�z�@�k���N�̊J�������\�z����X���Q
http://2chb.net/r/army/1515740255/l50 �V�X���l�Ă������痈�Ăˁ�
���B�b�g���[�I�x�l�[�g�ƃ��b�g���I���������Ă���
�ǂ���4�Ǔ��������E�Ȋ����B
���B�b�g���[�I�x�l�[�g�ƃ��b�g���I�̋N�H1�N�O��1933�N�ɁA
�R���e�E�f�B�E�J�u�[���ƃW�����I�E�`�F�U�[�����h�b�N���肵�Ė������J�n
�Â���1937�N4���ɃJ�C�I�E�h�D�C���I�ƃA���h���A�E�h�[���A���h�b�N���薂�����J�n�A
1938�N5�����[�}�ƃC���y�����N�H
�o�ϓI�ɋꂵ�����Ԃ�����������˂��B
���������Ԃ͂Ƃ����ƁE�E
https://ja.wikipedia.org/wiki/ ���b�N�X_(�q�D)
https://ja.wikipedia.org/wiki/ �R���e�E�f�B�E�T���H�C�A
>>325-327 >�o�ς������Ȃ�����푈������ŁB
>�؋��ŃN�r�����Ȃ��Ȃ��ċ��n�ɗL����˂�����
�R�̐l�ԂȂ̂Ɍo�ϑ卑�A�����J��1�Ԑ푈���Ă邱�Ƃɋ^��������Ȃ��̂��ȁH
�v�����������V���K�|�[���܂ł���Ă����l���\�������������ɋA����������̂�
>>377 ���ׂĂ̐푈���o�ϔj�]�ɂ��j�ꂩ�Ԃ�̈�肾�Ǝ咣���Ă���悤�ɁA�����ǂ߂Ȃ��Ȃ�A���P�̖��肩���蒼������������
>>379 327���^�e�ǂ݂��Ă�����
�����Ă��邱�ƈȏ�ɓǂ߂邠�Ȃ��Ȃ�
377�������̓s���̂����悤�ɓǂ߂Ĕ��_�Ȃ�Ă��Ȃ��͂��Ȃ̂����B
>>336 >>4 >�@�p�C�R���������C�����@>�@���悻�ꖜ���[�h�̏��܂ōs��
����͗��j�Q��2017�N10�����̋L���ɂ��ƈӊO�Ȃ��ƂɃ��g�����h���C��̐�P����B
���̊C��ʼn������C����s�����Ƃ���h�C�c�͑������łł��Ȃ������B
���̔��Ȃɂ���p�]���B�ߋ����Ō��������Δ�Q���o�邪�G�͑����m���Ɍ��łł���Ƃ����l���B
�i�����ē��{�ߊC�͎��E�������Ɨ\�z�j
���������p��͓��m�̖C�킪�N������A�p��͍͂����œːi���ߋ����C��ނ��낤
>>381 ���I�D�ʂ����邩�瑊�ł��㓙�B
�������ΐ��C�����ׂ��Ă������Ƃ��ˁB
���G�K��A�s���̎��͓G�Ɍ������Đi�����ׂ��A�������B
���ƌ����ȊO�X�J�X�J�̌��ネ�C�����l�C�r�[�͕��j�ς��Ă�̂��낤���B
���{�C�R���G�ɕ`�����������C������Ď��ۂ͉�݂���������ˁA�p�C�R�̑z��̕��������I������
>>377 �o�ϑ卑���Č����Ă��o�ς̋K�͂��f�J�C�����ŕn�x�̍������痈�鍑���̕s���s���͑���������̃K�X�������Ėʂ͂���
�����ăA�����J�̐푈�͍��͍l�����ɔj�ꂩ�Ԃ�ōs�����Ă��͑卑�A�����J�ɋt�炤���ӋC�ȏ����ɂ��d�u�����Ċ����ōs���������������ɂ����鐕���e���̊J�헝�R�Ƃ͖Ⴄ
>>383 ���{�R�����܂����Ă��Ȃ������X���o���Ƃ��A�b�c�ł́A����������̏��ɓI�ȖC��ɏI�n�����Ɛ푔�^�ŕ]����Ă����
��̂̕}�K�R���������X���b�h�Ƃ����Ă���
>>383 ���{�C�R�͉p�C�R��͂ɂ��Ă���悤�ɁA�p�C�R�Ɠ����悤�ɓˌ����ĖC���킪��{
��͌Q�ɂ��30km�ȏ�̃A�E�g�����W�C��̍\�z�͊G�ɕ`�������͗L�����낤���ǁA�����܂ŊG��`���������ŊG�̎��_�Ŗ��������Ƃ������o����{�C�R�����Ă���̂�
���������\�z�����������ƁA���ۂ̑z��͕ʂ�
>>385 �����͋������l�߂����������ǓG�͑����������Ƃ��Ēǂ����Ȃ������ł͂Ȃ���ˁH
�������C��ɏI�n����ׂ̉������C��ł͂Ȃ��A�������C��̒i�K���瑊��Ƀ_���[�W��^���āA�ڋ߂���܂łɐ�͔���k�߂�̂��{�|�������悤�ȁB
�d���Ƃ��ē��ܘZ��Ẳ������C����ꎞ�Ԍp�����A��C�e�̖w�ǑS�����g�p��ᶂ��A�����G���m�͌��ł̖ړI��B�����A����������{��ᢎ˂��Q���{���͈�ǂɈ�{��������݂̂Ɖ]�ӁB
�������C��̒i�K���瑊��Ƀ_���[�W���̂����҂��Ă��Ȃ�����ڋ߂���܂łɐ�͔���k�߂�Ƃ��܂Ƃ��Ɋ��҂��ꂿ�Ⴂ�Ȃ�
�X���o���͋�����������s��ő�������������̂�
�A�b�c�C��ł͓��{�͑��͓��ɕ�����ċ������Ă�Ε⑫�o�����ȁH
�A�b�c�͂܂Ƃ��ȖC��w�����Ă���������c
>>386 ���̍��̓��V�������[�ŋ�������̓X����Ȋ����Ă���
>>381 >�ߋ����Ō��������Δ�Q���o�邪�G�͑����m���Ɍ��łł���
�f���}�[�N�C���C�������Ȋ����ł��ˁB�P�����[�h���Ă͕̂ʂɂ��Ă��B
�ł��A���{�ߊC�͎��E�������Ƃ����\�z�͂ǂ����炫���낤�ˁH
���{�l�̊��o���ƁA�k�C��������͓��{�ߊC�̕������E�ǂ������Ɏv���邯�ǁB
�Ƃ���Ń}���[���ʼnp���2�ǂ��������ꂽ���A���X�̉p�C�R�̌v��ł�
�����Č���̑O���킽��q��U����(�ȉ���)
�J�펞�ɉp��͂�2�ǂ���Ȃ�7�ǂ��V���K�|�[���ɂ�������{�C�R�̓��X�L�[�Ȑ^��p�U�������낤���H
>>386 ���݂����ɂ���y�ɏ����鎞�ザ��Ȃ�����A���e���n�����ď�������ł邾������
>>399 GF�������j���ǂ���Ȃ���ł���B
>>399 ���Ⴀ�@�������̓n���C�̑���ɃV���K�|�[����P�ł���邩����
�܂��V���K�|�[���͗��U�̔����͈͓������痤�U�ł���肻��������
41�N��������A���\�D�c��q�ƒn���C�ŃC�M���X��͎͂��t����Ȃ��́H
�V���K�|�[����P���͂����ȁB
>>397 >�n���C�̕Đ��8�ǂ͐^��p��P�i�V�ł��N�U���Ă��Ȃ��炵��
�����Ȃ́H�t�B���s���h���R�͌��E�����B
�V���K�|�[���v�ǂ�70���ԑς�����悤�ɍ��ꂽ�B
>>407 ���������Ȃ�������{�����͂̓C���h�m�܂ŏo�����ĉp�͑��Ɍ����点�ł��邩�ȁH
>>406 �ʂ��ؕ��Ă͓�m�����Ƃ������{���͌����˂���댯�Ȍv��Ȃ���
�~���͑��Ɏ��ˌ����̂��E�E�E
���C���{�[�T�̃}�[�V��������U���Ă͊J��1�T�Ԃŏ㗤�������݂ŏo�����鑬�U�v�悾��������
�j���̊J�풼�O�̃n���C�̏���Ή���Ƃ��菀���܂�ŏo���ĂȂ�
>>408 �V���K�|�[���ɂǂ̒��x�̊͑����z������Ă邩�ɂ�邯��ǁA
�������Ď��ƕ����ɐ������邵�A�J��^�C�~���O�ɂ���Ă͊C��ɂ��邩������Ȃ��̂Ŏ��ӊC��̏����ɂ��K�v�B
�}�j����X���o�����ʂ̊Ď����K�v�����A�A�����J���̓����m��ɂ̓n���C���ɂ��o���Ƃ��Ȃ��Ⴂ���Ȃ��B
�Ȃ̂ŏ������x�̐ǐ������C���h�m�܂ł͏o���Ȃ����ƁB
�A���R�͑���1�ǂł���͂���������{���o�����̂��Ȃ�
���̑O�Ƀh�C�c���J�킵�Ă��Ȃ������O��ɂȂ�̂ŁA
�V�[�n���P�[���Ɋ�������Đ����Ȃ������͏o���Ȃ��A�܂œǂ�
�p�{���͑����P�͂Ȃ��Ă��J�펞�ɃV���K�|�[�������
�l�I�ɂ͍U���ł��ăV���K�|�[���̃`�����M�[�v�ǂ�15�C���`3��ƌ��������ɂȂ��ė~�����B
���ォ��̖C���́A�͍ڕ���̂悤�ȃX�y�[�X��d�ʂȂǂ̐������̂ŁA������������n�`���������肢����ł������ł���
�O�ɒe�������Ƃ����邯��
���h���������ʒu�͌Œ�Ŏ��g�͕s���ڕW������
�Ȃ����ƍő�˒��t�߁i�m���X�����炢�j
>>420 �������Ǝv������
�R�͂ɍڂ��悤
>>418 ���̐������ĖC�䂩��C��̖ڕW���������������ȁH
�C�䂩��ړ����Ă�D�Ɍ���������
>>425 �v����Ɋ͖C�ł͖ڕW���ݍ��ނ悤�ɏƏ�����̂�����t�Ȃ̂�
�C��̓s���|�C���g�ŖڕW��_����ȁB
>>426 ����̖C���������ƁA����ȃs���|�C���g�Ŗ���������Ȃ�Ė������ۂ���B
���e�͌��\�A�o�E�g
>>426 ���C�t���̃X�R�[�v�Ől�Ԃ̓��_������
��Γ�����Ƃ��v���Ă�ᖳ�����낤�ȁH
���̃L���C�Ȋ���t�b����Ă��I�I
>>426 ����C������Z�ˌ��₼
��ԖC�Ȃ͑_�������A�Qkm���炢�����E
>�@�i���{���̗��㎩�q���j��155�~���֒e�C�̏ꍇ�A�˒�20�L�������ŁA100���������Ƃ�50�������e����Ɗ��҂���锼�a�iCEP)��300���[�g��
�U�z�E�̍l������CEP�Ǝ��Ĕ�Ȃ����
>>449 >CEP
���������Ɨ��p���[���Ȃ�̂Ŗ����͈͕͂͊��Ƒ卷�Ȃ�����
CEP�����S���[�g���Ȃ疽�����͐��p�[�Z���g���x�Ǝv����
> �䂤�������v�Z����30�����������͂�͂�Ƃ�ł��Ȃ�
�䂤���͎����I�^�N�炵�����A��A��뎚�Ȃǂ��L�ۂ݂ɂ���炵���̂ʼn��Ƃ������Ȃ��B
���Ȃ��Ƃ�����̗��㎩�q���ł͕s�\�Ȑ��l����
�p���C���̃g�[�g�C��38cm skc/34�́A
���C���������肷�邽�߂̗D�ʂ́A�ԈႢ�Ȃ��v�ǖC�ɂ���
>>438 �͖C�Ď˂͖C�O�e���ɉe���^���邩��U�z�E�̑召����������ǁH
�e���͈͂ƎU�z�E�͈Ⴄ����
�͖C�̎U�z�E���Ď��ۂɌ����Ă݂��f�[�^����Ɍv�Z���邩��M�̗h������݂���Ȃ���H
>>438 �͑̂̓��h�͖�������U�z�E���̂�����ɂ������
���łɌR����ˁ[��
�����������������͉��ł������̂�
�͂���œ������l�Ԃ��A�Y�����œ������l�Ԃ�n���ɂ���n���G�}�����y���݂�������
>>445 �U�z�E�ɂ��Ă����Ɛ������Ă�������H
�E�I�b�V�����b�g�̃m�Y�������邾��A�܂��z�����Ȃ���
>>447 ���肪�Ƃ��A�v���Ă��ʂ肾��B
>>446 �܂����Ƃ͎v�����Ǔ��h�C�����Ă邩�疳���̐��x�ŗh��Ȃ��u���Ȃ��C�g����e����яo��Ƃ��v���ĂȂ���ˁH
>>449 ���h�ɂ��Ə��̃Y���ƎU�z�E���ꏏ���Ƃ����b�H
����Ƃ����h�C�������Ă���C�����A�����̋Z�ʂ̈Ⴂ�̘b�H
�������͓��h�ɂ��͑O��ł̂˂���A�Ђ��݂��e���^������Ęb�H
>>436 �͖C�̖C�e���݊�����������̂����C�x�����u
�A���A�O�A���̖C���v�ǖC�����邵��
>>451 ���ʂ͂��邯�lj����܂ł͂ł��Ȃ���ˁB
http://www.warbirds.jp/ansq/21/B2001881.html �ǂ������匾���낤���ǂ�
>>453 ����͌������ǁA�A���^�̗\�z�Ƃ͈Ⴄ���傾��B
���̐풹�ɂ́A�u�U�z�E�v�������o���Ȃ��Ə����Ă��邯�ǁA
�u�C�e���݊��v�������o���Ȃ��Ƃ͏����Ă��Ȃ��̂ŁA
>>451 ���ւ̃A���`�e�[�[�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ǝv�����ǁB
>>454 �����ł���킯�Ȃ������B
���C�x�����u��S�C�ɂ���
�S�C��Ďˎ���9��Ȃ�1�唭�C�ȍ~��8������X�ɒx�������邭�炢���Ȃ��ᖳ��
����Ƃ��אڂ���C���̖C�e�͊����Ȃ��Əؖ����Ă����́H
>>456 ���ꂪ�A���^�̍l���Ă闝���Ȃ�A�풹�̃����N�͕K�v�Ȃ������B
����͒ނ�̃G�T�Ȃ̂��ȁB
>>450 �C�g��U��Ȃ��猂������ǂ��Ȃ邩�Ƃ����A�n��ɌŒ肵���C�Ƃ̈Ⴂ�������ł��Ȃ��H
�C�g��U��Ȃ��炪������Ȃ��Ȃ�
>>459 ����Ӗ�����͐��������H
��C�͂�����Ō������e�ɑ��肪������ɗ��Ă����̂����҂������
������e���ˌ��A�Ȃ�Ă��̂����߂���킯�ł�
���������ړ����Ă�D���ԁA�q��@�A
>>456 �אږC���̒e�ۊ��͊W�Ȃ�
���{�C�R�ł͖C�����͂̕s������A�S��Ď˂��ł��Ȃ��������A��������P���Ă���C�e�������ɂȂ�A98�����C�x�����u���J�����ꂽ
���ݔ��˂̎���A�܂�אږC���ł͓������C���Ă����́A�^�C�~���O�����炷�K�v���Ȃ������Ƃ�������
>>462 ���ꂶ�����������Ȃ��B
�������̑S��Ď˃f�[�^�[�����Ă��Ĕ�r���Ȃ���B
�אږC���̉e���Ȃ��Ƃ����Ȃ�P���C�g�ċ쒀�͎͂U�z�E100���ȉ��Ƃ�60���Ȃ́H
>>463 �����œ\���������N�Ɉɐ��^�����ݑł����ŏo��������ׂ��L�^�������Ă���̂����E�E�E
http://www.warbirds.jp/ansq/21/B2001881.html >>463 ����ŏ\��
�אږC���̒e�ۂ�������Ƃ����������咣����Ȃ�A����𗠕t����\�[�X�������ŏo����
>>466 �킴�킴�풹����T���Ă���Ȃ�Đe�Ȑl�ł��ˁA���Ȃ��́B
���̃����N����
>>463 �{�l��
>>453 �Œ����Ă��ł���B
�����
>>463 �݂����ȃ��X������z���Ăǂ��v��?
��C���̈��͉͂����œ`�d����̂ŁA�������C�e�Ȃ�C�e�̐�[�̈��͂��ׂ̖C�e�̐K�ɓ͂��Ȃ���i�͂��O�ɒʉ߂��Ă��j���v����B
�܂���Ē��̖C�e������������Ռ��g��
>>469 �_�w�_�����Ă��ł͂Ȃ�
�����ł�����x�ɉe������������A�H�ƓI�ɉe���͂Ȃ��ƌ�����
�e���ւ̉e���v�f�͑��ɂ��F�X���邵
�C�����Ƃɔ��C������t����b�������l�͂��Ȃ�
�������Ƃ̏ؖ����ł����
�C�g�Ԃ̋����ƖC���Ԃ̋�������S�R�Ⴄ
�Ⴄ�b�ɂȂ邯�ǁA
��C�ǂ܂��ǁ[��
�����肠�`��
>>474 ���̎���̐�͂���ԃJ�b�R�ǂ���Ȃ�
�t�l�̓��E�E���x���g���u�V�`���A�v�����J�b�R�C�C
��ɔ�s�@�����Ȃ����Ă�����ˁE�E�E
����͍ʼn�����������Ɛ����A��ʂ������Y��ɏC����������
���͂���
�C�^���A�C�R���E�E���x���g���O�W����̓V�V���A�@1909/6/10
munizioni�̓C�^���A��Œe��������͌R���i
�āA�����݂�ȏ�����ā`��
>>473 �_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO 3:07�����肩��
���A���A�E�Ɍ�����
�͋��Ⴂ�̂Ƀ}�X�g���������牓�ڂ��Ɣ��D�ɂ��������
>>473 ���Lnavweaps�ɂ��ƁA�ďA����A�E�B�X�R���V���͒��������E�̏��Ԃɂ����Ƃ���
http://www.navweaps.com/Weapons/WNUS_16-50_mk7.php During the 1980s activations, agastats (time delay relays) were fitted to the right and left gun and these created a turret-whipping problem.
This was corrected by increasing the delay in the right gun to 1 second.
Wisconsin differed from her sisters in having a 1 second delay for the left gun and 2 seconds for the right gun.
>>483 ���肪�Ƃ��B
���̓A�C�I�����̒玁�̋L���ɔ��C��H�}������A
���C�̂�0.06�b�̒x���͒m���Ă����A
1�b���A�����܂ł��Ȃ��Ⴂ���Ȃ������̂ˁB
>>484 ���������ǁA�ڕW���ړ����鐅��C������Ȃ��Ȃ�������A�e���^�C�����O���C�ɂ��Ȃ��Ă��悭�Ȃ����̂���
�C���ւ̃X�g���X�Ƃ����Ӗ��ł́A���ށ������̃T�C�N�����I����Ă���A���C�̔��C�������������ǂ��̂��Ǝv��
�P�b���ƒe���^�C�����O���C�ɂ���قǂ̍��ł͖����̂ł́H
��ĂɌ�����ł���[���ǂ�ŃX�C�b�`�͂Ȃꂽ�ꏊ�ʼn����Ă���P�b���炢���ʂɂ���ˁH
>>487 ���܂A���������Ă��̃{�P�͗��݂Â炢�B
>�@�i���{���̗��㎩�q���j��155�~���֒e�C�̏ꍇ�A�˒�20�L�������ŁA100���������Ƃ�50�������e����Ɗ��҂���锼�a�iCEP)��300���[�g��
>>489 ����ȃ��X�v��Ȃ�����A���
>>472 ���Ɂu���߂�Ȃ����v�������ȁB
>>490 ���������Ă�̂��Ӗ��������ȁB
���͂����̊Ǘ��l�������Ȃ̂��H
�{�l���������Ă���̂ɉ��̂�����ɎӍ߂̕K�v������H
��̃A�C�I�����̗Ⴉ�����2�������ɔ��C�x�����u�ŖC�e�̑��݊��������Ȃ�Ăł��ĂȂ������ƌ�������H
���Ȃ݂ɂ킩���Ă�Ƃ͎v����
>>487 �͍��x�ȃ{�P��
>>471 > �������Ƃ̏ؖ����ł����
�ł����B��̖͂C�e�͉�����2�{����1.3�{���x�Ŕ��Ă��邾��B
�����̃{�[�g�ƃ{�[�g�̔g�݂����Ȃ��B
��������C�e����藣��Ă����Ȃ���B
�ׂ̒e�ۂ��N�������g���������ɐi�ނ���ˁB
>>491 ���܂�
>>456 �ł��̑��݊������������邽�߂ɂ�
�u9��Ȃ�1�唭�C�ȍ~��8������X�ɒx��������v���ď������뎩���ŁB
���̒x���^�C�����O�͓��R����̂���̂��̂���ˁB
����Ƃ����ЂƂ������ƁA
>>467 �ւ̉͂�H
�A�C�I�����̖C�g��310cm�Ȃ��ǁE�E
����X���[���ꂽ�A�܂�����͂���ŕ��a�ł�����
>>495 �܂莩���S��������Ċ�^���ԂŎӍߗv���Ȃ́H
�܂������ȉ��߂��ł���̂�����������݂��Ȃ���̖͂��͂Ō���i
�����ĖC�e�͍����ʼn�]���Ă�̂ŁA
�����ʼn�]���Ă�̂Ń{�[�g�Ȃ�ʖ\���ł���
>>498 ���̖��ʂȃ��X���Ă�ԂɁA
>>494 ,
>>496 �̖₢�|�������������B
>>497 ������A
>>488 �œ˂����݂��ꂽ����B
�ߐڂ����C���甭�˂��ꂽ�C�e�̑��݊���
>>502 ���A���ł����Ă�̂��Ƃ����{�܂�
>>503 ���Ƃ��Ύ����̗���Ń��{�b�g�A�j���̂悤��
�u�_�u���p�[���`�I�v�Ɩڂ̑O�̕z�c��
�����ɗ���Ńp���`���Ă݂Ă���
���_�������H�A���킩�邳
�A�C�I���̍��C�ƉE�C�̋�����6.2m
���V�����[�Ƃ�KGV�͂ǂ��������낤�Ȃ��B
�ނ���4�A�t���炢�̂ق����D������ɔ����Ă�����ɂ����
���C�x�����u�̗̍p�A���ēƕ��͊m�F����
���V�������[��1947�N�ȍ~�ɓ��ꂽ�̂��ȁB
���{�̋㔪���͂����ƒx���b���͒Z�������ł���ˁH
98����0.03�b���炾�����B
>>511 ���肪�Ƃ��B
���Ȃ݂ɉ������߂Č����̂͌̍����a�����̒���ŁA
�d���������S���̂Q�b�Ƃ������̂������B
����ȍ~�������Ⴄ�����������������ǁA��ԒZ���̂�
�������̃T�C�g�Ő番�̂R�b�i�������ɒZ�������낤�I�j�Ă̂��������B
>>511 ��a�̂͌����m���ɂ���a�����̏W�听�I����u�����͑�a�E�S�O�Ձv�ɂ��A
���a15�N��46�Z���`3�A���C���p�̂��x�����u�����A0.08�`0.2�b�̉ώ��B
��a�̎�C�x����2���̓������˂ɑς��鋭�x���������A�܂�3���������˂͂ł��Ȃ������Ƃ������{�쑾�Y�L�q�����ǁA
>>513 �A
>>514 �T���N�X�B
�C�e���C�g����ʉ߂��鎞�Ԃ́A���ɖC�g���œ������x�Ƃ��Čv�Z�����0.05�b���傢�B
��������ƁA0.08�b����Ă�A�ŏ��̒e���C�g���o�����ƂɎ��̒e�������o�����ƂɂȂ�܂��ˁB
>>514 ���C��ɖC�g�������Ō�ނ��Ă�Ԃ͎�C�x���ɃX�g���X���|�����Ă����
�R���}���b�̃Y���͑D�̍\���ɑ��Ă͓����Ƃ݂Ȃ��ׂ��ł��傤
>>503 �Ȃ�قǂȂ�قǁB
���S�ɓ��������s�ɑł��o���Ă��̂܂ܔ��Ă���Ζ�薳���͂��B
���A�͂��ȃ^�C�~���O���̈��͂̍��ŁA�ǂ��炩����m��s���鎖�������āA
����ƂR������ĂĂ���s�e�ۂ̉e������s�e�ۂɋy����ė����킯���B
���s���Ă̂��A�˂��ꓙ�ł����킸���Ƀu�����肷��Ɠ������ڋ߂����Ⴄ��������B
�ނ����s�̂悤�ɑ��ݍ�p���݂őł��o���̂́c�����������Ɩ������B
���e2�����ׂĊԂɔ̎d�������A����Ȃ���
>>517 �������A���ދ@�̓����������炷�����ł��B
>>516 �Ō��Ӗ��Ȍv�Z�����������Ȃ��܂��B
���X�����A�A���Ō��������Ă����͋C�ɂ���K�v����������
�y�i�������{�~�낵�z�@�L�b�V���W���[�͓c�����u�W���b�v�v�ƌĂю̂āA�����ƃ}�X�R�~�͓c���𑒂���
http://2chb.net/r/liveplus/1521427443/l50 �C�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��������̂ŕ��������̂ł���
>>523 ���n�������ˁH
����v�����C�M���X�l�ɕ����������B
�Ƃ����̂͏�k�Ƃ��āB
��O�C���������ƑO�ɂ������̂��������܂Ō��Ɏ����Ă�������ł���B
�ނ�����^��͂���݂�Ƒ�4�C�������߂��ŁA
�܂��W���h���������Ȃ���������A�����ʂ�@�B���̌��ɖC���u������������Ă��Ƃł́B
���ދ@�̐������܂��Ȃ̂�
>>523 �Ƃ肠����wiki�̃G����(���)���������悤���H
>>517 �^���G�l���M�[�̑��ʂ͕��Ղ���
�s�[�N���̕��ׂ����U����@�B�I�Ȍ̏������ł���Ǝv����
>>527 ������x�͂����v���܂������A�C�e���˂̔��͂��C���Ƃ��͑̍\���Ƀ_�C���N�g�ɓ`���킯����Ȃ��ł��傤�B
�C�e���˂̔��͖͂C�g��������鎞�Ԃɕ��U���Ċ͑̂ɓ`���킯�ŁA
������Ԃ͕S���̉��b�Ȃ�ĒZ�����Ԃ���Ȃ��̂ŁA�s�[�N�l�̕��ׂ���������ʂ�
��������Ȃ����Ǝv���܂��B
100���[�g��10�{���1000���[�g���̂ق����y���_
���������C�g�̌���^�����͒��ދ@�ʼn^���G�l���M�[���M�G�l���M�[�ɕϊ�����Ă���Œ��Ȃ̂�����A
���͂̕�Ȃ�C�����Ռ����z�����Ă����̂ł�
16�C���`50���a�̔��C�T�C�N��
���ނƕ�����3.5�b
�炷�ƒ���1�b�A����2.5�b�Ƃ����Ƃ��납
���C�̏Ռ���1�b�̎��Ԃɕ��U�����Ƌ��ɁA�ꕔ�̓O���Z�����������̊ɏՔ}�̖̂��C�M�Ȃǂɕϊ�����邩��A�͑̂ւ̏Ռ��ʂ�����
�A�C�I�����̍ďA�����A���C�x����1�b�ɂ����Ƃ������A���ގ��ԂƂ�����������
�x�������̗��R���A�C���̃E�B�b�s���O(�ڑł�)�����ɂ���Ə����Ă�����
�ڑł��Ƃ����̂́A���C�����̏Ռ������ꂽ�Ƃ���ő�������錻�ۂ��낤
�~���b�P�ʂ̔��C�x���ł́A�C���ɂ�����X�g���X���ߑ�Ƃ�������
�C�e�̊��h�~�̂��߂ɂ͔��C�Ԋu�̓~���b�ő����̂ɑ��A�͑̍\���ւ̃X�g���X�ɘa�̂��߂ɂ͊Ԋu���X�ɋāA�C�g�̒��ރ^�C�~���O���ꔭ���o���o���ɂ��������L���Ƃ������ƂȂ낤
http://www.navweaps.com/Weapons/WNUS_16-50_mk7.php he recoil distance given above is the nominal figure.
The absolute, metal-to-metal recoil distance was 48 inches (122 cm).
When the gun is fired with full charges at a +15 degree elevation,
recoil lasts 0.43 seconds and counter recoil (runout) lasts 0.90 seconds.
During runout, the gun is automatically lowered to the loading position, thus speeding up the firing cycle time.
>>533 �p�ꂪ�ǂ߂Ȃ��̂ŊG�Ŕ��f���܂����B
�܂œǂB
���Ȃ݂Ɍ����ɂ���46�����C9��̐Ď˂͔����a�͖�8000�g���Ƃ̎�
�C�̔����̃s�[�N���ĖC�e���C���𗣂ꂽ���_���Ǝv���܂����ǁA�i�C�e�̑��x���ő�ŁA����p���ő�ɂȂ�j���ꂪ�����Δ��������U����鎖�ɂȂ�܂��H
>>535 ���v�ł̓��R�C���ƃJ�E���^�[���R�C����3.5�b�Ƃ����ǂ݂悤������
>534�͒��ނƕ����̍��v��1.33�b������A���v�̊G�ƕ��͂̂ǂ��炩���Ԉ���Ă��邱�ƂɂȂ��
VIDEO ��������3.5�b�͂��肦�Ȃ��̂����ǁH
�����ǂ܂��G�Ŕ��f����T�^���ȁB
>>416 �V���K�|�[���v�ǂ̓n���C�v�ǂƕ��Ԑ��E��4��v�ǂ�1�ŁA�p���S�̂łV�債���Ȃ�
�ŋ���15�C���`�C��i�˒�33km�j��5����z�����Ă���B
�������͂Œ@���ƂȂ�ƁA���X�͋Z���������40cm�C�i�˒�38km�j�ŃA�E�g�����W���Ă��܂��Ηǂ��B
>>523 �@�B���i�^�[�r����@�j���Ԃɓ����Ă�
>>526 �G�����͋����悩��̐v����������̃^�C�v�V�b�v�Ȗ���
>>542 >�������͂Œ@���ƂȂ�ƁA���X�͋Z���������40cm�C�i�˒�38km�j�ŃA�E�g�����W���Ă��܂��Ηǂ��B
�͒����͂邩�ɏ������C��ɒ��������Ȃ��Ɗ�{�I�ɒn��C��͔j��ł��Ȃ��̂�
��͂ŃA�E�g�����W�ˌ��Ƃ��A�e��ɋ�ɂȂ�܂Ō����Ă�1�������邩���ă��x�����Ǝv����
>>539 http://www.eugeneleeslover.com/AMMUNITION/NAVORD-OP-769-APPENDIX-2-ORDNANCE-DATA.html �����炪Firing cycle timings�̐}���f�ڂ���Ă���OP769�ɂȂ�܂��B
�ʂ̃y�[�W�ɂ��̐}������܂����A�f�[�^�[��0.43��0.90�ł��ˁB
���C�T�C�N���̏���Ԃ͂����܂Ŗڈ��Ȃ̂ł��傤�B
>>438 ����ŌŒ肵�Č��ꍇ�ƁA�C���葕�u���K�v�Ȋ͖C�Ƃł͌�҂����x�̖ʂł��s��
�u���ƕd�v�̂Ƃ���ɋ��C�R�̐퓬����f�[�^���ڂ��Ă�
�@����a�C�i36cm�`40cm�C�j�̐퓬�����71m�i����3��m�j�B
������
�@����a�C�̒P�C����i�ˌ�������ŌŒ肳��Ĕ��˂����Ƃ��̒e���덷�j��56m�`60m�i����3��m�j
����ā@71m�^56m�`60m�@���@1.26�`1.18�{�@
�͖C�͗���ɌŒ肵�Č��ꍇ�ɔ�ז�1.2�{�قǒe���덷���傫���Ȃ�B����قǑ傫�ȍ��ł͖���
>>542 �S��C�e�g���ʂ���������1����ׂ��Ȃ��ł���肾��
���������Ȃ��ڕW�Ɍ������Č����Ă��P�Ȃ�e�̖��ʂȂ���
>>544 ���⑊��͋쒀�͂̂悤�ɉ������č����œ����������͂��Ȃ��A�S�������Ȃ��Œ肳�ꂽ����C��B
�Ƃ���Ζ����m�����ȒP�Ɍv�Z�ł���
���
>>433 ���o���Ă��ꂽ���������p����Ɓu����@���a�P�Q�N�x���K�@�ˋ���31100�A����179�A���E56m�v
�ڕW�C�������20m�l���Ƃ��ā@�i20m�~20m�j�@�^�@�i179m�~56m�j�@���@�������͖�4�p�[�Z���g
��C���25�����ĂΔj��ł���v�Z
>>538 ��d�̋ɂ݂ƌ������_�������Ă�
>>546 �������ˌ����悤�Ƃ����̂ɎːS�ړ�����͖͊C�ɕs�������疳�����Ă��ł����H
������4���H�H�H�H�H�H�H
>>548 >�ڕW�C�������20m�l���Ƃ��ā@�i20m�~20m�j�@�^�@�i179m�~56m�j�@���@�������͖�4�p�[�Z���g
�Ղ�ww
����Ȑ����������сA����ł�����ł��o����Ɩ{�C�Ŏv���Ă�́H
�������Q�O���l���H��a�̎�C���ł��������傢���������A�h�f�l���ȁH
>>545 ��������
���v�̐}�́Athree gun turrets�Ƃ���ʂ�A�O�A���C���Ƃ��Ă̔��C�T�C�N��
������A���C�x�����l�����āA3�C�g�̕��������܂ł�3.5�b�ƍl��������Ǝv��
>>542 ����a�C��Ȃ�Ĕ����ŊȒP�ɔj��ł��邾�낤�ɁB
��Ԃ̖��͑����ɖ����e�o���Ȃ��ƁA
>>554 ���m�Ȉʒu���s���ȏ�ɋٖ��ȑ�C�Ŗh�䂳��Ă��鑕�b�C����ŊȒP�ɔj��o���������
>>548 �U�z�E�ɑ���32�~250�ʂ̑傫���̓G��͂��
�u�D�̂̂ǂ����v�ɓ�����̂�5���ʂȂ̂ɉ��Q�ڂ����������Ă�����E�E�E�E�E
��ȁE�E����^�Ƃ��ł��\�I���Ă��C��������̖ʐς͑D�̂�2���ʂ����Ȃ���
�i�C�g�Ɣz�u���Ă�Ԋu���x����₷���j
>>555 �R���q�h�[���ł��N���~�A�ł��������ǃC�}�C�`������
���̎�̐w�n�ɐ����t����ꂽ�C����Ŕj��͍̂���
���S�ɔj��ł��Ȃ��Ɗ撣���ĕ�������Ă��܂��̂�
�����Ă���ς�ł��������������͂������Ȃ�
>>552 �����h�f�l�ł��邱�Ƃɉ����āu�����̐l�Ԃ͂����I�ȉ��l�Ƃ͔�ו��ɂȂ�Ȃ��n�������v
�Ǝv���Ă鎩���ꉮ����Ȃ�ł��傤�A���������l������
�}���[�����̂����ɏ㗤���ĂQ���������čU�������i����������Ƃɂ́A
�������ׂ����R�����锤�Ȃ�čl���Ȃ��^�C�v�Ȃ�ŁA����Ӗ��K���B
>>548 �@����̏��a12�N�x�̐퓬�ˌ��f�[�^�Ȃ�m�F�ł���̂ł����A
�b��@����30,210m�@���ߎU�z�E351.8m�@����4�e
����@����22,900m�@���ߎU�z�E254m�@����3.8�e
�@���ݎˌ��ŏ�L�ƂȂ��Ă��܂��B�������ʂɋ����ˌ��Ƃ������ˌ�������Ă��邩������܂��A
>>433 ���̃f�[�^�͒�~������ԂƂ����ςł͂Ȃ�����̈�Ď˂Ƃ��̂��̂ł͖����ł��傤��?�@�@����Ƃ��ēK�ƌ����邩�ǂ����B
���ݖC���ΎE���}���͂ǂ����痈�Ăǂ��֍s���̂�
1944�N9������̃h�[�o�[�C���C����͖ʔ����B
���{�ł���̕C�G����Δ��\���̌��z���͓V�c�̖h�i�Q�d�{���t����c���j��10�g�����e��ƌ����Ă��邯��
http://www.sengokushi.com/sengokushi/?p=1045& ;page=6
���ꂾ���̑ϔ��C���V�F���^�[���햖���ɏ㗤�\�z�n�_�ɂǂ���ꂽ�낤��
�C��{�͖̂����ł����d�{�݂���ēd����������A�d�b����Ďˌ��w�����Ɖ��M�s�ʂɂȂ�����
���d�ɂ����ĉ��X�ƒE�����Ă䂭�X���Ⴂ�̘b����~�߂ăL�b�`����̘͂b�ɖ߂���
>>565 KGV�@�u����������肶��Ȃ��Ǝv�����ǁH�v
�_�R�^�@�u��d���ł킩��܂���v
�m�[�X�J�@�u�Ȃc����ă_���݂����v
�M�Z�@�u����Ȃ��Ƃ����낤���ƑS���Ƃɒu���Ă����v
��͂�d������Ă��蓮�ʼn��Ƃ��ł��鑕�u�͕K�v����
>>416 >>569 ���ߔ�r�����̂����㎮�\�ܑW���_�C������B��͂̔��ˑ��x���炢�͊F�m���Ă�̂ŗ�����
>>568 �Δn�̖L�C��ɐݒu���ꂽ�̂́A���m��͐ԏ��41�Z���`�A���C��
���R�A���͂͐���
�����������1,200���[�g���ŁA�͍ڑ����V�Ȃǔ�r�ɂȂ�Ȃ�
�n�ʂ��h��Ȃ��Ȃ�C���ӂɃ��[���~���ăg���b�R�ŖC�e���^��ŃN���[���ő��U����悤�ɏo���邼�B
�܂����������_�Ƃ��ē����̌R��
��e���Ă��Z�����Ȃ����d�ʐ������Ȃ�����R���N���[�g��������ł������ł��邩�琅�������ɐݒu�����Ƌ߂Â��Ȃ��Ȃ�B
�h�C�c�̉��ݖC��̑���a�C�͊�{�d��
����C��̔��ˑ��x�����A�h�C�c��40cm�C��i�g����͂ɓ��ڗ\�肾������C�j�͎n�߂͎蓮���U�������B
�Δn�v�ǂ̖C�䂪�������Ă鐅��Ɍ��ǕČR�͐���͂����Ȃ�����
�ł��W�����o�[���͕��������
�܂��v�ǂ̖C���a�͂ꂿ�Ⴄ����ˁB
>>578 �┑���̃W�����o�[�����A�}�T�`���[�Z�b�c�Ɍ����ꂽ�b�H
�������̃W�����o�[���͗v�ǂƂ͈Ⴄ����
����C��Ɛ�̘͂b���ɑ���
>>578 �̓��˂Ɏ咣����
>�ł��W�����o�[���͕��������
����߂���
�ނ͉����������������̂��낤��
>>565 ��a�ƁA�v��͂����ǃ����^�i���ȁB���b���������������A�ʎ��ו����������B
���͈ӊO�ƃm�[�X�J�����C�i����r�I���ԂƂ������B��d�͂�4���ギ�炢���f�B�[�[�����d
�Řd���Ă�̂ŁA�{�C���[�S������Ă�400�������p�f�B�[�[�����d��⏕�Ɏg����A
����炾���ŖC��2���炢���������Ȃ����낤���B
�T�E�X�_�R�^�ȍ~�͏d�ʌy���ƏȃX�y�[�X�̂��߂��唭�d�@�̓^�[�{����{�ŁA���͌v400����
�̔��p�f�B�[�[�����d�@�����邾��
�W�����o�[���͉��ݖC��Ɏ���Ă����̂Ƀ}�T�`���[�Z�b�c�ɕ������������Ď��H
>>582 ��C�������Ă���Ȃɓd�͂����́H
��a�͑���͂�蔭�d�p���[�͒Ⴂ����C�������|���v������K�v�����Ⴂ���炾���������B
���̐����|���v�͉��œ��������킩���Ă�́H
�v����ɁA�C���쓮���͉͂��ŁA���̂��ߖ����Ȃ萅����������|���v���͉͂��ŁA�|���v���͂̔������͉����Ƃ����A���ł���H
����o���ŏ�������A���Ȃ����Ă����悤��
��a�^��C�̐����|���v���ēd���̐����|���v����Ȃ������́H
>>588 �X�N�����[���쓮����^�[�r�������ĕK�������^�[�r���Ɨאڂ��Ēu����ĂȂ��킯�����A
�u��C���t�߂܂ŏ��C�Lj�����v�����ƂɁA���ɖ�肪����Ƃ͎v���Ȃ����B
>>589 ����B�x���ň��݂Ȃ��珑���Ă����Ƃ�������ɂ������Ȃ����E�E�E
�~�X�N�����[���쓮����^�[�r�������ĕK�������^�[�r���Ɨאڂ��Ēu����ĂȂ�
���X�N�����[���쓮����^�[�r�������ĕK�������{�C���[�Ɨאڂ��Ēu����ĂȂ�
>>577 �Œ�v�ǂ͌Œ�Ȃ̂����݂ƁA�Œ�̂Ɏ��g�̈ʒu��틵�ɉ����ĕς����Ȃ��̂����
WW2�̐�̗l���ł͋ǒn�I�ȑ��݉��l�͂����Ă��A��ǑS�ʂɗ^����e���ɂ��Ă�
�K�������Ⴉ�������Ă�����
�A���R���m���}���f�B����㗤�����A�l���`�p�}���x���[�܂Œz�������̂ɁA
>>592 ���̏�Ńm���}���f�B�ɋ@�b�������R�@�̎�͌��W�����ď㗤�R���C�ɒ@���Ԃ������Ď��Ȃ�v�ǖC�ǂ���������Ęb�����ǁA�j���̗��ꂶ��P�ɉI�ꂽ��؋�̖V����˂��Ă�����
>>593 ����Ɨv�ǂ̉��l�͊W�Ȃ��b�A�v�ǂ͂������U������Ȃ��ׂɂ���B
�I�����������
������ʏ�̐w�n���n�ƈႢ���݂�铽�����A�ނ����`���đ��݂��֎������B
���������������Ă�̂ɂ܂������ł��Ȃ��̂�
����������ΘA���R�͍Ō�܂Ńh�C�c�̓S�z�������̃m���E�F�[�N�U�����Ă��Ȃ��B
�t�x�݂̏��w���Ȃ�����u����Ⴂ���̂ɁB
>>588 �����@���͊ʎ����̑O��ɗאڂō��E�����ɔz�u��������C�ǂ͂���Ȃɒ����Ȃ�
���C�ǂ������ƕۉ�����ς����琅���ǂ�����ق����ǂ�
>>593 �v�ǂ≈�ݐw�n���\�z���邱�ƂƁA
�����p�̋@�b������q����p�ӂł��邱�ƁA����甽�����������ēG���㗤�������쒀�o���邱�Ƃ͂ǂ��݂����đS���ʂ̘b����
���ݐw�n�\�z���鎖�͓G�ɂ���ɑł����㗤��͂�ɋ��v�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���̂�i�����G�������Ȑ�͂Őw�n���ʓ˔j���悤�Ƃ���Ȃ畁�ʂɌ��ނ��_���邯�ǁj
���͂Ȑw�n���U���\�Ȑ�͂������Ɏ��Ԃ�v���邵�i�h�q���ɂƂ��Ă��h�q��͗p�ӂ̎��Ԃ��҂���j�A
�U������ƓG�����f����Ȃ�㗤���̂��̂���߂���A�㗤�n�_�̕ύX��]�V�Ȃ������Ƃ�������
�{�C���[����C������܂ł̌o�H�Ȃ�ƂȂ��܂Ƃ߂Ă݂����S�R���M�͖����� orz
���{�̋���͉͂����㕜���͑�a���l���ł�������͂����
�����Ƒ��U�͌ォ�珑�������������œ��̓��[�^�[�͌�
�O���ׂ͍̂������킩��Ȃ��̂ŖC������̂�
�����E�����Ə��������Ǔ��{�̂������܂���Ƃ̍����t�A���{�d���͖����A�p�ꂾ�Ɛ����������� hydraulic ����
���{�ƊO���Ń|���v�ƃ��[�^�[�̈ʒu���t�����Ǔ��{�̂͐������[�^�[�Ő����|���v�����A�O���͓̂d�����[�^�[�Ŗ����|���v�����ƌ������ɓǂ߂�̂�
�Ƃɂ����ԈႢ���w�E���ė~����
�v��+��͂̑g�ݍ��킹���ƓG���Ă������
>>599 �Ȃ�قǕ�����₷����
�A�C�I�����͎������L�x�Ȃ̂ŁA�Ȃ�Ƃ��ǂ݉����Ă����Ό����͂�
�Ⴆ�A���L�����N��1-13�ɂ͊e��C�����͂̔z�u���킩��
http://www.eugeneleeslover.com/AMMUNITION/NAVORD-OP-769-CHAPTER-1-GENERAL-DESCRIPTION-TURRET.html ����A��A�g�e�ȂNJe��@�\���Ƃɖ�����H�Ɠd�����[�^�[������A���ꂪ�������[�^�[������V�����_�[���쓮���Ă�Ǝv����
������G�N�Z���}�̖����̂Ƃ���ɂ́A�d�����[�^�[�̎��ɖ����|���v�����āA���̌�ɖ������[�^�[�Ő����g�e��A�����V�����_�[�Ř������̂���
���������ƁA�C�����ɂ������p�C�v���������ޕK�v�����邯�ǁA�d�������̏ꍇ�͓d���������������߂Ηǂ��̂ŁA�@�\���ȕւ���Ȃ����Ƃ����C������
�����A�ǂ����ݗv�ǍD��������˂�
��͂����v�ǂ��ă��}�����
�D�������Ƃ���������Ȃ��m���Ƃ��Ď��R�ɒm���Ă��܂��B
�������Ζ��G�̗v�ǃA�o�I�A�N�[�ɓˌ����Ă������z���C�g�x�[�X�ɂ݂͂�ȋ���M���������
��������ƁA�ǂ��𗧂��������������C�t�����Ȃ��ǂ�
>>606 ���܂��₨����͖��ɗ����Ă�˂��́H
�����݂�Ȕ����Ă���邩����ʂ͓�������
>>606 �Ƃ肠�������̃X���ǂݒ����Ă���B
�V���K�|�[���A�}�j���A�J���[�A�m���E�F�[�ɒ��ڏ㗤���Ȃ������z��݂͂�Ȕn���ƌ��������B
�������Ă��鐅��ɓG����͂̐N���������Ȃ������Ȃ炻�̖ړI�͉ʂ����Ă邩���
�t�ɃA��������������r�ߕ����ē��{�C�ɂ���������������
���̐w�n�͐퓬�������������G�����j�Ƃ�����ʂ������ĂȂ������̐w�n�͂ł��̖V�B�ǂ��𗧂�������
���A�Δn�A���R�̊e40�����A���C���ŊC���𐧈�����\�z������Ȃ��B
>>601 ���w�E���肪�Ƃ��������܂�
���������Ă݂܂������ǂ����ȁH
���ʂɍl���ēd���̕��������C�C�ł��傤����
�A�����J������a�̐����|���v���ăr�b�N���������Ęb�����X����Ȑ̂̕��@�ł����܂ŋ��͂ȕ����̂́c�c�ƕ��ꔼ���Șb�ł������
���������̓��{�͓d�C�W�ォ�������炱�ꂵ�����悤���Ȃ������ł���
798���͓͂������ł������ł��傤���X�ɐV��͊J������ꍇ�d���Ɉڍs���Ȃ����ɂ�
>>611 ���ʌ��ւɋ��ʂ̃K�[�h�}���z�u���ăZ��������܂���
��������D�_�ɓ������Ɏ����Ă�����܂���
�K�[�h�}�������R�����D�_�t�������ɗ����܂���
�v�ǃA�Q�̐l�͂���Ȋ����ł��艟�����Ă��銴���Ɍ�����̂��
��a�̖C������p�����@��500�n�͐��͐���@��1�C��2�@
>>614 �j����͉��̖��ɂ������܂���ł����B�J���������݂͂�Ȕn���ł��A�܂œǂB
���������Ηv�ǂɂ̓n���C���Y��������������Ă���Ƃ����ő�̐�ʂ��������Ȃ�
���m�͎�C���a�̕��C���d������������A���{���������ł��Ȃ������Ƃ�����ł͖�����
>>573 >>577 >�@���{���R���Δn�v�ǂ����ā`�Ɣ��肵�Ă���
������{���R�͂���Ȕ��肵�ĂȂ���B���l�^�́u���j�Q���v�Ƃ����G���Ȃ���
����Ƃ������C�^�[�l�̃V�~�����[�V�����b�B
���e�͖C�p�Ɋւ���m���̂Ȃ��l�̏������L���ŗv����Ɏq�����܂����x���B
�������Δn��ČR�͍U�����Ȃ���������ǁA�ʂɑ�R���H�ꂪ�L��킯�ł�������
��s����������A����̂悤�ɑΓ��N�U���[�g�ł��Ȃ��������疳������Ă��B
�m�[�X�J�����C�i���@1250�����^�[�{���d�@4��A850�����f�B�[�[�����d�@4��
�Δn�̖C��ł́A�R�̏ォ��ዾ�Ő���̓G�͂��ϑ����āA��p���狗��������o��
>>618 http://www.navweaps.com/Weapons/WNUS_16-45_mk6.php http://www.navweaps.com/Weapons/WNUS_16-50_mk7.php ������ƒ���
>>573 >�@���{���R���Δn�v�ǂ����ā`�Ɣ��肵�Ă���
���̘b���̌��l�^�́u���j�Q���v1999�N11�����Ƃ����G������
>>618 �����Ȃ�g���̂͊C��������A�R��Ă��Ђ̐S�z���������r�������l���Ă����
���ہA���Ȃ�ʁX�R���Ԃ�����������
���m�͂��͂̕��C�ł͖������g���Ă��邩��A���R�Ƃ��Ă͏����ア����
>>621 ����͒P�ɓ��{���v�ǂ�������ƃ����e���Ă��Ȃ������ƌ����Ă�ɉ߂��Ȃ�
���{���R���g�A���`��V���K�|�[�����C�H�U�����Ȃ��������Ƃ��n�߁AWW2�ŗv�ǂ𐳖ʂ��琅��͂��U�߂�����͖w�ǂȂ��A�����Ă��m���E�F�[�̃u�����b�q���[�̂悤�Ȗڂɂ��������Ƃ�����A�v�ǂ̗D�ʂ͏펯���������������Ă���
>>620 ����ł̓����^�i�ƃA���X�J��
�����^�i
�@1250x10�@�^�[�{���d�@
�@500x2�@�ً}�p�f�B�[�[�����d�@
�A���X�J
�@1000x4�@�^�[�{���d�@
�@1062x4�@�f�B�[�[�����d�@
�C�����v�d�͂���l����ƕĐV��͂̃f�B�[�[�����d�@�̓m�[�X�J�����C�i��2�C���A�A���X�J���S�C����������̂ɑ��đ���͍͂ł��o�͂��傫�������^�i��1�C������Ɠ������邾���Ȃ�
(�^�e)��(�g�e+�g��)��(����)��(���+���U)��4�H���ɕ����Ȃ��ƃA�C�I�����f�B�[�[�������ł�1�C�����������Ȃ�
>>618 >>624 ���{���d���ɖ����g�p�����̂ɐ�͂͐����������̂͂����̃A���ł���
��͂̏ꍇ�����ɂ���ƕK�v�Ȗ��ʂ��d���Ƃ͌��Ⴂ�ɑ�������
�r���{�[������@������������@orz
�A�C�I�����̏ꍇ�@�֔z�u�����x�ɑS�d���r���̉\���͒Ⴂ
�͂��A�A�C�I���̃^�[�{���d�͂͂����ԗ]�T������1��敪�c���Ă邾���ł�2�C���]�T�A��肭�肷���3�C���������Ȃ����������ł���
>>625 >�m���E�F�[�̃u�����b�q���[�`�펯������
����Ȃ��Ƃ��L�������ǁA�t�B�����h�Ƃ����n�`�͖k���Ɠ�������
�����m�ł͊W�Ȃ��ł��傤�B
�ɂ߂ē���Ȏ������ʉ��E�펯������̂͊ԈႢ�ł���
>�@��̖͌^�ł̓I�X�J�V�{���O�v�ǂ���̖C�����d���m�̓u�����b�q���[�ɖ����������l�q���Č����Ă���B
>
>�C���̕���1�L�����[�g���Ȃ��āA�����狌���C�ł�28cm�C�e�𐔕S���[�g���̎��ߋ����ŐH�������^�_���Ⴗ�܂Ȃ��ł��傤�B
http://sazanami.net/20170326-tv-anime-youjo-senki-norway-oscarsborg-fortress/#i-4 >>630 �ق��F�_���n���C���̂���ɂ͘A���͑���2�K�v�ƌ������͉̂R�Ȃ̂��H
���̔F�����ԈႢ�Ƃ������̂�2�����̃n���C���Y���炢�Ŗ�������Ă��邪�H
�t�B�����h�̉�������Ȃ̂�
�P����WW2�ł͉��ݗv�ǂ͎���x��ȎY���ƂȂ�ŔF�߂��Ȃ��낤
�Ȃ�ł����Ƒ傫�ȖڂŌ����Ȃ��낤
>>616 ���ۂɔn�����Ǝv����
�g������Ō�A����ł��݂��łт�l�ȑ㕨�Ɋ�����₵����
>>633 ���łŋ��͂ȖC����������ݗv�ǂ�������āA�Ȃ�ׂ����Ȃ������̂������̗��j
���̎��������ĐQ�������������Ă������͂͂Ȃ�
���܂��n���C���Y�Ȃ�H
>>636 ����œn�m�\�͂�WW1�̍�������I�ɔ��W����WW2�ł͉��ݗv�ǂ͖��p�̒����ƂȂ�܂����Ƃ�
�߂ł����߂ł���
�v�Ǒ��Y�ɂƂ����Ⴛ��u�[������������
�鍑�C�R���O�W������~�낵��12�C���`�C��
���@���K�[�h�����������e���ϑ����[�_�[type930�́A���Ƃ��Ɨv�ǂ���̎ˌ��p�Ƃ��ĊJ�����ꂽ����
>>638 15cm���̉��ݖC�ݒu����̂ɂ��l�ꔪ�ꂵ�Ă��@�B�͕n��ȓ��{�R��30cm���̖C���O�n�̖h��w�n�ɐ�����Ȃ�Ė����Q�[�ɂ܂邵
>>636 �ނ�̏������݂͖������O�����̊��z�ɉ߂����A�����̗��t�����Ȃ�����[�ǂ����邾�����ʂł��傤
�����A��D���Ȑ�͂����C�ɗ��Ƃ������Ƃ�S��I�Ɏ��ꂪ�����݂̂���
�����͏�ŏ������ʂ�
�J�풼��̍��`�U���펞�ɁA
>>639 �n���C�̗l�ɍU�����ɐi�U���[�g�I�ԗ]�n�̖����ꏊ���Ɨv�ǂ͐��Ȍ��ʔ������邾�낤��
����������ɂ����Ă͂��������i�U���Ƀ��[�g�I���̗]�n�̖R�������͖w�ǖ����v�ǂ̉��l�͌���I�Ȃ��̂�����
����ȏ�ł��ȉ��ł������Đ����N����͂��v�ǂ�苭���Ƃ��A��͂��v�ǂɗ��Ȃ�ĔF�߂Ȃ��Ȃ�Č����Ă���l�͂��Ȃ���
�J���[�ɓS�ǂ̉��ݗv�njQ���\�z����Ă������狗���I���X�N��`���ăm���}���f�B�[���㗤�n�_�ɑI�A���R�B
�}�W�m�v�ǖ��G�}�������Ă�ˁA����
>>645 �}�W�m���𐳖ʂ���˔j���ăt�����X���������������j������̂��B
�m�������B
�n������ʂɒނ�Ĕ�Q�S���X���̖ʖږ��@����
�}���[�����̖��т͑啔���͓˔j�s�\�A
���ݐw�n���p�_�҂͉��݃m�[�K�[�h��@�ł��������Ă���̂��H
>>614 ���ւɌ����|�����x�����������u���Ă܂����B
���ւ�������ċ��ɓ��܂�܂����B
���ꂪ�����Ƃł������̂��낤���A�����ʁB
>>648 �}�~�͂̎g�������ԈႦ�Ă�Ǝv����
>>650 �ɘ_���������Ȃ����瓪�̈������ۗ���
���̏ꍇ�Z�R���͗ǂ��Ƃ��ċ��ʂ̃K�[�h�}���ق����ł������̌�������h�~���ʍ������̂ɂ��Ď{��������������̂�����
>>644 �ƌR�̗v�ǂ��ė��R�����łȂ��A���ݖC��͊C�R�A
���˖C�w�n�͋�R���Ė��Ȗ������S���Ă�ƂȁB
>>652 �x�������p�_�������A�Ƃ����咣��
�ɘ_���������Ȃ����瓪�̈������ۗ��Ȃ��ău�[�������|����
�܂��A���ʌ��ւƂ��K�[�h�}���Ƃ��Z�R���Ƃ����œˑR����Șb�����o�����̂��͒m��A
����₷���Ⴆ������̗���đS�R�킩��Ղ��Ȃ����I�O����ăp�^�[�����唼���Ă����ˁE�E�E
>>651 https://dictionary.goo.ne.jp/jn/227125/meaning/m0u/ http://wakariyasuku.org/shuudann10.html �����v�ǂȂǂ̐w�n�ɒu��������A
���̐w�n�A�v�ǂ��U������̂ɕK�v�Ȑ�́A��Q�̑z�肩��A
���ڂ̍U�����T����قNj��łł���Η}�~�͂��������Ƃ�����B
��͂��C���͂̎�͂̎���ł͐�͂̐������͂̃o�����[�^�[�Ȃǂnj���ꂽ�B
��ꎟ���O�̃h�C�c�̓C�M���X�ɕ��Ԃقǐ�͂�������B
�������炢�̐�͂ŋύt������ΐ푈��}�~�ł���ƍl�����B
�����͂����͂Ȃ�Ȃ��������ǁB
�}�~�͂Ƃ͑���Ɏv���~�܂点��͂ł����āA
���̕��@���������܂��Ă���킯�ł͂Ȃ��B
>>613 ������a�̎�C���͂�d���ɂ���ꍇ�A���Ɖ������K�v�ŁA���̔��d�@�̂��߂ɂǂ̂��炢��
�d�ʁA�X�y�[�X��v����̂�
���̌��ʂƎj���̐����n�d�ʁA���v�X�[�X�Ƃ��r���Ă݂Ă��ʔ���������
>>632 �@
>>630 >�@�t�B�����h�̉�������Ȃ̂�
���ɓ���
>�@�m���E�F�[�̃t�B�����h�n��͂��̓���Ȓn�`
http://futaritabi.net/archives/6787861.html >�@��͂��v�ǂƐ킢�ɍs�����Ƃ����A�P�[�X
>�@��͂̊y���Ȃ�WW2�Ŏ��Ⴊ�����đR��ׂ�
�����m�ŌJ��Ԃ���Ă����j�������A���{���C�R�̗���C��͂����Ă�����I�ɔj��Ă���
>>625 > ���{���R���g�A���`��V���K�|�[�����C�H�U�����Ȃ�����
���R�ɐ�͂��������͖������A�����̊C�R�̓A�����J�͑��ւ̔����Ŏ��t
���ꂪ������A�܂�G�͑��̋��Ђ������Ȃ�A��햖���̃A�����J�̂悤�ɐ�͂��͖C�ˌ��Ɏg���|����
>>657 ����C��Ɨv�ǂ͕ʕ�
���ƁA���V���g�����ő����m���ׂ̗v�lj��͋֎~
���̃X���ł͏펯���Ǝv���Ă������A�����ł��Ȃ��H
���̖����_�j����ɗ���낤
�ނ���v�Nj��������Đl�̕����Q�[���]���C������
WW2�ŗv�ǂ͑��݉��l�����������Đl�͂���P�̂̔\�͂������Ƒ傫�Ȏ��_�ŗv�ǂ̑��݉��l�����Ă�Ǝv��
�����I�ɂ�
>>634 �̈ӌ��ɓ��ӂ��A��͂Ƃǂ����������Ȃ�Ă��ꂱ���Q�[�����_�ŋc�_�͕s�т������Ƃ���
������܂��Ⴄ��
���q�l�͖ڂ̑O�̋����ア�����킩��Ȃ�����ˁB
�Ȋw�Z�p�̐i���̉��b�ŗA���\�͂ƕ�⋔\�͂�����I�Ɍ��サ��WW2�ł͍U�ߎ��
�u�ǂ�����U�ߍ��ނ��v�u�ǂ̐���I�Ԃ��v�̑I�������ߋ��̐푈���������ƍL����
���̌��ʁA���̎��R�x�������Ȃ��đ�R�̋@�������g�o����l�ɂȂ���WW2�ł�
�u����͓����Ȃ��v�u�G�Ɏ����̐��ʂɗ��Ė��Ȃ��Ƃ��̉Η͂��o�������v�ƌ���
�h���I�Ȍ��_��w�������v�ǂ͑��ΓI�ɂ��̉��l���������A�����͂����]�����Ă���
����͗v�ǂ��̂��̂����U���͂�h��͂̕]���Ƃ͈قȂ鎟���ł̉��l�ςŁA�����F��
�Ȃ��l�Ɨv�ǂ̑��݉��l��_�������Ă��i�v�ɘb�܂荇��Ȃ��Ǝ����͎v��
�P���ɉ��ݗv��VS��͂ŃK�`���R����������ǂ������������Ĕ�r�͊y�����y��������
�������ɘb������₷���̂��낤���ǁA�����WW2�ł̗v�ǂ̉��l�Ƃ���̂͂������
�Ⴄ�Ǝv��
���ꂩ��v�ǂƏd�C�͊�{�Z�b�g���A�d�C�������Ȃ��v�ǂ͂����̏d�w�h��w�n�ɉ߂��Ȃ�
����u���ݖC��VS��͂ǂ����������v���Ęb�̒��ł͏��O���Ă����Ǝv�����ǁA������̕���
�o���㗤�x���U���ł͖̊C�ˌ��̗L�p�_�ł͏d�C�������Ȃ����ݗv�ǂł��h�䑤�̐�����
�i���㗤�j�~�\�͂̉����j���Ċϓ_����͖����o���Ȃ����݂��Ǝv��
�����������l������Ȃ�
>>647 �̉��ݖC��X����������������̂�
>>659 > ����C��Ɨv�ǂ͕ʕ�
����C�䂠���Ă̗v�ǁB�������C�̑傫���ɋK��͂Ȃ��B
�C�����ł���h�q���鑤���v�ǂƎ咣����Ȃ炻��͗v��
> ���V���g�����ő����m���ׂ̗v�lj���
��͌����Ɠ������֎~�B�����ď�����͊͑������ɑS�͂𒍂����B
�v�ǂȂnj�B�Ȃɂ��d�v���͖����������킯
���̏���C�R��͐����̃L�����Ȃ����̂����������
���ݗv�ǍU���ɕK�{�Ȃ͍̂q���͂ł�����
���ݗv�ǂ�������Ȃ���
96�����U���O�H�ƒ����ŗʎY���܂����Ă�����Ȃ������킯��
�ǂ����ʎY���Ă������������Ȃ����A��@�ɘZ�l�����l���K�v�Ȓ��U���ґ�߂���
�y�j�㏉�z�@�@�@�e���p�V�[�ʼn����@�@�@���}�C�g�k�[�����@�@�@���ʃE�T�M�����\�@�@�@�y�t�e�n�z http://2chb.net/r/liveplus/1521681235/l50 >>669 �����̃X���Ⴂ�͗ǂ�����
�S�������̖����X���Ⴂ�b�͎~�߂��
�J�펞�ɑ�a�^��1000�ǂ͗~��������
�E�E�E�Ƃ��Ȃ番���邪
���������ƕ����邩��I����ĂȂ��
>>665 �T�C�p���◰�����̖C����A���{�͗v�ǂƂ͌����Ă��Ȃ�
�v�ǂ́A�C�����łȂ��A���G�A�Ə��A�h��A�e����~�܂Ŋ܂߂��V�X�e���Ȃ̂ɁA����𗝉��ł��Ȃ��������݂���������
�h����Ə����u���A��͂ɂ͍͊ڂ䂦�̃T�C�Y��d�ʂ̐���������̂ɑ��A�v�ǂɂ͖���
������ł��傫�������ϑ����u���A�W��100���[�g���n�_���낤�Ɛݒu�ł���
�p�ĂȂ烌�[�_�[�����R����
�܂��A��͖͂C���ȊO�̑D�̂����Ă��͂��X������g�e�ł������͉�����
�v�ǂ͖C��̉��ɒe�����Ă��_���[�W����
�v����ɁA��͂͗v�ǂƔ�r���āA�ϑ����u�͏������ĒႭ�ĒZ���ď��Ȃ�
�܂萸�x���Ⴂ
���Đ�͂̓I�̓f�J���A�X�Ɏア�̂ő����ϐ����Ⴂ
�v�ǂ͐��h�q�̕��킾����A�Ηv�ǂ̐퓬���N���邩�ǂ����́A�ЂƂ��ɍU�߂鑤�̑I��
WW2�őΗv�ǖC�킪�N���Ȃ������̂́A����͂��v�ǂƂ̐퓬�����������
����������͂̈Ӌ`�͑���̐�͂Ɨm��ʼn��荇���邱�ƂȂ���
>>674 > �T�C�p���◰�����̖C����A���{�͗v�ǂƂ͌����Ă��Ȃ�
�ꉞ
�u�����̗��������v�@�����ꗘ�A����L
> �R�����悵�ăT�C�p�����͓�U�s���̗v�ǂł���Ƃ����Â��Ă��������ɁA�e���͑傫�������B
>�����p�@�������͎����ꔪ���A�u�}���A�i�����ɂ����Ă͘Z���������炢�c�R�����̎U���ɂ��A�G�ɑ�Ō������������...
�T�C�p���͎��̗v�ǁB
���o�E�����q��v�ǂƌĂꂽ�肵�����A�v�ǂ̒�`�Ȃ���ɂ���Ă��ς��ł���
�q�g���[����������Ŏ��̊W�����v�njď̂��D���������悤��
�����ŗv�ǃX����������������Q�[���[��
���������Β�����v�ǃ}�N���X�̃}�N���X������Đ�͂Ȃ�ȁA�܁[1200���[�g���������͂�������v�ǂƌĂт����Ȃ�C�������킩��
�S��1200m�Ƃ��^�ʖڂɃh�[������C�ɏo�����
>>682 ���]��͂Ȃ�R�ł��邾�낤��
>>683 �O�h���̗͂l�ɁA�O�X�^�t�A�h�[���ƃp���C�����ڂŃ���
������10�{�T�C�Y�̃[���g���f�B�[�R���猩����l�ԂŌ���120���[�g���T�C�Y�̋쒀�͂Ƃ���q�͂Ƃ����������b�������Ƃ������W
>>681 �����b�����S�ɉߑa���ċ��邪�v�ǃX���͊��ɂ��邵�A�v�ǂ��ʂ�����������F���ł��Ȃ��z�͌�ĂтłȂ��B
�����q��@���j������a�����Ȃ����̒���������
�j����͂Ƃ������q��@�������Ɨ��s�Ƃ���ς����獢���
>>679 https://ja.wikipedia.org/wiki/ �v��#��O�A�풆�̓��{�̗v��
���{�ł͗v�ǂ������łȂ����͖��m�A���ꂩ������������Ȃ��͊W�Ȃ��B
�@�������ނ̂łˁB
>>688 ���Ɍ����Ă����邯�ǁA���������N�͈�̉��̃Q�[����z�肵�Ă���̂��ˁB
�n���̈�o���ŃQ�[���Q�[���ƘA�Ă�������킯�ł͖������B
�N�������咣�������̂��͒m��A�v����ɘ_���I�ɘb���ł��Ȃ�����l�i�U���ɑ���̂��낤�B
>>689 �M�ߐ��͂Ƃ������AH45���܂Ƃ��ɓ�������T�C�Y����Ȃ����̂ȁB
�C���t�����̂͋������Đ�������Ȃ�Ƃ��Ȃ�Ƃ͌����A�^���J�[�����剻�͎~�܂�����50���g�������ł͖������B
���̍��ɂȂ�ƈ����ȑO�Ɍ�����������ɂȂ邪�B
......��������̓X�������Ă̂��������F�����Ă���Ȃ����ȁH
>>692 ���߁[�̂���Ă�Q�[���Ȃ�Ȱ�
�������Ƃ��̉ߑa�X����グ�Ă��
>>694 ����͂������̑䎌����B���݂��ꏊ�Ƒ���͕ق��닶�����B
>>695 ��ɂ킴�킴�A���J�[����ė��Ƃ��ĂȂɑ��l������Q�҃d�����ĂN�\
�������炳�����ƃX���`�͏�����
>>696 ����ɂ��������N�\�Ɠ���Ȃ��Ƃ���ׂ�Ȃ��Ƃ̓A�����J�l����B
���肵���o���Ȃ��Ƃ��m�����������Ȃ����B
�@�F�X�����Ă��܂����A�u���{�z��j�v��u����𒆐S�Ƃ������{�̌��w�H�Ǝj�v�u���{�̗v�ǁv
�@�C���v�ǂ͎��g����邾���łȂ��C���˔j��j�~���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂��A��L�̍���C��ł��ˊE��180���B
>>689 �v���U��ɐ�̓X���炵���U�肪�E�E�E�B
��C���a�Ɋւ��Č����ƁA46�Z���`�C������ł����Ɍ��x���Ă�悤�ȋ@�����܂��ˁB
����ȏ�˒������Ă��A���̋����Ŗ��������҂ł���ˌ��Z�p�������邩�Ƃ�����肪���邵�A
�P��������̈З͔͂��˒e���̑����ł�����x�͕₢�������E�E�E�B
�Ȃ̂ŁA������ڂ����͂̑傫�����A��a����^�i�{���ŗ���������Ȃ����Ǝv����ł����B
����܂�傫������Ɖ^�p�ʂł̕s�������邵�B
������{��L���ȗv�ǐ^�c�ۂ�����̎�͂�H���~�߂ĉI�����Ƃ����Ƃ���͐�����������ȁA���Ǒ��邪������܂ŗ����鎖�͖�������
�����܂ʼn�����d�˂ėǂ��Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ăق����M���͐����֘A���낤��
���R����̖{�����Ƃœǂ߂���X�Ƃ��閈��
�����������Ő�͒��߂����ˁH�ƂȂ����Ƃ��ɐ�͂͂��킽
>>700 �����z�肷��̂��ʔ����V�тł͂���B
����̂g���͑傫�����̂͌����I����Ȃ����A
���b���͌����f���Ă��Ėʔ����Ƃ���B
�ʎY�\�Ȍ����Ƃ����������������̂��낤���ǁB
>>689 > ��͉͂����܂ŋ��剻�����낤��
�����ȋ�z�ݒ肷������A�f���Ƀ��V���g���R�k�Ȃ��ōl�����炢���Ǝv���B
���Ԃ�46cm�C��51cm�C��͂��S���S�����鐢�E�ɂȂ��Ă��͂��B
��������͂̎�C�𗤏�C��ɓ]�p���邱�Ƃ͏��Ȃ��Ȃ�̂ŗv�ǂ͕n��
���b�͂̎���ł��ł�18in�N���X�͎������Ă�킯����
�t���[���A�X�@�u�Ђ�[�I���A�X���C�݂����v
>>706 20�C���`�͊m���ɍs������
����ȏ�͂ǂ�Ȋ��������
�h�[����80cm�͗��ɖ������Ǝv������
���ˑ��x��2�`3���J�����Ⴄ�̂͂�����ƒv���I
>>698 ���̐���}������Ǝ��j�A�������[���ɌŒ肷�邱�Ƃŋ@�\���ȗ����������ʔՂɌ������Ȃ��B
��r�I�����̕��ʔՂł��\���Ȑ��\������ꂻ��
>>706 �C�e�̈З͂��傫���Ȃ肷���đΉ��h��͎̂Ă邩������Ȃ��ȁB
��C�e�ɑς���鑕�b������͖̂C���ƒe��ɂ����Ō�͏��m�͎�C�ɑς������x�Ƃ��B
����̕ĉp���������Ă���͉͂Η͂͐����u���ő��b�����������������������
���ʂɑ��b�d�˂�����ɍs����Ȃ��H
�n���n���������剻�����Ɏ��~�߂�����ׂɏ�����C�������
>>700 ����ƁA�����̉e���Ƃ��������o�Ă��邩�ƁB
��͂ɂƂ��Ă��܂��A���[�_�[���̓d�q�A�����@��̏d�v���������Ă���A���������˂Ȃ�
�قǂ̔����͔��������Ȃ�͂��B
80�N��̃A�C�I���������̎��A���ˋ@��ǐ����u�������ɑς����Ȃ��Ƃ������R�ŁA
�V�[�X�p���[��~�T�C�����ˋ@�Ƃ��̎ˌ��ǐ����u�̑�����������ꂽ�킯������ˁB
�t�@�����N�X�́A�����̉e�����ア�ꏊ�ɐݒu�\�Ȃ̂ƁA�ǐ����u�����h�[���ŕ����Ă���
���瑕���\�������̂��Ǝv���B
�Ȃ̂ő���a����20�C���`�C6��ǂ܂�ŁA���Ƃ͔��ˑ��x�𑬂�����Ƃ��A�������������ɍs���Ǝv���B
�O�����h�X�������e�̐�[��TV�U����L���U���݂����ȏ����I�ȗU���M�~�b�N��g�ݍ��ގ���WW2�����̃��x���ł��\
���̑O�ɐ������Ă̘b����B
>>716 �����ʒu�ɋ�J�����炵����CIWS�B�ŁA�V�[�X�p���[�̓C���~�l�[�^�[�������ɑς����Ȃ������
80�N��㔼��RAM�������đ�ֈĂ��o�Ă������A���p���O�ɑ匳���\������
���オ�o���o������z��Ȃ���
��1������ɉp����N3�p��18�C���`45���a�C�A�A�����J��18�C���`48���a���J��
>>713 �ȒP�ȗ����ŁA����܂ŋ��ЂƎv���Ă��Ȃ������q��U���ɑΉ�������
���̕��c��Ƃ��������̂���
�������ꂽ���b�Ƃ����̂��A�悭������قƂ�ǂ͐����h��Ɛ����h��
�ߑ��͂̑c�ł��郍�C�����\�u������20�N�O�Ƀz���C�g�w�b�h�����͓o�ꂵ�Ă���
�����܂����I�푈�ӂ�܂ł̋����͖C��ő咆�j�������͂Ƀg�h�������ׂ̎���������݂����Ȃ���ŁA���C�ɑ������Ă���͂Ɍ������ނ̂͌����I����Ȃ����������
>>725 1880�N��̃t�����X�̓C�M���X��͐H�����߂ɐ�����150�ǂƂ��z�����Ă���ǂȁB
���ꂪ�������쒀�͂��Ƃ��m��Ȃ��炵���B
>>726 �����̐������͉��ݖh��p�ł����Ȃ��A�����̑��͂�˒�����l���Ă�
�u���C�ɑ������Ă���͂Ɂv������ł����ނ��Ƃ͌����I�ł͂Ȃ��Ǝv���B
�㗤�x���Ƃ��ɋ��o���ꂽ��͉͂ʂ����āu���C�ɑ������Ă���v�̂ł��傤���H
�y�t�e�n�z�@���̎������N�����̂́A���C�g�Z�킪����s�ɐ��������P�X�O�R�N���A�Q�P�N�O�̂��Ƃł�
http://2chb.net/r/liveplus/1521806322/l50 >>727 ���̐�͂͂��łɑ咆�j�ł����Ă����̂��H
���̂���̐�͍͂ō����x14�m�b�g�������Ƃ���B
��������20�m�b�g�߂��A������24�m�b�g1890�N�ɂ�30�m�b�g�o��悤�ɂȂ��Ă�B
���̍��̖C��ł̌�틗���A�C�̔��ˑ��x�l���ď\���ڋߐ�͐������邪�H
�t�����X�̐������D���͎��܂炸�A
�܂���{�ߊC�����n���C�Ƃ����₩���������d���͂������ƂȂ̂ł�
>>730 ��s�ڂ̈Ӗ����悭������܂��E�E�E
>>725 ����́u���C�ɑ������Ă���͂Ɂv�Ƃ����Ă܂��B
��͂����C�ɑ�����͎̂�ɂǂ������C��ł��傤�H
�����ē����̐������͉��ݖh��p�ł��B
���̂Q�҂̎傽�銈���C��̓��b�v���Ȃ��Ǝv���̂ŁA
�������̑�ʌ�����>725����̌��̔ے�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ǝv�������ł��B
>�㗤�x���Ƃ��ɋ��o���ꂽ��͂́E�E�E�Ƃ����������́A
�����I�ł���܂��̂ł��l�т��܂��B
�ł��A>�������쒀�͂��Ƃ��m��Ȃ��炵��
�Ȃ�Č����������\�Ђǂ�����܂��H
�܂����̌�쒀�͂�350�g��500�g���A750�g���Ƃ����Ƃ����܂ɑ�^������
>>734 �������Ă����͂��d���߂邽�߂ɑ��Q���}�킸��
�����Ɛ��ň��|����̂����̍��̎v�z
�������̊������ł͐�͂͒�~�ł�����́H
��P���~�͑D�̊�P�����C���Ȃ��͂̌����}���Ă܂Ő�������K�v�͂Ȃ��B
>>732 ���̎���̐���������PT�{�[�g�̂悤�ȍ������[�^�[�{�[�g�Ȃ́H
>>734 �p���C���ɑ�ʂ̐��������W���z�����ꂽ��ǂ��Ȃ邩�H
�h�[�o�[�C����34�����̕������Ȃ��A���S�ɕ�������Ă��܂��B
�����ŊJ���邽�߂ɐ����������ނ���͑D�̊J�����n�܂�B
���̍��p���̊W�͈���������B
�������������ނ���͑D
>>737 �ΒY�������V�v���@��
��ɏ������N���X��243�����̓^�[�r������
�Ȃ���قǁA40�m�b�g�ŃY�o�o�o�[���Ƃ�������ł��Ȃ��̂�
�����������̍��͐�������͂Ȃ�Ċ͎킪�������ȁB
���Ȃ炻�̃A�C�f�B�A�͎̂Ăi�G���A88������)
�b�W�I��͂Ƃ��������т����N�\
>>742 ����A�P�Ȃ鐅�����p�̕⋋�͂ł���
���������ڂ��ċ}�����i�͉��R�m�r�[�̔����͑�����ɓo�ꂷ��ˋ�͈ʂ���������
�������p�J�^�p���g��ݒu���Ė{��40�m�b�g�̐�������400�m�b�g�Ő��ʂɑł��o���̂ł�
Foudre�͐^�̉���3�{������ŁA��������O�̍b��4�ǁA���̍b��4�Ǔ���
�q���͂Ƃ�������͂Ƃ����P�g����͂Ƃ��A�A�j���ɂ����Ȃ������Ȃ̂�
>>750 ������͂̓t�����X�̃V�����N�[�t�i����ȁj�A�������͓��{�ɂ��������A�������Ă��Ȃ��̂͊C��R�́E���V�����炢���H
�f��ɏo�Ă��郄�c�͋���ł����ǂ�w
70�N�ゾ�������ȁH�ʂ̎����ɐ�������͂Ƃ��̐������̐����\�z���������ƁA10���N�O�̊ۂɍڂ��Ă��L��������
���^���_�[�Ƃd�c�`�i�h�l�`������10�l����������{�͐푈�ɏ����Ă����@���@�Ȃ�Ƃ������_
>>748 ���ڒ��͑S��7.8���ŏd��14�g�����x17�m�b�g�@�����͋���1�{�݂̂Ƃ������������قǂ̓��U��
����2�`3�{�H����Ă��퓬�q�s�p���o�����Ⴄ��a�^�̐����h��͂��āA������ɂ͓�����O�ɍl���邯��
>>755 �����͑D�̂̑傫���ƌ����L���ȗv�������邩�ƁB
�����h��ɑ���v����
�E�������P�{�Ă����̂܂ܐ퓬���p�������邱�ƁB
�E���ꌽ�ɋ������Q�{�Ă��A30���ȓ��ɌX�Ε�����Ƃ��s���퓬���p�������邱�ƁB
�������Ǝv���܂��B����ł̔�Q�͌y�����{�ł��ˁB
�������ゴ�`
�f�U�C���Ƃ��Ċ������Ă�悤�Ȃ�����悤�ȂƂ��낪�t�����X�̖͂���
���m������ŗV���D�Ŋ��Ă����ȗe�p
>>750 �Ȃ����P�g����͂̓A�C�I������͂ɑ�������v��~�܂�ɏI������B
>>755 �p�����j�^�[�͉��݂ɐڋ߂��ė����C������̂ŁA�@����̃o���W�͕K�{
>>757 �{��A�j���ɏo�Ă������B
>>757 �s�v�c�̊C�̃i�f�B�A�ŃK�[�t�B�b�V���Ɉꌂ�ł�������^���悤
>>757 �͐�C�͂̂������݂�����
����Δn�v�ǂ�41�T���`�C�����ė��p����
�y���̑D�̂��u���a���p���܂���|�q�D�ł���[���D�ł���[��Ƌq�D�⏤�D�ɂ��ė��p���Ă��ȁA�����푈���n�܂�����
>>766 �y���͂܂������邯�ǁA
�_���e���A���M�G�����q�D�ɂ���Ă����������R��������Ȃ�
�̎Z����͊m���ȏ�ɁA�ۊǂ������D�̂ł��Ȃ�����
�㉺���Ђ�����Ԃ������̃J�b�g���f������
�㉺���Ђ�����Ԃ��Ċ͍ڋ@�͂�����H
����Ȃ��Ƃ����킸�ɁA�n���Ƀ��r���X�[�c���B���Ă���Ƃ��炢�����Ă��������I
�n���ɒ���a�^���B���Ă��邭�炢�����Ă��������I
>>771 ����a�^���āA���b�œK���̕����H����Ƃ�51�Z���`�A��3��̕��H
��҂͌��Ă݂������ǁA���̑�a�^�̕����D�G����ȁc
�O�i�b����2�ǂ���炸����̕��͓��^�ɂ��Đԏ�Ɣ�r����悩�����̂�
>>773 ���ꂾ��������������X���̕���������łȂ��́H�i�l�����邩�͒m��Ȃ����j
�q��@�̒��͂ɉe���̑傫���r���̏����Ɏ��s���낵�Ă�������̕��������
����������̊͋��≌�˂͂����������B�������̂����K���̕��i
>>775 �C����p�̓x�A��������ł́H
���^�̒��͐������u�Ƃ����^�͋��Ƃ�������肪����
���łɋ������ˊǂ��Ō�܂ő����������\��
>>773 ��s�@�𒅊͂�����̂ɁA�ǂ�����čb��Ŏ~�߂邩���s���낵�Ă�����
�͂̑��x�ő�ɂ��āA�q��@�͂��肬��܂ő��x���Ƃ��āA�l�Ԃ��~�߂�Ȃ�Ă���Ă��B
�܂��c�����̐��������ł��ĂȂ����̂��b�B
����ȃC�M���X�̏��Ă����̂Œ��͒��ɂ����͂ł���t���[���A�X��2���������āA
����ɂ��悤�ƂȂ����B
���˂̌��͓V�邪�֓���k�ЂŔ�Q�ĉ��ꂪ���ɂȂ邱�ƂɂȂ�A
�H�����x�ꂽ����́A�P�Ăł̎������ʎĊ͔��܂ʼn��ˉ������ꂽ�B
���̐v���͉��˂̓����͂����̐��������̋�ԂŁA
�O���G���x�[�^�[�ɉ������q��@���㕔�G���x�[�^�Ɉړ������邾����
�펞�i�[�ɂł����Ȃ������B
>>773 ����A�[�J�C�u�X�Őԏ�����Ō��������
���L�V���g���݂����Ȋ͌^��猟�����ꂽ�}��ϑJ���悭�킩���
�O�i�����ăA�C�f�A�͈����Ȃ��Ǝv�����ǂȁB
��s�@�̔��B���͂₷�������
�O�i���̍ŏ�b��300m�A��i��500m�A�O�i��800m���炢�ō��A
>>782 �i�[�ɂɃJ�^�p���g�����Ă����ċ��́A�����I��2�i��s�b��
���g�������̂��~�낻���Ǝv������
>>765 ���@���K�[�h�͎��ۂɋN�H����5�N�O���A���邢�͂���ɑk���ď��̍�����
R����C���ė��p�ŋɓ�����������́i����^���m�́j���x�[�X�v�������ł��Ă����
���ꂪ���~���ɂȂ������炱�������ɋN�H�ł���
���������Ƃ���1940�N�x�\�Z�Ō��������肵�Ă����킯��
�����̍����͐�̓X���Ȃ̂ɋ��̘b�肾�����̂ŁA
������������q��@�������Ă�����ɏ�铋����{��������Ȃ�
>>788 �}���O�ő�a�^���Ȃ��ŋ����Ȃ�v���Ēߌ^�ɂȂ�B
���{��A�_�ː��A���A����O�H�œ��^4�ǂƂ������ƁB
���̌�������Ȃ��P�^�������Đi����̑��D���Ō����J�n�ɂȂ�B
�Ɍ����b�����\��ɍ��킹��Ȃǂ̑��������������A�Ēߌ^4�ǂ͋}������Ύj����葁���Ȃ�\��������B
�܂�������Ƃ���ōq��@���Ԃɍ���Ȃ��̂�96��Ƃ��悹��H�ڂɂȂ肻���ł͂���B
>>781 �͂���̓G�͍̊ڋ@�͂u�s�n�k�ŃW�F�b�g���i��40�~���`�F�[���K�������Ȃ�ȁA���������^
����Ȃ̗���łǂ��ɂ��ł���킯������[�A���������̂Ȃ�G�̕P��2�i3�i������O�Ȃ̂�����[��
���{�C�R�ɃA�p�b�`��n�����[��������R�i��ꂪ�����Ȃ̂������āE�E�E
���i���̈�Ԃ̖��_�́A��ԒႢ�͎͍b���g���鎖
���m�ȃQ�[���[�ɐ������Ă�����s�\��������u���Ƃ�
��荇��������X�^�C���͎~�߂��B
���X�v�Ƃ��̊i�[�ɂ��璼�ڑł��o���J�^�p���g�͗ǂ����Ɍ����邯��
���i�[�ɂ��璼�ڑł��o���J�^�p���g
�ΖȂ牌�L���Ȃ邵
http://nighthawk.o.oo7.jp/aircraft/data/jpn-bb-mutsu-view.html �����ł����˂肪�o�Ă���Ƃ���Ȋ����ɔg����B
�ʏ�͑D�Ȃ�g�悯���b��ɍ�邱�Ƃ��o���邪�A
��s�b�͂���������ɂ͂������A�b���`���Ċi�[�ɏo������ɒB���Ă��܂��B
��l�͑������ŗ�鈂���Q��O�ɉ���͑�����ɓ��������ǁA
���̉e�����Ċi�[�ɂ��͎��t���������������˂ɂ���������Ă͔ی������B
>>799 �����Ⴄ������w�ɂ����Ăr�k����Ă������r�k������ɂ���Ƃ��̍���w�\���͉��������Ď��ɂ�����������
�ł��܂��ό��q�ň���ۂ����肾���畗�����Ȃł������Ǔ���I�������獢���ˌ�������
�X���`�̏�ɃA�j��������ɏo���Ȃ��z���n���łȂ��ĂȂ�Ȃ̂��H
���Ⴀ���݂܂���2�x�Ə������݂��܂���Ƃł������Δ[�������?
�����܂ōr���̂͗�Ƃ��Ă͂��ꂾ����
���g���Ə��z�����g�ւ̑�͑厖�Ǝv����1�R�}
�����s�����}���ق�4��16���܂Ő�͑�a�W���J�Â���Ă���B
�����m���̊e�펑���W���ŁA4��7���ɂ͌����̍u��������
http://soka.mypl.net/soka_life_learn/F000000000031/news?nid=161 �X�L�[�W�����v���Ŋ͎�������グ�āA
��s�b���Ⴂ�ʒu�ɂ����Ċi�[�ɏo�������
��̓X���ʼn��̂����i���̘b�ɂȂ��Ă邯�ǁA�Đ�͂ł��Ă�����2�K���ĖC�����D��
>>809 ���E����̔g�̔�Q���āA�����i�[�ɂ̋��ɂǂ�ȉe��������́H
���̃t�H�[�h���̌����Ăɓ�i���b�̈Ă���������
�����i�[�ɂ����ї��q��@�Ƃ͂���@����
>>813 Z�K���_���ɏo�Ă���A�[�K�}�̃J�^�p���g�f�b�L��z�����Ă���
>>811 ���i����s�b�̉��i��s�b��
�q��@�o���͎͊ɂ���B
800�̉摜���炢�Ȃ�܂��b����邭�炢�����A
806���炢�ɂȂ�ƍ��E����b�ɏオ�����g�̈��͂Ŕ����Ԃ����B
�쒀�͂̊͋��������藴鈂̊͋������Q���肵�Ă�́B
>>813 �ȂA>809�̊i�[�ɂ���Z���]�X�͗�鈂���Ȃ��ĎO�i���̘b��
������ɂ�����
�܁A�X���`������ǂ��ł��ǂ���
��鈂̊͋�������
�S���A���D�ł��r�V�Ŏԗ��b�ւ̔g�̑ł����݂ŐZ���]���Ƃ����邵�Ȃ�
�P�Ă͔�s�b�O�[��g�ɓ˂�����ň�����
�j���� in RN
�r�b�N�K���Ɍׂ����ĉx��ł���Ȃ�āc
>>693 ��ڽ������͂ɊW����b�Ȃ�Ȃ�ł��������롐��vs�T�C�p���v�ǂق����ł�����B
���������ΐ�͂ɂ������������ڂ���Ă��ȁB
>>824 �������I�̍��͂����m�炸�A����ɎQ���������{��͂����ڂ��Ă����u�������v�͒P�Ȃ��^�̓��Β��ŋ����Ȃς�łȂ���
�T�C�p���ɐ�͂Ƃ�肠���邾���̑���a�C�ݒu�o������@�B�͂�����{�R�Ȃ��J���Ȃ�
�@�B�͂Ƃ������A
�v�ǂ���ł�������͂Ȃ�͑��͖���
�T�C�p���͑�3530�D�c��������3�ǂɕߑ�����đD�̔��������v�A������X�O�O�O�l�̓�����������o�������̂̑����̑����͊C�ɏ�����Ƃ������ʂɂȂ����B
>�@�哌���푈�J��ɓ��{�C�R�ɂ���ėv�lj����ꂽ�@�u�R�͓��v�@�}�j���K�n��
http://sakurasakujapan.web.fc2.com/main02/marianasaipan/area34.html ���̗v�ǂ�
>���{�R������i�C�R��܍����n���j�͂���܂ł̕ČR�͖̊C�ˌ��E��P�ɂ���Ėw�lj�ł��E�E�E
>�u�R�͓��v�͖�1���ԂŕČR�����ɐ�̂��ꂽ�B
��股���Ǔ��{����v�ǂ͖@����
>>824 �݂����ɊJ�������Ă������ăX���`�Șb���X�Ƃ�������A�z�����߂���
�W����ƌ����Ă�����͂������������ł��̌㉄�X�ƊW�����b���������ǂ��킯�Ȃ���
�h���g�̂܂�T�r���R����ǂ�����Ŋ̐S�̎h���g���ЂƐ�ɂ��������Ȃ���Ԃ͍��\�ł����Ȃ�
�X���`�w�E����ƁA
�X���Ⴂ�Șb�������͉ߑa���ė���������܂��}�V
>>824 �q���͂Ȃ�Ă����݂������A���̘b��₻�͍̊ڋ@�̘b��ł��A�S���X���ɖ��W�ł͖���㩁i����
��͂�����C���ʂɎ��{���Ă�����ȁ`
�j���[�J�b�X���ł̏����@�������͂����Ă�ۂ����ǁc
�i���݂邩���芮�S�~���ς݂��Ė�Ȃ�����
>>836 �X���I�ɂ͐�͂⏄�m��͂�����ɉ������ꂽ�͂�A���ꂪ��͂Ƃ��Ċ������Ă�����ǂ����������ʂ���H
�v�悾���ɏI������q���̘͂b��Ȃ�X�����v������͂Ƃ͖��W�ɐv���ꂽ���̘b�͖{��ɂ���̂͊ԈႢ����
>>838 �ΒY�A�H���A�^���A�e��Ƃ����ڕ��w�ǐς�łȂ������ŋi�����オ���Ă�Ƃ��H
F-35B�̋��鍡�Ȃ�A
�Ȃ���͂ł͂Ȃ����nj�q�͂͂�Ȃ���g�r�r�|�Q�����Ēe���ϑ��݂����Ȏ������Ă��܂����B
���̋Z�p���ƖC�e���}�X�^�[�ƃX���C�u�݂����Ȏ����o���Ȃ��̂���
>>845 �\�����ǁA�C�e�����˂���Ă���Ƃ������́A�ʏ�G�͂����ɕߑ�����Ă���Ƃ������Ȃ�B
�܂�A���ʂ̃��[�U�[�U���C�e�Ȃǂ��g�������������B
>>843 �C�M���X�Ȃ�풆�ɐ�͂̍q����p�~���Ă邯�ǁA���q���͐�����s�@�ϑ��H
>>838 ���͂�����ς�p���ő������̂��ȁH
�e���ϑ���SH����Ă�C����UAV�������Ă郍�C�����l�C�r�[
�_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO �_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO ����J�����[��I
�����������I�������c����
�C�������˂������ق������`
>>835 �����m�푈�ł̃A�����J��͂͑�ʂ̎�C�e����������A��ȗp�r�͗���ˌ��B�Ί͎ˌ��͋ɏ����B
�Ƃ���ΕĐ�͂̎�Ȏg�p�@�ł��闤��ˌ�����邱�Ƃ͉��̖��������B
��������͖{���̗p�@�ł͖����B�{���̗p�r�Ō��Ȃ�A�n���C���i�V�ŁA���Ċ͑��������邵���Ȃ�
��꒼�q�͂Ƃ��ċ��͂ȑ�v���b�g�t�H�[���Ƃ��Ă����������Ί�Ō���Ă��ǂ�
���Ȃ�t�x�݂̂����ɂł��邩���
�����O�}�K�W���Ɍf�ڂ̐^��p��C���ʼn̊C�ɂ���ړI�̑�a��
>>857 �K�X�^�[�r������51cm4�A�����̂̎��_�ʼnΑ��ƒf���o����
�K�X�^�[�r���͂Ȃ���w
�K�X�^�[�r�����̂́A��O����͑D�p�@�ւƂ��Č������Ă����A�j���������ƌ����Ƀ��\�[�X�˂����߂�
��͂Ȃ�Đ^�ł�������������o��悢�̂ł����āA
�d���𐆂��Ĕ��d�@�Ă��̓d�C�œd�C���i����
>>862 �A�����J�̓j���[���L�V�R���ō̗p���ăe�L�T�X���A�R�����h���Ƒ����Ă�A���L�V���g�������̗p���Ă�B
�Ȃ��̗p�����̂��A�Ȃ����̌�m�[�X�J�A�_�R�^�A�A�C�I���ƒʏ���C�^�[�r���͂ɖ߂������H
�ڂ̑O�Ɍ������铹�������璲�ׂĂ݂���ǂ����ȁH
����Ȃ̂�ʎY���Ƃ��čD���ȂƂ��ɉg�q���āE�E
�ꉞ465�n�͂�3�m�b�g�o��E�E
>>857 �^��p�̊C����
���̑O�ɑj�~����Əo������ł��낤�đ����m�͑��̌��̓K�������B�T�N�b�Ə����o�����Ă��Ȃ�����Ƃ����O��
�n���C�̍q���n�Q�ɑ��Ă͊�P�ŋ�P�����Ēׂ��B��P���s�Ƃ��ׂ���Ȃ����͍l���Ȃ��Ƃ����s���̗ǂ��O��
�̏�ɐ��藧���Ă��邩��Ȃ�
����ɁA�j���̑�a34�m�b�g�ĂȂ痝���ł��Ă��A
�쒆�̃t�B�N�V������a��34�m�b�g�o�����������R���߂��邵�i���̌�q�Ƃ������������炵���j
�ǂ��]�����Ăǂ��]������Ⴂ���̂��Ă���
>>860 �ǂ݂̂���C���͂┭�d�@���p�@�A���т̂��߂ɑ�ʂ̏��C���v�邩���^�̃{�C���[�ς�
���ɂȂ邾�낤���A�K�X�^�[�r���p�R�����y�����K�v�ɂȂ�̂ł́H
�ׂɑ�a����Ȃ��Ă����̂܂ܔ�b�Ɩ����A���łɂƂ˂����Ő^��p���̊C�ɂ��Ă��悩������ȁA���������Ȃ����Ƃ�����
>>872 �G���̏��݂�������Ȃ��̂ɁH
��������b������36cm����n���C�̗v�ǖC�A�E�g�����W�o�������}���͌��킸������
�������Ċ�P�U���o���������̂���Ղł���A�����͂�~�b�h�E�F�[�̍q������ɂ������Ȃ���`�p�U���Ȃ�ĕs�\�ɓ�����
��b�E�������������ǂ̈ʒu�ɋ������l�������ȋY����������͂����Ȃ�����
H45�^���ĕ����̃l�^����������
�������ˁA�����I�Ɋj�����ɂ����Ă������ˁB
���j�^�[�Ȃ�S�U�Z���`�Ŏ˒��O����̊C�ɂł���ȃn���C
>>876 �����̃l�^�Ƃ������A
�h�C�c�R���L�́u���C�F�������njR�̖ʎq�̂��ߐ}�ʁE�\�z��������Ă݂܂����V���[�Y�v�̃A����
�������Ȃ�14�C���`��RAP�C�e���J�����Ď˒�50�L�����[�g���������ł��Ă��
����̓l�b�g����̐l�Ԃ�������ˋ�͂�����M�����畨���̎���Ď�
80�T���`�C�Ȃ畚�����ł���悤�ɂ���
>>883 5�ǂ̐�͂����̂��ė�ԖC��ςނ�
���[����~���Ƃ肠�����ǂ̕����ɂ������Ƃ��o���邼
24�Z���`��ԖC�Ŏ˒�5�����[�g��������
�y�ʖC�e�ɂ��ď���1100m/s�ɂ���Ⴂ�����B
���O��t�x�݂̑�w���H
�����̃Q�[���[�ɂ܂Ƃ��Ȓm���Ȃǖ����B
�N�������ʼnɂ����ė]�����V�l���Ǝv����B��̂������邶���B
254mm�A��2��@105�����A��4��A6000�n�́@15�m�b�g
�����D�Ȃ̂��E�E�����鎩�M�͖����E�E
�ʐ^�������ƕ��ʂɌ�����s�v�c
���̂�����Ȃ��V�l�̌�y���C���^�[�l�b�g�Ȃ�B
>>872 �n���C�̖C����Ăǂ���̕������Ă��H
�^��p�R�`�������p�ł��̉��ɐ�͕����ׂ���R�`����_�������ł���A�͂������ɂȂ����B
>>892 �͔���������i�ɂȂ��ĂĂ����ɐ��l�̐��������邯�ǖ��Ȍ`���Ă�ȁB
>>893 �ł܂���w
�c���ᔻ���鉴�l�̂��n�~�w��
�n���C�͖C�ˌ����Y�͐�͌Q���n���C�v�ǂ��˒��Ɏ��߂邠���肩��X�e�[�WGO�I�ȃC���[�W�Ȃ낤
�Ђ�[
���A���Ȃ��������v���܂����H�A�����ł��B
�X�Ύ��̐l�܂߂��͓����̕Ќ��ړ��͑S���̖��ʂ��āu�����v�̐����c�肳����Ă܂�����
>>900 ����ች��g�����̐Z��������A�X�ɐZ���i�s��������Ȃ�
�ނ��떳������������d�ʕ��������ފ͂̍ە������ď�������ׂ����̂��҂��ڌ����Ă��邵
>>897 �^��p��P����Ȃ瑾���m�͑�����ł��Ă邩��A����Ă��Ȃ����Ƃ͂Ȃ���
�S�Ă̍��͂��n���C�C���ɒ������݁A���ԑD�͂��ׂĒ��p
���R������͑S�����~�A�{�y�h�q�͒��߂�B
�o�ς̓Y�^�Y�^�A�����̖���e�ɂ���V����B
�I�������Ⴆ��Q�Ȃ��ł��A���͑��͔��g�s��
����ɖC��ׂ��Ă��㗤��͕̂s�\����
>>902 �����܂Ń����Ȃ�f���ɏ㗤���Đ�̂��Ȃ�
>>902 �P�Ȃ鎩���e���݂����Ȃ����......
�ő��ړI�Ǝ�i���ǂ���̘b����ˁ[��
�n���C��̂ō��͂���ׂ��Ă����Ȃ��̖��ł��邩������Ȃ��B
�ςɐ�킸�ɔ����������Đ瓇�Ɠ슒���A�����J�ɂ�邩��n���C�Ƃ��̎��ӓ��{�ɂ����Ƃ�����Ƃ����݂��������������������̂ł�
�Ȃ�����Ȏ��ʼn����ł���Ǝv���̂��H
���a12�N����C400���Q�O�ǂ�������
�u���B�ƒ��N�������A�����J�̂ɂ��Ă�������Ζ����傤��������x�X�g
�n���m�[�g�̗v���ۂނ����̘b�Ȃ̂ɁA
>>902 �t�߂ɋ�ꌒ�݁A��n�q�������ł܂ł����ĂȂ��A�{�y����B-17�̑��������Ă���
�I舂ɋߊ����Ԃ���Ȃ�
>>908 �ǂ���������Ȃ�p�i�}�^�͔����Ȃ�Ă�Ȃ炢�����ǂ������ƌ����邩��
���Ƀp�i�}�^�͂̔���ȕ�����p�𐿋�����邵�A�������Ă�������̊ۑD�͂��炭�̓p�i�}�^�͎g�p�֎~�ɂ��ꂽ��������Ȃ�
�������̕��������Ɛ�㕜���ł̒Ɏ�ɂȂ�
>>910 �n���m�[�g�̏����������܂���ĐΖ��֗A����������Ȃ����Ď��Ȃ炻���푈�����A���ɏ������ނ̈��������ɋ֗A���������Ȃ�ΕĐ푈���闝�R�����ʖ����Ȃ邩��˂�
���B����ɉ�����鎖���ő�̖ړI�ŁA�Γ����͂͂��̎�i�ɉ߂��Ȃ����
�n���m�[�g����ő嗤����P�ނ��A�O��������������E������킴�킴�A�����J�����{�Ɏ���o���Ӗ���������
�����̓X���`�B�R�͐�������A�푈������킦�A�ƌ����Đ키�̂��d��
��C�����āA����̒��S����ɏd�S������悤�ɂȂ��ĂȂ��̂��ȁB
���S�������Ŏx���Ă���v�����̖C�����Ⴀ��܂������̐S�z�͖��p
>>915 �Ȃ��Ă��
�C���ŖC�g�̒ނ荇�����Ƃ邽�ߖC���ɂ͏d�肪���Ă��āA�C�����̖C�g�������o���邾���Z�����Ă���
�C�����A�C�e��������ɂ����̂Ɍ�ǂ��ُ�Ɍ������Ă�͂̓o�����X���Ƃ��Ă��邩��
�ےÂȂ̖C����������ɐ���Ă�̂��o�����X�̂���
>>903 ���͂ɔ䂵�ĉߏ��͑���������ɖ��ԑD���ʂ��S�~�N�Y�Ȃ��
��̂���ɂ͑S�����p���Ă��܂�����Ȃ����Ęb�������Ă��ȁE�E�E�E
>>913 ���{�R�̒����ւ̐i�o���A�����J�Ƃ̑Η��݂��ꂪ�����m�푈�̌��ɂȂ����炵����
���{�R�͉������߂Ē����֍U�ߍ��́H�Ȃ�ł���ɃA�����J�����������́H
>>920 �܂��Ӊ���ŏ��ɍU�����Ă�����ŁA���{�Ƃ��Ă͔������Ȃ��킯�ɂ͂��������B
������ŏ��͉p�Ă��A���@�ҏӉ�炵�߂鐳�`�̓��{�Ƃ����悤�Ɏ����グ�Ă��̂�
�ł��싞�ח��ŁA���{���Ӊ����Έ��߂Ȃ����������Ă�����{�ɂƂ��Ăǂ�ǂ�s���ɂȂ��Ă䂭
�p�Ă����{�������̗����S���Ƃ��߂���C���Ƌ^���A�����n�߂�͓��{�������c�������łЂ��Ȃ��Ȃ��œD��
>>920 >>921
21�ӏ�v���˔����^����(�F�X������)���������E�˖��B���ρˉؖk�����H��ˉؖk����(��)�f��
�˓��֓Ɨ��H��˔����^�������ˎx�ߒ��ԌR���������˓G�O���K��ḍa�������ˑ��C���ρˎx�ߎ���
�����͋ォ�����œƗ��Ƌ@��ϓ������߂����{�����ӂ��Ă������A�f�Ղʼn��Ăɕ����n�߂�ƁA
�����˒n��苒�˖f�ՓƐ�
�@���J��Ԃ��悤�ɂȂ�@��ϓ���N���Ă��܂����B
�悭������u���F���A�����J�ɂ�����v�K�v�Ȃ�đS�������B���ʂɏ�����Č����Ȗf�Ղ��p�����Ă������ȂɓG������Ȃ��B
>>920 ���X�̓��V�A�̓쉺�ɑR����R�����_�m�ۂ̈�
���͑���̕s�i�C��Ƃ��Ă̎s��m�ۂ̈�
�����s�i�C�ő嗤�s��~�����͉̂��Ă��ꏏ�����A���ő債���]�����o���ĂȂ����{�������̍����ɏ悶�Đ��͊g�傷��͖̂ʔ����Ȃ�
���������e���̎v�f���Ԃ��������ʂ�921����922������������
�����͐�̓X���Ȃ̂ŁA
�l�^�Ɍ����̂����Ȃ��A��͂̎x���C�����Ȃ��i���m�͂�쒀�̖͂C���ł͑ʖڂ炵���j�Ɛ�ǂ��D�]���Ȃ������Ă����������H
����킯�˂������B
�P�ނ��鑬�x��葁���i�R���������
�[��
>>928 �����ŁA�Ȃ��L���ȌR�����\�[�X������Ȓ����ɒ���t�������Ƃ���>920�ɖ߂�
��������̐푈�Ȃ��A��a�̃n���C�C���ɘb�������悤��
���^��p�ɕ����͖����Ƃ��Ă���a��Ă���悩�������
�A��čs���ĉ�����́H�n���C�̖C��͊O�֎R�̉Ό��̒��ɂ����ŊC���猩����
�v�H���ĂȂ����͖̂���
�r�X�}���N���POW���ČP���͂ł��Ă��낤��
1941/1/19�A����5/24�Ƀf���}�[�N�C�킾����
>>925 ����������͂̎x���C���������ɂȂ������͂����Ă��A��ǂ��D�]�������Ȃ�đ��݂��Ȃ��̂ł́H
>>932 ���ׂ̈̒e���ϑ��@���Ă�����
>>936 ��͂����S���đΒn�C���o���鎞�_�Ő��m�ۏo���Ă�������
���{�R���w���_�[�\���ɍs������ԖC���Ȃ�Ă̂͗�O��
�ŁA���̗�O���B���ǍD�]����\���������P�[�X���Ǝv��
�T�C�p����C�e�A����ւ̊͑��˓��͌�l�ߑ���\�͌����Ă��鎞�_�Ő�ǂ̍D�]�ɂ͌q����Ȃ����낤
�Ȃɂ����Ă�w
>>937 30�N��ɍs��ꂽ�ϑ��@���݂̂̒������ˌ����K�̌��ʂ�
�u�ϑ��@����̌���������ᐳ�������v���������ǂ�
���̗L���ȃE�[�`�����㗤�K�[
���Ɏ����ނ���Ȃ���
>>935 �ǂ����Α��Ȃ���^��p�̓��t���炷�Ƃ�����Ηǂ������
>>943 �ǂ����n���Ȃ���F����͂Ƃ��D���ɓo�ꂳ���āA�Q�[���X���ɂł������Ă���������
���}�g������A�������Ȃǂ͈ꔭ����
>>943 ���̎������炷�ƂȂ�ƂP�N�x�����i�n���C��P��12���̂��̎����ł��邱�Ƃ��d�v�ȗv�f�j�A
��ω��ɓ��{���ς����邩�˂��H
>>947 ���N�J��ł��������BABCD��͐w����N�x��ƌ������Ƃɂ��Ē��날�킹��
���N�J��ɂ���h�C�c�����X�N���O�Ŏ~�܂��Ă邠���肾����
>>948 �P�N�x�ꂽ����{�̍��͂��Ȃ胄�o�C��H
�����푈�̉e���ŁA���{�̍��̓s�[�N��1937�N�Ƃ������Ă��
>>948 ���N�ɂȂ�����G�Z�b�N�X����A�C�I������͂��������Ă���̂ɁA���܂���^��p����
1941�N7�������_�ŁAABCD4�J�����犮�S�֗A���ꂽ��A�y����10�����A�d����1.5�����������ԃX�g�b�N�͎����Ȃ��Ƃ̊��@����
>>948 �����̓s���ʼn������`�������Ȃ�]���ł��B
948�͂ǂ������z�Ȃ��牽�ł���������A�ƈ��̂肵�Ă邾���Ȃ̂ɂЂǂ���������w
���z��L�X���Ƃ��Ȃ�悩������
>>955 �]���s���ƌ����Ă���H
�X���`����̌�����摜�u���Ƃ��]
>958
���܂ꂽ��������{����}�C�i�[�W�������������C�����邯��
��O����R�I�^�͑�В��肾����B
�ł��吳���Ƃ��R�͌����Ă���������邵��͖��o���Đ搶���J�߂�Ƃ����Ȃ���
�Ƃɂ������s��p���V�Q�ÎQ�W�Ȃ���Ⴂ�Șb�����b���l�Ԃ͂ǂ��ł������邵�n���ɂ����͓̂�����O
�x�m�A�~���A�����A�O�}�A����A�����A�F���A���|�A�}�g�A����A�Ɣn�A�ɐ�
�S������x��ɂ���Ĕ����͑��~�����ƂȂ�C�����͂悭�킩��B
>>964 ���[���ƑO�A�F�B����ɂ��������̌������B
��펞�̐�́A�d���A�y�����킹��55�ǂ��܂������Ă��B
�F�B���������B
�u�������ȁ[�B����Ȍ|�l������ȁB���[���ƁE�E�E�������I�~�X�^�[�~��v
�E�E�E�E������Ăق߂�ꂽ�̂��H
�z���^�A�[�_�^�A���^�E�E
��Ȏ����������펞�̃A�����J�C�R�̋쒀�͂ƌ�q�쒀�́A�����͂��܂߂�P�O�O�O�ǂ��Ȃ����H
�A�����J���ƁE�E�͖��ȑO�ɋ������̐����������邩�ǂ����E�E
>>962 �܂���O�Ƃ������풆�h���ȁB
�����w�Z�ł̘b�Ȃ̂�
>>940 ����͓��ڕW������ł����āA����̌Œ�ڕW�ւ̒e���U���Ȃ�ČR��������O�ɂ���Ă鎖����B
>>567 ���q�͐����̘͂b����ˁE�E�E�E�B
>>971 �n��ւ̊Ԑڎˌ��ł͊ϑ��@���Ă����̕ӂ�̒n�}��̋��ɂ����������ސ��x�����Ȃ��B
�P�˖ڈȍ~�͔����A�Ђ̉��Ŋϑ��s�\�ɂȂ�Ƃ�������������Ⴂ���̂��ˁH
�����牄�X�ׂ��܂Ő����������ނ����Ȃ��B
�܂���������
>>973 �����猂���͂�������Ă�
���������������悤���Ȃ����猋�ǂ͏��X�ɍ���Ċ��I�ɖ������
����C��͑���a�ɂȂ�قljB���悤�������Ȃ邩��G���A����Ȃ��ăs���|�C���g�Ɍ������Ǝv������
������A�s�X�n�Ƃ��~�n�̍L���H��ȂǂɎ蓖���莟��C�e���������ނ̂Ȃ�͖C�ˌ��͂���Ȃ�ɗL��
�Ζ����~��{�C�ł��Ȃ��̂ɓ�i�_���Ԃ��グ��C�R�m�����Ĕn���Ȃ�Ȃ����Ǝv����
���۔n���Ȃ�Ȃ��́B���a�P�S�N�̎��_�ŁA�ޒJ�����͊C�R�͂ǂ�ȂɃA�����J�ɂ����߂��Ă�
���a14�N��16�N�ł͐��E����Ⴄ
�t�����X�~���̉ߒ��ŃC�M���X�R�ƃh�C�c�R������ԂɂȂ�������
�ƃ\��̊J�n�Ńh�C�c�s�킪���肵����������
�p�����炷��ΐA���n�����������グ���邩��A���R�Q���܂ł͍s���Ȃ��Ă�
�p���C����n��Ȃ��h�C�c�Ɍ����珟���ڂ͂Ȃ�
���B�Ńh�C�c���푈�n�߂�����A
>>977 �C����͖C�Œ@���K�v�����������ŕ����Ė��������ꂿ���������A�𗧂����̏ؖ��݂����Ȃ���
�j�~�b�c�̓T�C�p���ւ�138,8000���͖̊C�ˌ���s�\���ŕs�O��ƕ]��
�ꎖ�������ȏt������ɂ͉������Ă����ʂ݂�������
>>988 �����Q�[����ʂ͗L�������A��{�I�ɖ��ʂȃ��j�b�g�͏o�ė��Ȃ����ˁB
>>977 �A�C�I���^��͂���ꎟ�p�ݐ푈��UAV�Ŋϑ����Ȃ��琅�����̐�̖ڕW���͖C�ˌ��������т͂���B
������20���I���ɑS�͑ޖ������ʂ��p�Ό��ʂ�����Ȃ��̂ł���
�����͂����Ă��A�Y���E�H���g����AGS���A�Ί͎ˌ��͒f�O���ė���C�������z�肵�Ă��邱�Ƃ�����A�͖C�ˌ��̖��͌p����
�Y���E�H���g�͍����Ȃ肷��������āA���܂������炻�ꂵ���c��Ȃ�������������
�Ⴄ��
���̑Ί̓~�T�C���O�a�U��
�͒��ɂ�闤��C���̗L�������̂̓y���[�͑��̍�����S�B
�V���A���g�}�z�[�N����Ȃ��Ċ͖C�ˌ����Ηǂ����������
���e���ڂ������^�����D�Ŏ����U������邩��ߊ��Ȃ��̂��B
>>993 �͂����茾���Č�q�̋쒀�͂�����͂̕��������B
���s�͒��͍R�������s�����ċt�ɕs������B
�͖C�ˌ��̋��Ђ͐��ۖh�䑤�ɘI�V�w�n���l�Ƃ����āA���A�w�n��n���w�n�╪�����R���N���[�g��
���̃X���ւ̌Œ胊���N�F http://5chb.net/r/army/1520287947/ �q���g�F http ://xxxx.5chb .net/xxxx �̂悤��b �����邾���ł����ŃX���ۑ��A�{���ł��܂��BTOP�� TOP�� �@
�S�f���ꗗ ���̌f���� �l�C�X�� |
>50
>100
>200
>300
>500
>1000��
�V���摜 ���u�y�R���z - �V�E��̓X���b�h74�����C�� YouTube����>3�{ ->�摜>29�� �v �������l�����Ă��܂��F�E�y�R���z - �V�E��̓X���b�h72�����C�� �y�R���z - �V�E��̓X���b�h73�����C�� �y�R���z- �V�E��̓X���b�h 86cm�C �y�R���z- �V�E��̓X���b�h 85cm�C �y�R���z- �V�E��̓X���b�h 87cm�C �y�R���z - �V�E��̓X���b�h 78cm�C �y�R���z - �V�E��̓X���b�h 82cm�C �V�E��̓X���b�h 97cm�C �V�E��̓X���b�h 110cm�C �V�E��̓X���b�h 104cm�C �V�E��p���X���b�h1��� �F����͑��� �U���X���b�h ���������X���b�h75���� ICOCA�X���b�h�@46���� goro's�X���b�h288�H�� �����I�C���X���b�h70�{�� Luxman�����X���b�h 42��� ���ҕ������X���b�h��77�ʖ� Luxman�����X���b�h 40��� �����݂����߂ĎX���b�h�@126��E�� �Ì��h���Ԃ₫�X���b�h 9�{�� �����݂����߂ĎX���b�h�@138��E�� �Ì��h���Ԃ₫�X���b�h 6�{�� �����݂����߂ĎX���b�h�@144��E�� �Ì��h���Ԃ₫�X���b�h 8�{�� �Ì��h���Ԃ₫�X���b�h 82�{�� �Ì��h���Ԃ₫�X���b�h 10�{�� �Ì��h���Ԃ₫�X���b�h 41�{�� �����݂����߂ĎX���b�h 140��E�� �Ì��h���Ԃ₫�X���b�h 27�{�� �Ì��h���Ԃ₫�X���b�h 67�{�� �Ì��h���Ԃ₫�X���b�h 22�{�� �Ì��h���Ԃ₫�X���b�h 63�{�� �Ì��h���Ԃ₫�X���b�h 79�{�� ���ؐU��q�����X���b�h 8�h��� �Ì��h���Ԃ₫�X���b�h 44�{�� �Ì��h���Ԃ₫�X���b�h107�{�� �Ì��h���Ԃ₫�X���b�h 69�{�� �h���N�GX���C�X���b�h23��� �ߑ㖃�������X���b�h�@��46���� Infosphere�l�@�X���b�h 4����� �Ì��h���Ԃ₫�X���b�h 103�{�� �̏d�ʃX���b�h60�`69kg��@6kg �� 70�X�[�v�������X���b�h 22��� �̏d�v�E�̑g���v�X���b�h 2kg�� �̏d�ʃX���b�h 60�`69kg�� 7kg �� �L�J�t�F�����X���b�h�@24�X�� �ꎟ�n��@�`���V�̗��X���b�h 22���� �{�[���p�C�\�����X���b�h28�C�� �I�i�z�[�������X���b�h 252�{�� �Ì��h���Ԃ₫�X���b�h �P�O�Q�{�� ���t�I�N���S�Ҏ���X���b�h 812��� ���t�I�N���S�Ҏ���X���b�h 808��� �{�[���p�C�\�����X���b�h27�C�� �I�i�z�[�������X���b�h 261�{�� �I�i�z�[�������X���b�h 258�{�� ��s�����a���@(ATM)�X���b�h 13��� �W���b�N�E�I�E������@33�X���b�h�� �y�ޓ��z�����������X���b�h 105���� === ���b�������X���b�h�`7���� === �y+�z�o�b�e���[�X���b�h�y-�z 91�� �y+�z�o�b�e���[�X���b�h�y-�z 90�� ���ǎ�������ĔY�߂�l���W���X���b�h77�l�� �T�����N�T���f�[�����X���b�h331���� �O��� �R�� ���p NIKE �g���r�X�X���b�h
09:55:22 up 23 days, 10:58, 2 users, load average: 8.27, 9.22, 9.52
in 3.4693682193756 sec
@3.4693682193756@0b7 on 020523